『人生の一冊の絵本』 柳田邦男 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
星は見えない夜もそこにあって
詩人の長田弘さんが二〇一五年に亡くなった。長田さんは、詩やエッセイの他に、すでに紹介された『最初の質問』のようなアメリカの絵本の翻訳にも、かなりの功績がある。この章では、長田さんが翻訳した絵本を二冊紹介している。
『いつでも星を』
まず一冊目は『いつでも星を』である。最初は犬と散歩している少年が見上げている空に、星がひとつ、きらきらと光る。そしてしだいに星が多くなり、少年少女も少しずつ増えていく。
静かな始まり方をする絵本だ。星空の広がり方がのびやかに描かれていく。子どもたちの“星遊び”が点描される。少年のひとりは、黄色い星を描いて切り抜き、ポケット入れる。
少女は金色の星を棒に付けて、魔法の杖にしたりして楽しむ。(抜粋)
訳文は、長田さんの詩のトーンになっていて、やっしい言葉だが、人の生き方や心の持ち方がじわっとにじみ出てくる。そして最後に素晴らしい言葉が添えられている。
<星が みえないよるも あるけど、 いつでも 星は そこにあるんだ。 よぞらのなかに>(抜粋)
『この世界いっぱい』
二冊目は『この世界いっぱい』である。海岸で幼い兄と小さな妹が遊んでいる。
<岩を、 石ころを、 小石を、 砂を>
<体で、 肩で、 腕で、 手で、 掘りおこして、 周りをかこんで、 ほら、 貝だよ>(抜粋)
そしてしだいに視野が広がり岩肌や荒々しい海岸、なだらかな丘陵の農村が広々と広がっていく。そして
<この世界いっぱい 古くって 新しい>(抜粋)
と書かれている。ところが、突然嵐が襲いかかり激しい風と雨で人々が避難する。
やがて嵐は去り、夕暮れの展望デッキに日没直後の空を眺める男のシルエットが描かれる。
<この世界いっぱい みたされている すばらしい 静けさに>(抜粋)
特別な物語はない。ただただ日常の断片を切り取ってつないだだけだといってもいい。しかし、その日常はなんと力強い肯定感に満ちていることか。その感覚は、どこから生まれたのか。(抜粋)
関連図書:
メアリ・リン・レイ(文)、マーラ・フレイジー(絵)、長田弘(訳)『いつでも星を』、ブロンズ新社、2012年
リズ・ガートン・スキャンロン(文)、マーラ・フレイジー(絵)、長田弘(訳)『この世界いっぱい』、フロンズ新社、2011年
まるい月に目を輝かせる赤ちゃん
昼下がりの乗客が少ない時間に電車に乗ると異様としか思えない光景が広がっている、と柳田は言っている。誰もがスマホかタブレットに熱中していて、窓の外の風景や空を見ている人が一人もいない。子どもを真ん中に座らせている親子三人も、会話もせず各々がスマホに熱中している。
そういう時代だからこそ、テレビを消し、スマホなどを切って(せめてマナーモードにして)、親が子どもに絵本や童話を読み聞かせたり、逆に子どもが親に読み聞かせたりして、絵本や童話の楽しい世界をこころに刻むことがとても大事な意味を持つようになっていると言いたい。(抜粋)
この章では、そういう時に是非、読んでもらいたい本を二冊が紹介されている。
『きょうはそらにまるいつき』
一冊目は『きょうはそらにまるいつき』である。はじめに、見開きいっぱいに、夕暮れが近づく公園の風景が描かれる。走っている子どもや散策している人など、いろんな人が公園に集まっている。その中に若い母親と赤い乳母車が描かれている。乳母車の赤ちゃんは、空を見上げている。
<赤ちゃん が そらを みています>(抜粋)
次のページには、ダークブルーの空に大きなお月様が輝いている。
荒井さんの絵は、どの頁もロックのギターがいきなりフォルテで始められるかのように、めちゃくちゃ明るい。特に赤と黄色のアクセントが強烈だ。三度も登場する赤ちゃんがそれぞれに月を見つめる瞳の輝きのなんと純粋なことか。デジタル文明など介在しない。いのちの自然な躍動が伝わってくる。絵筆をもつ表現者、荒井さんの内側に漲る生命観がほとばしり出たと言おうか。(抜粋)
『よるのかえりみち』
二冊目は『よるのかえりみち』である。この絵本は、夜の街の独特な味わいのある情景を描いた絵本である。夜おそくに母さんうさぎに抱っこされて、子うさぎのぼくが人どおりの途絶えた街を通って家まで帰る。その道ながらに、店じまいするレストランや本屋、ビルの窓から漏れれいる明かりや電話の声、・・・・・。
みやこしさんは、木炭紙に木炭やアクリルガッシュの絵具で絵を描いているので、木炭紙のザラザラした感触が浮き出ていて、夜の街の風景や窓明かりのなかの室内の情景が、しっとりした詩情で表現され、幼い子のこころに映る”よるのかえりみち“の情景が、読者の胸に静かに伝わってくる。みやこしさんの表現力はすばらしい。(抜粋)
関連図書:
荒井良二(作)『きょうはそらにまるいつき』、偕成社、2016年
みやこしあきこ(作)『よるのかえりみち』、偕成社、2015年
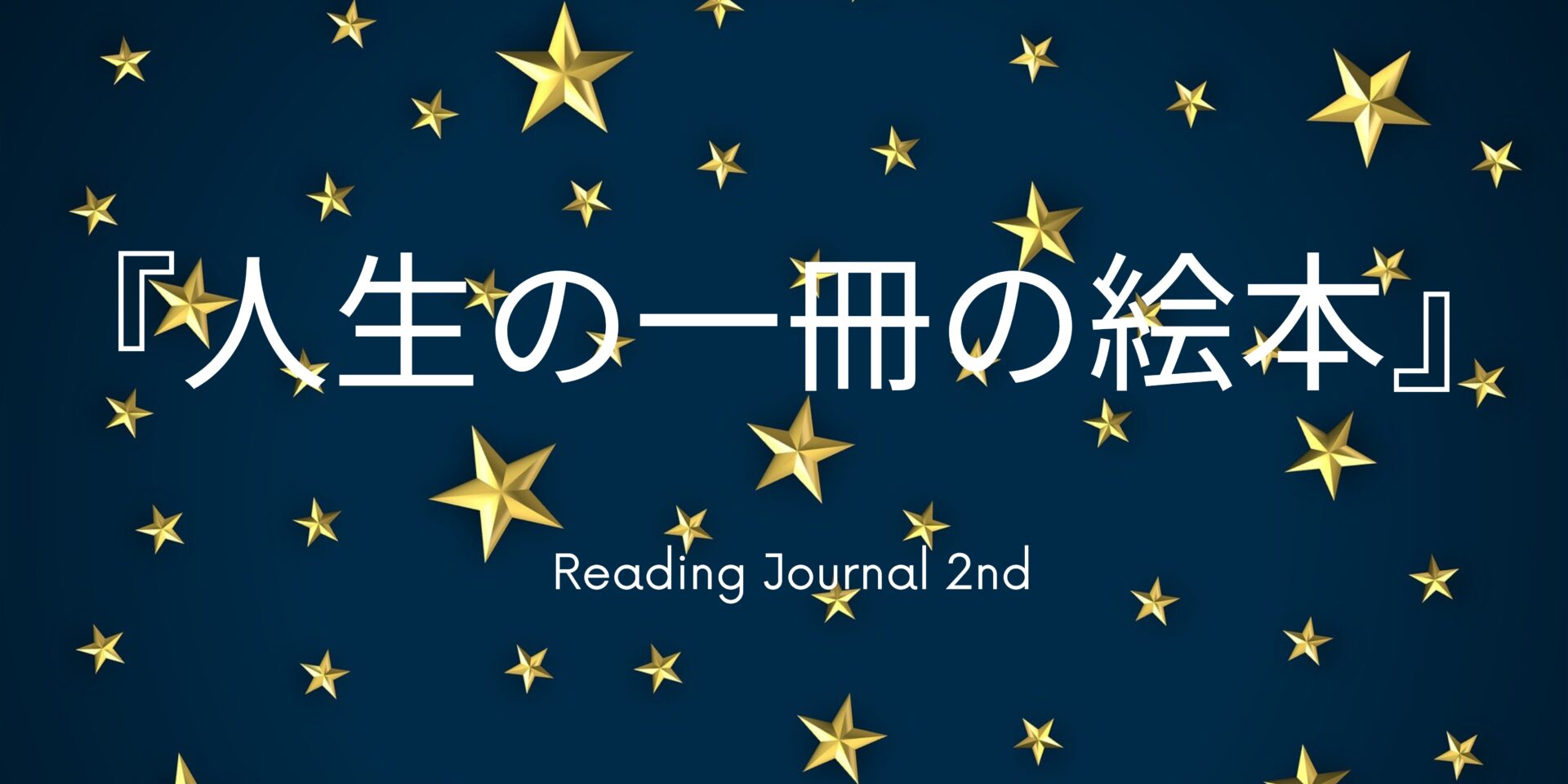


コメント