『人生の一冊の絵本』 柳田邦男 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
疎外された少女に雪解けが
『ジェーンとキツネとわたし』
柳田は、『ジェーンとキツネとわたし』の絵本の表紙絵を見たときに、これは、前回紹介した『きょうはおおかみ』と同じ、イザベル・アルスノーの絵と分かったといっている。そしてその絵の表現の可能性にまたしても驚嘆している。
『ジェーンとキツネとわたし』は95頁ある分厚い本である。
主人公は小学五年生の少女エレーヌ、彼女はクラスメートから悪口を言われイジメられている。そして、自分自身でも太っていることにコンプレックスを持っている。エレーヌは『ジェーン・エア』の主人公ジェーンの人生に自らの状況を重ね合わせていて、絵本の途中に『ジェーン・エア』の物語が挿入されている。そして彼女は『ジェーン・エア』を読み耽ることで、みんなとの間に防波堤を築いている。
夏に行われたキャンプでも、彼女は『ジェーン・エア』を読み、防波堤を築く。ここで柳田は、物語の展開もさることながら、その絵の魅力について多く語っている。
キャンプの最後の夜、テントの前の石段で『ジェーン・エア』を読んでいると、キツネが現れ、怖がらずに寄ってくる。キツネだけ色がつけられている。おそらくこころの変化の兆しとして、キツネを登場させたのだろう。その夜、ほかのグループから追い出された女の子ジェラルディーヌが転がりこんでくる。そして、ジェラルディーヌとはじめてこころを開いて話し合えるようになる。
学校に戻ったとき、エレーヌは背筋を伸ばし颯爽としている。景色もクラスメートたちも色彩ある絵になっている。エレーヌは『ジェーン・エア』を読み終え、ジェラルディーヌにすすめる。<読めばわかるけどね、結末はすてきだよ>と。(抜粋)
関連図書:
イザベル・アルスノー(絵)、ファニー・ブリット(文)、河野万里子(訳)『ジェーンとキツネとわたし』、西村書店、2015年
C・ブロンテ (著)『ジェーン・エア』(上・下)、新潮社(新潮文庫)、1953・54年
もうひとつのこころの動きが
今回紹介される絵本は、こころの“ひみつ”をテーマにした『ひみつのビクビク』と、心の中の“もうひとりのじぶん”を描く『くろいの』である。
『ひみつのビクビク』
絵本『ひみつのビクビク』は、主人公の少女のこころの“ひみつ”をテーマにしている。何が秘密かは、英語版の書名“ME and my FEAR”にあるように、”fear(=恐怖・心配・不安・気がかり)”である。翻訳者のなかがわちひろは、この題名を『ひみつのビクビク』と訳している。
作者のフランチェスカ・サンナは、少女の不安な気持ちを真っ白な海坊主みたいな生き物「ビクビク」に変えて表現している。少女にとって不安なことがあるとこのビクビクが多きになり行動を邪魔する。そして少女が海外移住するとビクビクはどんどん大きくなり、少女はしたいこともできなくなってしまう。
しかし、仲良くなった男の子にもビクビクがいる事に気づいた時、少女の気持ちが変わっていく。
その瞬間に、わたしは気づいたのだ。男の子にもビクビクがいるのだ、と。気がつけば、わたしのビクビクがどんどん小さくなっていくではないか。<なれないことや、まごつくことがあっても、クラスのみんなが、それぞれにビクビクを持っていることがわかってくると、友達のなかに入っていけるようになる。(抜粋)
柳田は、このテーマは、いじめの頻発する日本の子どもたち、あるいは大人たちにもしっかりと理解してほしい、と言いている。
『くろいの』
もう一冊の『くろいの』は、子どもの心の中にひそんでいる“もうひとりの自分”がテーマである。ここで“もうひとりの自分”をくろいのに変えて表現している。この手法は『ひみつのビクビク』と同じである。
主人公の少女が学校の帰り道に「くろいの」に出会う。<ねえ、なにしているの>と声をかけると、くろいのは歩き出し、よその家の塀をくぐって手招きをする(道草をして遊ぼうとすることを暗示している)。そして、誰もいない家で少女はくろいのと遊ぶ。そして最後に
くろいのは草花一輪を手折って渡してくれる。少女はバイバイをして、花のにおいを嗅ぎながら、いつもの道を帰っていく。(抜粋)
関連図書:
フランチェスカ・サンナ(作)、なかがわちひろ(訳)『ひみつのビクビク』、廣済堂あかつき、2019年
田中清代(作)『くろいの』、偕成社、2018年
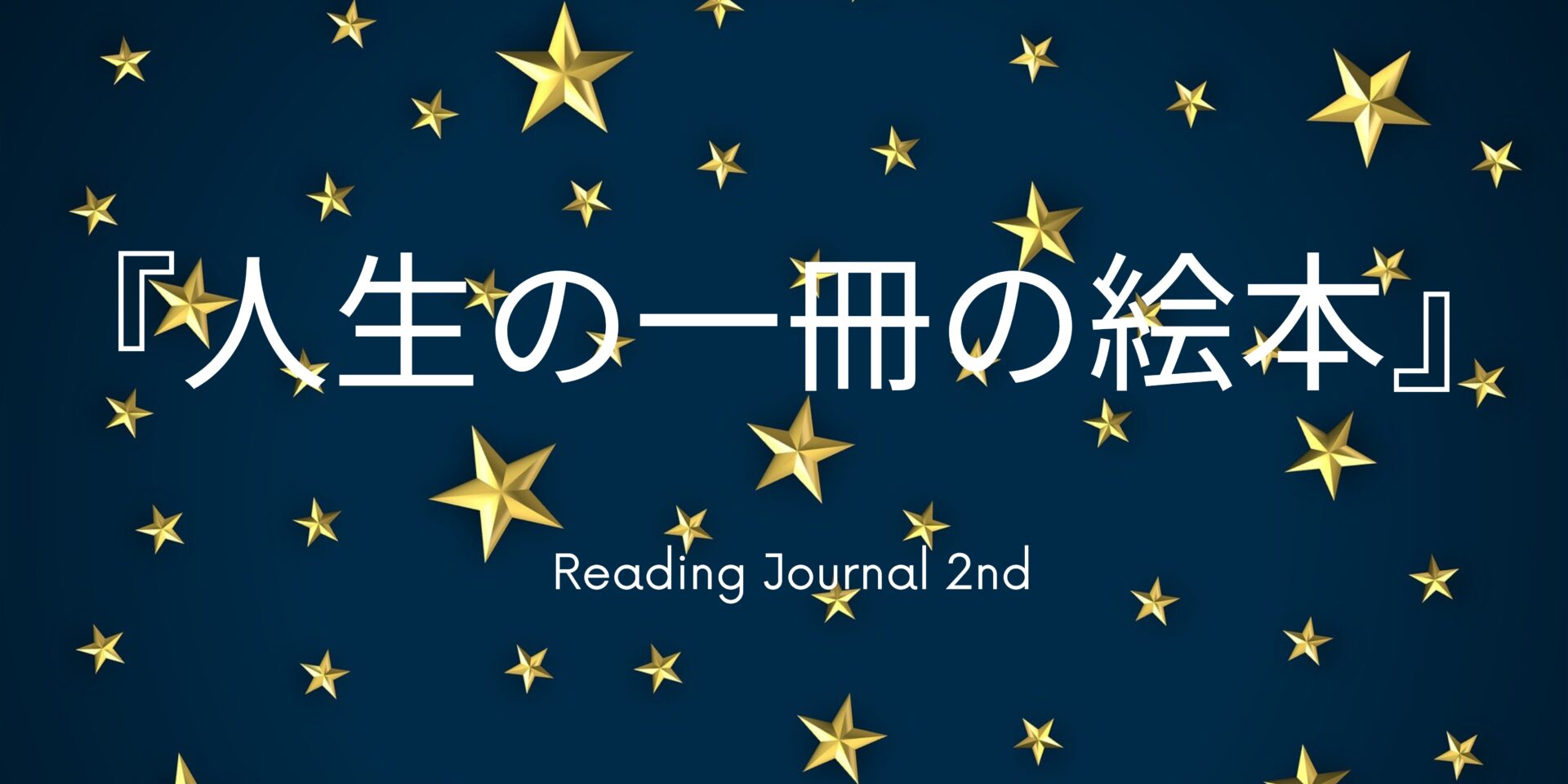


コメント