『人生の一冊の絵本』 柳田邦男 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
木は見ている、人の生涯を
『最初の質問』
子どもたちが発する質問には、意表を突くようなものがあって、なかなか面白い。大人は、「世の中はこうなっているのだ」と思い込んで、深く考えない。こころの潤いを失っている。
詩人の長田弘の『最初の質問』は、そのような問いを深い哲学的に語る傑作である。教科書にも載る『最初の質問』は、画家のいせひでこの絵で絵本になっている。
ここで柳田は、1ページごとにつづく問のなかから、樹木に焦点を当てている。
〈樫の木下で、立ちどまったことがありますか。街路樹の木の名をしっていますか。樹木を友とだと考えたことがありますか〉(抜粋)
ここでは、鬱蒼と葉の繁る木の下を、少年が右腕で涙をぬぐいながら歩いている場面が描かれている。
樫の巨木はそんな少年を大きく包みこむようにして見守っている。〈そうなんだ。悲しいとき、苦しいとき、孤独なとき、木や森はいつも黙って人間を見つめ抱きしめて、生きるのを支えてきたのだ、人間は自然界の征服者だなどと傲ってはいけない>という思いが湧き上がってくる。(抜粋)
そしてこの場面の絵は、ずっと後に出てくる場面の伏線になっている。
それは、〈何歳のときのじぶんが好きですか。上手に歳をとることができるとおもいますか。・・・〉の頁である。(抜粋)
冬に同じ巨木の下に、一人の老人がロングコートを身にまといハットをかぶって巨木を見上げている。
私たちは、「人は木や森を見ている」という一方的な考え方しかしない。しかし、実は人は木や森に見られている存在なのだということに気づくべきなのだ。なにしろ、樫にしろ欅にしろ杉にしろ、五〇〇年、一〇〇〇年と生きて、目の前を通り過ぎる人間の栄枯盛衰を黙々と見続けるのだから、人間は謙虚にならなければならないと考えるのが、真っ当な倫理観というものだろう。気もこころを持った存在なのだという、自然界を見る目の「コペルニクス的転回」をするならば、人間の生き方も違ったものになるはずだ。(抜粋)
『ならの木のみた夢』
柳田は、『最初の質問』と同じようなことを考えさせる絵本をもう一冊見つけたとして、『ならの木のみた夢』を紹介している。
田園地帯の川辺にある大きなならの木に少年は毎日やってきて木登りをした。ならの木は、葉を触れあわせ、枝をならして、少年をもっと上へと誘った。
ある日、少年はいつもと違うきれいな服を着てやってくると、<おまつりにいくんだ><おみやげを買ってきてあげるよ>と言う。<鈴がいいかな。枝にぶらさげたら、いい音がするよ>と。そして、木登りもしないで行ってしまう。(抜粋)
そしてその後、少年は引っ越してしまった。少年を待っていたならの木は、悲しみに暮れる。少年は、金属工となって生き抜くが、髪が白くなるころに解雇されてしまう。
初老になった彼が、公園のベンチに座っていると、近くで遊んでいる子どもに出張に行くお父さんが<おみやげを買ってきてあげるよ>と言った。その時、彼は少年時代の約束を思い出し、鈴を買って汽車で故郷に向かった。そしてならの木を訪ね、鈴を掛けてあげる。
その晩、ならの木がみた夢のなかで、現れた少年が若者になり、老人へと、走馬灯のように変わっていき、老人がゆっくりと手のひらを開くと、こう言うのだ。
<やっと見つけた。おみやげの鈴>(抜粋)
関連図書:
長田弘(詩)、いせひでこ(絵)『最初の質問』、講談社、2013年
やえがしなおこ(文)、平澤朋子(絵)『ならの木のみた夢』、アリス館、2013年
木に育まれる人間のこころ
柳田は、幼稚園や小学校に読み聞かせや紙芝居に時折で書ける。そういう時に子どもたちの強い視線を感じると言っている。
このように「見る」「見られる」という関係には、本来双方向性がある。ところが、現代人は傲慢で、自分が自然界でいちばん優秀な存在だと思いこみ、自分以外のものを上からの目線でしか見えないという悪い癖に染まっている。(抜粋)
この双方向性の視点は、生態学(エコロジー)のみならず、人間の精神性を高めるうえで重要である。
そして、そう思うと絵本の世界での擬人化は、動物や木の側から人間を「見る」ことにつながっている。ここでは、そのような視点から二冊の絵本が紹介されている。
『わたしの木、こころの木』
一冊目は、いせひでこさんの『わたしの木、こころの木』である。この絵本は一二編のメルヘン的な文章と絵で構成されている。一編ずつは、独立な物語になっているが、最初と最後の章は、東日本大震災で津波によってなぎ倒された一本のクロマツの倒木がモチーフになっている。
『フランシスさん、森をえがく』
二冊目は『フランシスさん、森をえがく』である。
主人公の画家・フランシスさんは、森をえがくと他のことを忘れて夢中になってしまう。フランシスさんは、花咲くマンゴーの木、赤いイチジクの木、ヤシの木、ハマベブドウの木などを熱心にえがいて行く。そして高さ五〇メートルまで成長したモビアの大木を描こうと気球に乗って森の上からモビアの木を観察する。すると、突然、金属音が鳴り響き土地開発の森焼の黒い煙が上がる。気球は墜落し、フランシスさんは失神してしまう。
意識が戻り、目の前のあまりの惨状を見て、画用紙の上に涙を落とす。するとなんと涙がにじんで木の形になり、その上に、一本だけ生き残ったモビアの木から花の涙が降りそそいでくるではないか。花の涙はさらに地面一帯を潤し、その下から緑の若芽がどんどん伸びてきて、森を生き返らせる。そのいのちのエネルギ-をもらったフランシスさんは、再びモビアの木の枝に座って描き始める。(抜粋)
関連図書:
いせひでこ(作)『わたしの木、こころの木』、平凡社、2014年
フレデリック・マンソ(作)、石津ちひろ(訳)『フランシスさん、森をえがく』、くもん出版、2014年
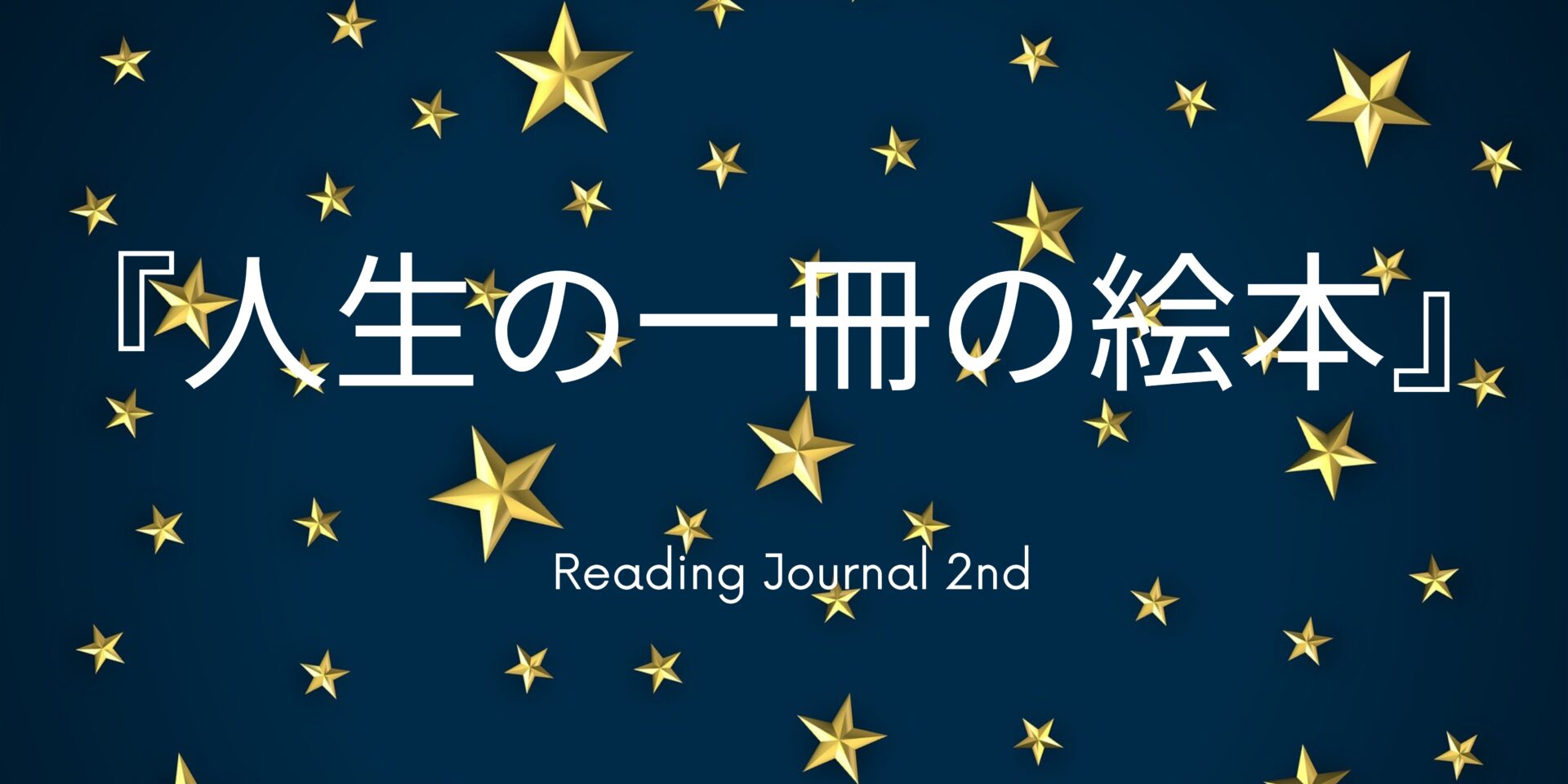


コメント