『人生の一冊の絵本』 柳田邦男 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
なんとなく笑えるって、いい時間だ
冒頭で著者は、日本が近年亜熱帯かしていることにふれて、ここでは、そんな蒸し暑い夜に気分をカラッとさせる絵本を四冊そろえたと言っている。
絵本作家は、言葉や絵にユーモアを忍び込ませることに四苦八苦している。そのような思考回路を覗き見て楽しむことは、絵本の読み手としてプロ級である。
『まめまめくん』
まず一冊目は『まめまめくん』である。主人公のまめまめくんは、とても小さい。表紙には、マッチ箱の中箱の中に眠るまめまめくんが描かれている。
まめまめくんは赤ちゃんの時は、お人形の靴をはいたり、マッチ箱の中箱や猫の背中で寝たりと、のびのび育つ。幼児期も、ハスの葉に寝そべったり、ミニトマトの木によじ登ったりして育っている。しかし、小学校に入るとあまりに小さいので、みんなと遊べない。机にすわるのも一苦労、給食のナイフとホークが大きすぎて食事に手が出せない。仕方なくいつも一人で絵ばっかり描いていた。そしてまめまめくんはやがて大人になり、仕事に就く。そして最後にすばらしい答えが描かれている。
子どもというものは、一人ひとり体型に違いがあり、個性があり、得意、不得意の違いがある。からだに障害がある子もいれば、知的発達障害の子もいる。そんな違いがある子がみんなのなかで、どんな居場所を見つけられるか。そういう大切な問題を、気づかせようとしているのだろう。そういう目で、絵本をゆっくり読み直し、一頁ごとの絵に隠されたメッセージを読み取ると、この絵本が「なんとなくおかしい」というだけのものではないことがわかってくる。(抜粋)
『どうぶつえんはおおさわぎ』
二冊目は、『どうぶつえんはおおさわぎ』である。
ある日、ゾウの飼育係が園長室に、〈たいへんです!(中略)だれかが、ゾウの テンテンを もっていって しまった みたいなんです。 それで、ゾウが「ソウ」になってしまって・…〉と言って飛び込んできた。そして事件はどんどん広がり、ゴリラがコリラ、フラミンゴがフラミンコ、カバがカハになり、最後に「どうぶつえん」の名前が「とうぶつえん」となってとうふ屋と間違えた人が列をなしてしまう。
お説教じみた言葉は何もない。言葉遊びのナンセンス絵本みたいだけれど、動物園の動物たちの様子が妙に面白い。言葉遊びなのだけど、動物園内の大騒ぎのなかに、いつの間にか自分も入り込んで楽しんでいるような気分になるのは、動物たちと一心同体になっているあべさんの絵ならではの力だろう。(抜粋)
『こらっ、どろぼう!』
三冊目は『こらっどろぼう!』である。
犬のマックスが、主人から畑のニンジン、イチゴ、マメなどを盗んでいく犯人を捕まえるように命令される。最初にマックスは小さなニンジンの葉っぱを食べる虫を見つけ<こらっ、どろぼう!>とさけんで追いかける。その時、ニンジンを食べていたうさぎが<いまのって・・・「あたしにいった」>と聞くが、虫が犯人だと思っているマックスは<ちがうよ>と答える。いちご畑に行くと、赤いブタがイチゴをたべているが、マックスはそれに目もくれずに、虫を追いかけて行ってしまう。
『108ぴきのひつじ』
四冊目は『108ぴきのひつじ』である。
主人公のメイは夜眠れないので、ひつじを一匹、二匹と数える。ひつじたちはメイのベッドを飛び越えていく。しかしメイは五〇ぴきになっても一〇〇ぴきになっても眠れない。
一〇八ぴきになったとき、ジャンプ力のない一〇八ぴきめのひつじは飛び越えられず、後につづくひつじたちからブーイングが起こる。メイはベッドに大きな穴をあけてやる、一〇八ぴきめのひつじがやっと通り抜けると、あとのひつじたちが次々に・・・・。(抜粋)
関連図書:
デヴィッド・カリ(文)、セバスチャン・ムーラン(絵)、ふしみみさを(訳)『まめまめくん』、あすなろ書房、2016年
二宮由紀子(作)、あべ弘士(絵)『どうぶつえんはおおさわぎ』、文研出版、2015年
ヘザー・テカヴェク(絵)、なかだゆき(訳)『こらっ、どろぼう!』、きじとら出版、2017年
いまいあやの(作)『108ぴきのひつじ』、文溪堂、2011年
不条理な悲しみの深い意味
この章では、昭和戦前期に活躍した童話作家・新美南吉の作品が取り上げられている。新美南吉は、短編童話作家であり、絵本を創作したわけではないが、戦後になってから彼の『ごんぎつね』や『てぶくろをかいに』などの童話が絵本化されている。
『ごんぎつね』
新美南吉の代表作『ごんぎつね』は、ひとりぼっちの子狐のごんと貧乏農家の兵十の、胸が痛むような展開となる(テキストはココ)
ごんは、悪いいたずらをして兵十を困らせたが、精一杯の謝罪をしていた。しかし兵十はそのことに気づかず、物語は兵十にとってもハッピーエンドにならなかった。
なんと不条理な結末であることか。にもかかわらず、私たちはこの物語を読んで、拒否感を抱くかというと、そうではない。悲劇的な結末の小説を読んで、こころを揺さぶられることが好きなくないが、『ごんぎつね』を読んだ感想も、それと同じと言えるだろう。
なぜこころを揺さぶられるのか。おそらくそれは、意識するにしろ意識しないにしろ、誰しもこころに持っている。不条理なつらい人生経験の思い出に重なるところがあるからだろう。・・・・中略・・・・・
そして、この作品にこころを揺さぶられる理由は、もうひとつあるだろう。それは兵十がごんを憎んではいたものの、銃を撃ってしまってから、ごんのやさしさに気づき、<お前だったのか>というつぶやきで、ごんが根っからの悪党でないことを認めたところだ。(抜粋)
『ついていったちょうちょう』
新美南吉の童話で絵本化したものに、この『ついていったちょうちょう』と次に『でんでんむしのかなしみ』がある。
『ついていったちょうちょう』は、風に吹かれて流されていく赤い風船に、ついて行く蝶の話である。風船に<ぼくは どこへ いくんだか わからないから、ちょうちょうさん もうおかえりよ>と言われてもちょうちょうはついて行き、ついには行方不明になってしまう。
『でんでんむしのかなしみ』
主人公のでんでんむしは、自分の背中の殻の中にはかなしみがいっぱい詰まっていることに気づく。もう生きていけないと思って、友達のでんでんむしに話すと、その友達も<わたしの せなかにも かなしみは いっぱいです>という。
そして、主人公のでんでんむしに「みんな同じなんだ」という深い気づきが起こる。
関連図書:
新美南吉(文)、箕田源二郎(絵)『ごんぎつね』、ポプラ社、1969年
新美南吉(文)、山中現(絵)『ついていったちょうちょう』、星の環会、2016年
新美南吉(文)、野見山暁治(絵)『でんでんむしのかなしみ』、星の環会、2016年
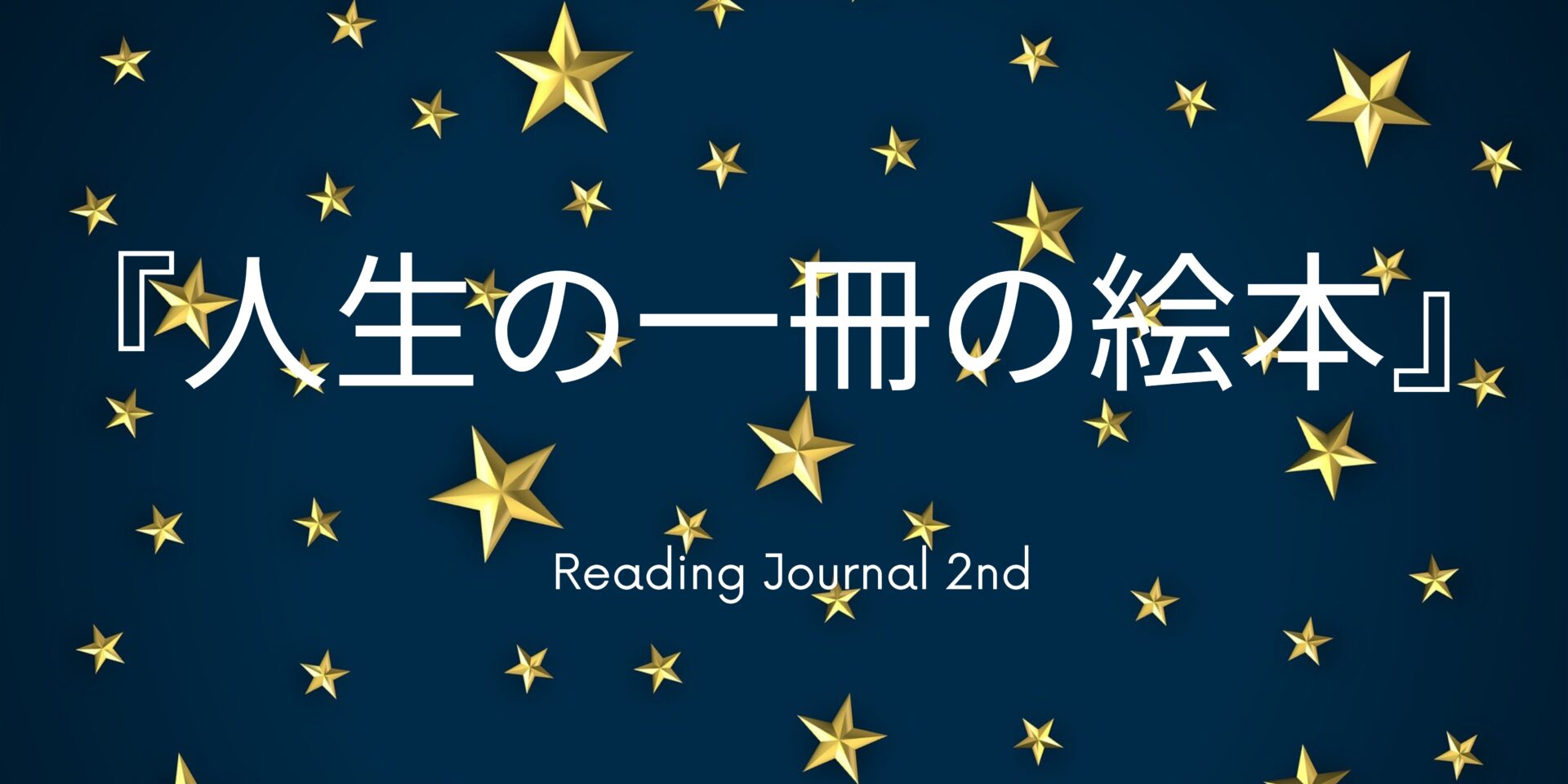


コメント