『本を読む本』 M.J.アドラー / C.V.ドレーン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第二部 分析読書 — 読書の第三レベル 8 著者と折り合いをつける
今日から、「第二部 分析読書」「8 著者と折り合いをつける」に入る。ここでは”前々回“、”前回“と同じく、分析読書の方法である。
前々回は、分析読書第一の規則である「本の種類を知る」、前回は、二の規則「本の全体の統一の要約」、第三の規則「本の部分の構成の把握」、第四の規則「著者の問題を知る」についてであった。ここまでが分析読書の第一段階である。
今日から第二段階に入り、まずは、第五の規則「重要な単語を見つけ出し、それを手がかりにして著者と折り合いをつける」である。それでは、読み始めよう。
ここから、分析読書の第二段階となる。第一段階が「本の構造をつかむ」ことが目的だったが、第二段階では「内容を解釈する」ことが目的となる。この第二段階も四つの規則がある。
分析読書 第五 の規則「単語の使い方の理解」
通常単語は、ひとつの意味だけでなく、多くの意味を持つ。読者と著者が完全なコミュニケーションをするためには、両者が同じ単語を「同じ意味で」使わなければならない。
そのため、分析読書 第五の規則は「重要な単語を見つけ出し、それを手がかりに著者と折り合いをつける」である。
この規則には、2つの手順、「重要な単語を見つけること」「使われている意味を正確につかむこと」がある。内容の解釈を目的とする第二段階では、他の規則も同じように2つの手順にわかれる。その手順はまず「言葉」を扱い、その背景の「思想」を論じるである。
もし言葉が完全であったらこのような規則の必要はない。しかし、言葉は不完全であり、しばしばコミュニケーションの妨げになる。この解釈の規則はその障害を克服するために必要である。
第五の規則の手順1「重要単語を見つける」
キー・ワード(重要単語)の見つけ方
著者が使っている言葉のすべてが重要であるとは限らない。著者が特殊な意味で使っている言葉だけが重要語である。それは読み手に取って意味のつかみにくい言葉である。
このキー・ワードを見つけるためには、パラグラフ全体を理解する必要がある。なぜならば、パラグラフを完全に理解できないのは、意味の分からない単語があるからである。
専門用語と特殊な語彙
ここで、重要単語の見つけ方として、上の普通の言葉を消していく方法の他に、著者が強調している単語を見つける、という方法があると言っている。強調の仕方として
- 引用符やイタリックなど、活字上の工夫をして強調
- その単語について定義をして強調
がある。
そして、その定義をしている言葉が「専門用語」である。この専門用語はどの分野にもあり、読み手はそれを発見しなければならない。多少とも主題について予備知識があれば、それを発見することが容易になる。
しかし、専門用語が確立されていない分野も多く、またて哲学のような分野では、普通の言葉を「専門用語に転用する」こともある。
また、重要単語を見分けるもう一つの手がかりが、著者が重要語の使い方で、他の著者の対立している場合である。
ある特定の言葉を、他の著者と違った意味に使う理由を、わざわざ説明しているときには、その言葉は、著者にとって重要語と考えて間違えない。(抜粋)
第五の規則の手順2「単語の意味をつかむ」
重要語の意味について、
- 単語は常に一つの意味を持つ
- 単語は場所によって、いくつかの意味を持つ
の二つの場合がある。
そのため、まず単語が一つの意味で使われているか、二つ以上の意味で使われているかを見極める。そして、二つ以上の意味で使われている場合は、それぞれの意味がどのように関連するかを調べる。最後に、単語が違った意味で使い分れている箇所に注目し、前後の文脈から、意味が変化した理由をつかむ手がかりがあるかを調べる
単語の意味をつかむためには、「前後の文脈のわかっている単語を残らず動員して、わからない単語の意味をつかむ」ことである。まわりの単語が、解釈を必要とする単語の「文脈」となる。これは難しい作業であるが、これが出来なければ、読書によって理解を深めることはできない。
一つの単語に二つ以上の意味を持たせる著者は、あいまいな言葉の使い方をしていると疑問に思うかもしれないがそれは違っている。
一つの単語をいくつかの意味に使ったからといって、あいまいに使ったことにはならないし、事実、重要な単語は、いくつかの意味に使われるのがふつうである。単語をあいまいに使うとは、意味の違いや関連をはっきりとさせずに使うことである。それでは、読み手が折り合うべき言葉の意味を明らかにしていないことになる。しかし、書き手が、重要な単語の意味を、読み手にもはっきりとわかるように使い分けているのなら、それは、決してあいまいな言葉の使い方をしていることにはならない。(抜粋)
単語については、まだいくつかの問題がある。
- いくつかの異なった意味を持つ単語は、どれか一つの意味にも、また、いくつかの意味の組み合わせとしても使われること
- 同義語の問題。ふつう同じ単語を繰り返し使うのは避けられ、重要語の場合は、意味が同じか、きわめて近い他の言葉を使うことが多い
- 「句」の問題。句は単語と同じく、ある特定の意味(名辞)をあらわす。そして一般に句は、単語よりもあいまいでない。そのため読み手にはっきりと理解してもらいたいために、手の込んだ句を使うことがある
解釈のための「文法」と「論理」
内容を理解する規則には二つの手順がある。これは「文法」と「論理」の側面がある。ここでは、文法は単語にあたり、論理は単語の意味(名辞)となる。およそあらゆるコミュニケーションが成立するためには、この二つの手順は不可欠である。
この章で扱った分析読書の第四の規則「単語の使い方を理解する」も「文法」=「重要語を見つける」と「論理」=「単語の意味をつかむ」の両面から論じている。
「解釈」の根底にある「文法」と「論理」の研究は、さまざまな実際問題を処理するさいに、本当に役立つ。この章では、まずその第一歩として、重要語を見つけ出し、意味の変化を見きわめ、単語のあらわす意味を正確につかむこと、すなわち単語の使いかたについて、著者と折り合いをつけることについて考えた。このことを心がけるだけでも、読み手の理解を大いに深めてくれるはずである。
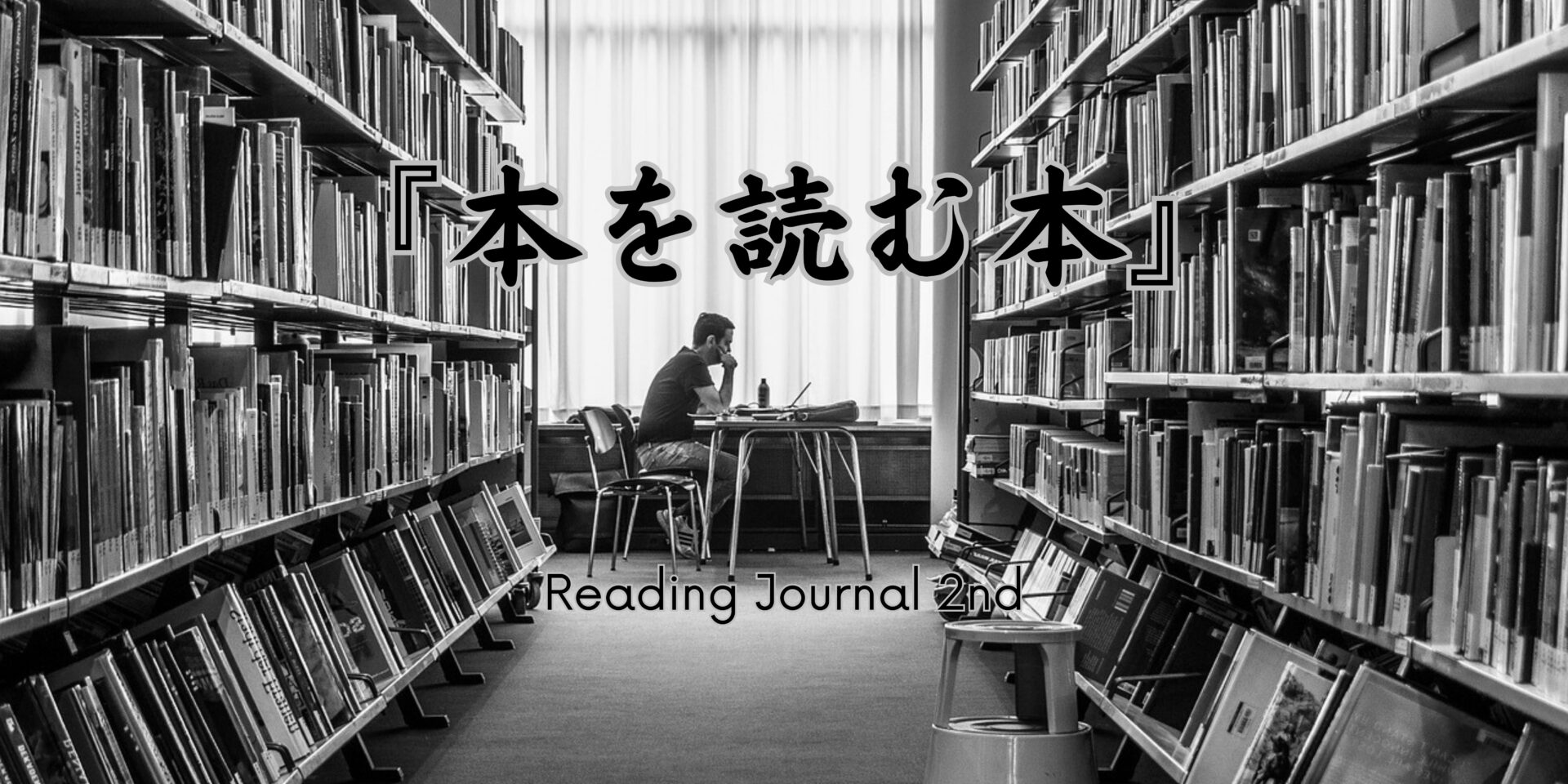


コメント