『本を読む本』 .MJ.アドラー / C.V.ドレーン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第一部 読書の意味 4 点検読書 — 読書の第二レベル
今日のところは「第一部 読書の意味」の第4章「4 点検読書」である。ここでは前回の「初級読書」に続き、読書の第二レベルの「点検読書」についての解説がある。点検読書は「下読み」と「表面読み」からなる。またここでは、早く読むための速読について言及されている。それでは読み始めよう。
「点検読書」は、二つのタイプがある。それは実は技術の両面であり、経験を積むと同時に行うことができるが、ここでは両者を切り離して扱う。
点検読書1 — 組織的な拾い読み、または下読み
点検読書1は、その本が読むに値する本であるかを品定めするために行う下読み(組織的拾い読み)である。この下読みにより、その本が入念に読む必要がないと判断した場合でも、拾い読みによりその本がどんな本か、著者の主張がどういうものかおおよそつかめるため、時間の無駄にはならない。
① 表題や序文を見ること:どちらも素早く読み、本の主題を把握する
② 目次を調べる:本の構造を知るために目次を見る
③ 索引を調べる:索引でその本の題目、範囲、引用文献などをざっくり調べる。索引に出てくる重要な術語については該当ページを何か所か読んでみる。
④ カバーに書いてあるうたい文句を読む:この種の文章は、宣伝のために書かれるが、大抵は著者自身が出版社の宣伝部の知恵を借りて書いている。
以上の4点を行うことによりその本が入念に読む本かの判断ができる。さらに行う場合は
⑤ その本の議論のかなめと思われるいくつかの章を読んでみる:その章の内容が漠然と分かってきたら、章のはじめか終わりにある要約をよく読む。
⑥ ところどころ拾い読みする:その本全体にわたり、パラグラフ一つか二つ、長くても二、三ページを拾い読みする。特に最後の二、三ページは必ず読む。
この点検読書は本を調べながら読むため、注意力と集中力を必要とする。そして、このような方法で、本のテーマや意図を見いだす手がかりを探し求め、あらゆるヒントに注意を払って読めば、その理解も深くなる。
点検読書2 — 表面読み
難解な本は一度読んだだけで理解できるものではない、しかし正しく近づけば、専門書でない限り、どんな難解な本でも読者を絶望させない。
その正しい近づき方とは、「難解な本をはじめて取り組むときは、とにかく読み通すことだけを心がける」ことである。最初の通読で半分くらいしかわからなくても、再読すれば、ずっとよくわかるようになる。
つまり、まずは表面的な読み方で通読することが大事である。
読書の速度
本章の点検読書では、時間内にできる限り多くのものを引き出す技術である。そのためこの点検読書の二つの段階は、早くすませるべきである。
ただし理想はただ早く読めるようになるだけでなく、さまざまな速度での読み方ができるようになることである。次の分析読書になると、読む速さはずっと遅くなる。しかし、分析読書でも始終同じ速さを保つ必要はなく、場所によっては飛ばし読みをすべきところもある。
点検読書による理解
点検読書を行うことにより早く読めるようになるが、それにはどんな得があるだろうか。第一に時間を節約できる。そして第二に速度が増すと集中力も増すので、理解力も上がる。
しかし、集中力さえあれば理解力が深まるということではない。ここでいう理解は、分析読書を通しての理解とは質が違うことに注意が必要である。
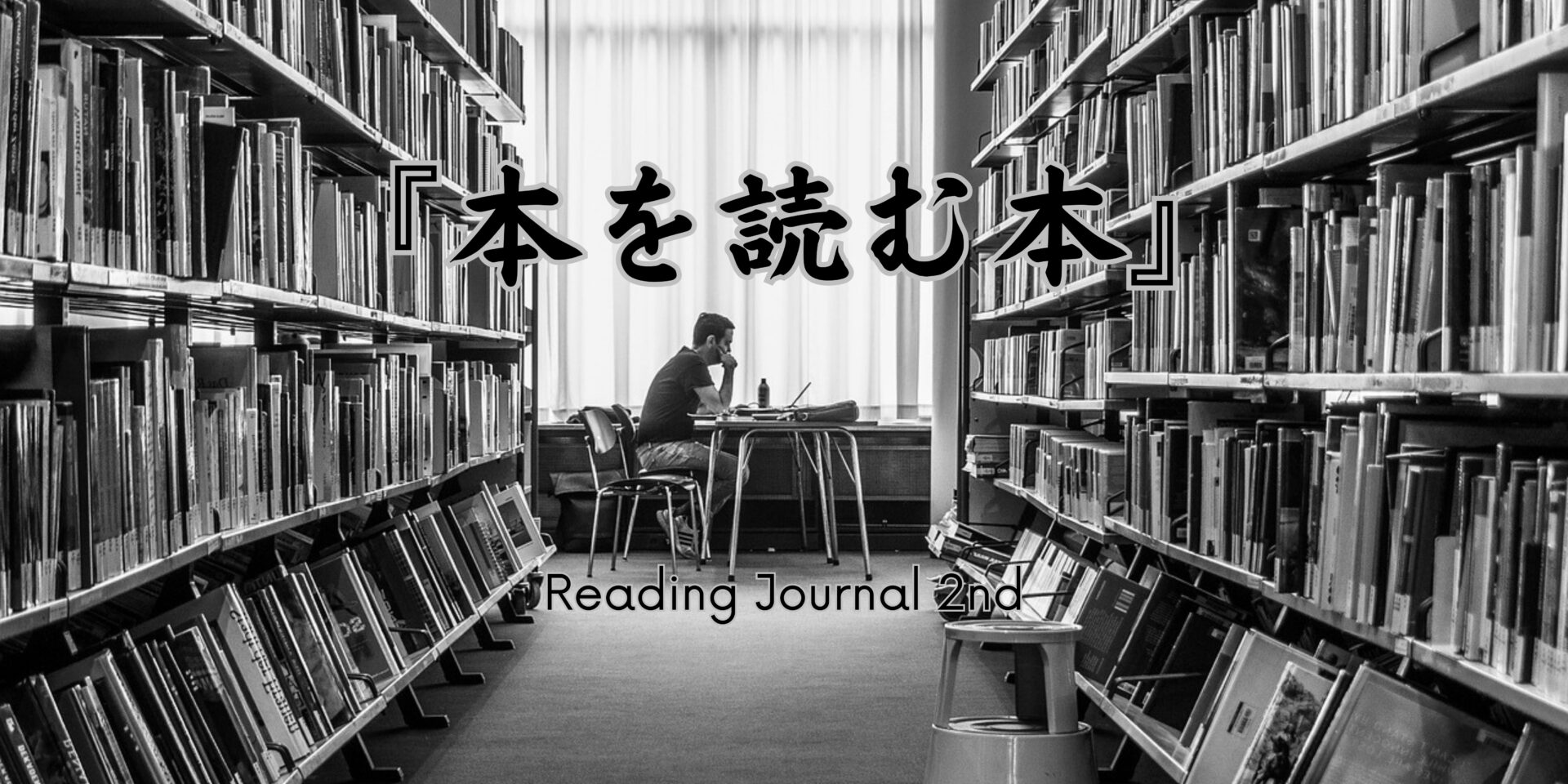


コメント