『本を読む本』M.J.アドラー / C.V.ドレーン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第一部 読書の意味 1 読書の技術と積極性
著者による日本語版へのメッセージ「日本の読者の皆さんへ」が終わり、ここから本文に入る。今日のところは、「第一部 読書の意味」の第1章「1 読書の技術と積極性」である。
ここは、読書とその技術についてのイントロダクションである。著者は読書というものは漫然と読むのではなく「積極的読書」が必要だとしている。そして読書の意味や学ぶこと発見することなどについて解説を与えている。それでは読み始めよう。
現代における読書の必要性
この本は「本を読む人」のための本である。「これから本を読みたい人」のための本でもある。つまり、「読む」ことによって知識を得、理解を深め、すぐれた読書家になりたいと思う人のために書かれた本である。(抜粋)
著者はこのように話を始めている。そして「読書家」とは、情報や知識を主として活字から得る習慣のある人と定義している。
ここで著者は現代のマス・メディアによる情報過多の問題について警鐘を鳴らしている。
現在はマス・メディアの発達により、テレビやラジオにより情報が手軽に入手できる。このような状況のため、読書は昔よりも重要視されなくなっている。
しかし、このようなマス・メディアは、物事を考えるという点で役立っているかは大いに疑問であると著者は指摘している。現代の情報過多はむしろ理解の妨げになっている。
理由の一つは、現代のマス・メディアそのものが、自分の頭でものを考えなくてもよいような仕掛けにできていることである。現代の頭脳はその粋を集めて、情報や意見の知的パッケージを作るという大発明をなしとげた。この知的パッケージを私たちは、は、テレビ、ラジオ、雑誌から受け取っている。そこには気のきいた言い回し、選びぬかれた統計、資料などがすべて整えられていて、私たちはいながらにして「自分の判断を下す」ことができる。だがこの知的パッケージがよくできすぎていて、自分の判断を下す手間まで省いてくれるので、読者や視聴者はまったく頭を使わなくてもすんでしまう。(抜粋)
ここの、マス・メディアが作り出す「知的パッケージ」が、私たちが自ら理解したり判断したりすることを妨げているという指摘は、全くその通りだと思う。この本の初版は1940年、すでにそのような指摘がなされていたんだなぁ、と思った。
現在は、さらにSNSなどを通して、フェイクニュースなどの「”悪い“知的パッケージ」が蔓延していて、ますます自ら考えことが重要となり、そのための読書が重要となっているんだと思う。(つくジー)
積極的な読書
読書技術をみがいてすぐれた読書家になるための方法、規則について、以下に述べていくことにしたい。それらの規則は活字になったものすべてにあてはめることができる。本だけでなく、新聞、雑誌、パンフレット、論文、広告文も例外ではない。(抜粋)
まず、「読む」という行為には、ある程度の積極性が必要である。そして、積極性の高い読書ほど、良い読書である。
話すこと、書くこととは積極的だが、聞くこと、読むことが受動的と考えている人も多いがそれは、間違いである。「読む」ことは、書かれている情報を巧みにキャッチする技術がなければ成り立たない。そして、その本に書かれていることをどのくらい巧みにキャッチ(理解)できるかは、読み手の積極性と熟練度によって決まる。
理解を深める読書
読書の成功は、その本に書かれているかを理解することであるが、その本には自分の理解を越えるところがありそれがわかれば、理解が深まると気づくときがある。
その時に、誰かに説明をもとめるとか理解するのをあきらめるというような行動は、その本にふさわしい「読みかた」をしているとは言えない。
自分の理解を越えた本を読むときこそ、読み手はいっさい外からの助けに頼らず、書かれた文字だけを手がかりに、その本に取り組まねばならない。(抜粋)
このような積極的読書が「浅い理解から深い理解へ」と、読み手を引き上げる。このような読み方はきわめて熟練した読み方である。
本には、「情報を得る本」と「理解を深める本」の二種類があり、その読み方も初めから分けて考える必要がある。
「情報を得る本」とは、新聞や雑誌のようなに、読み手の読書力や理解力によってすぐに理解できるものである。このような本は情報量を増やすが、理解を深めることはできない。
「理解を深める本」とは、前に一度読んで完全に理解できず、いま一度読む場合である。つまり、自分の理解を上まわる本を、再度読むことにより、読み手が理解を深めるような本である。
理解を深めるための読書が必要なのは、読み手と書き手の間に「理解の深さに差がある」場合である。そして、書き手は読み手よりも深い理解と洞察があり、読み手はそのギャップを埋める努力が必要である。
このような「本当に理解するための読書技術」を本書では問題としている。また、そのような読書技術が身につけば、情報を得るための読書の問題もたいていは片付いてしまう。
「知識を得ること」と「教わること(わからなかったことがわかるようになること)」の違い
単に「知識を得ること」も「わからなかったことを分かるようになること(教わる)」も「学ぶ」ことには違いないが、この二つには大きな違いがある。
「知識を得ること」は、単に事実を知ることであるが、「教わること」は、なぜそうなるのか、他の事実との関連や共通点や相違点について、さらに詳しく知ることである。
読書も単に記憶するだけでは「知識を得た」だけであるが、著者の述べたことだけでなく、その意図や理由を理解して初めて「(何かを)教わった」ことになる。
「教わること」と「発見して学ぶこと」の違い
ここで著者は、広く読むことと、よく読むことの違いを混同しないために「教わること」と「発見すること」に違いについてまとめている。
「教わること」は、話し手や書き手から学ぶことであり、「発見すること」は自分で研究調査し熟考して学ぶことである。
ここで、「発見すること」が積極的で「教わること」が消極的であると考えるのは間違っている。そもそも「受身の読書」などあり得ない。「教わること」=「助けをかりが発見」であり、そこには積極的な「教わる技術」「情報を受けとる技術」が必要である。
この「発見すること」と「教わること」の違いは、何から学ぶかである。「教わること」は、送られてくる情報や文字を読み、話を聞いて学ぶ。一方「発見する」は、自然界から学ぶことである。
「発見すること」は自然や外界から読みとる技術であり、「教わること」は本を読む技術、ないしは話し手から学ぶ技術である。(抜粋)
「発見すること」には、観察力や記憶力、そして想像力などが必要である。「教わる」場合は、それらは過小評価されるが、実は「発見する」ことに必要な能力がすべて要求される。
教師がいる場合といない場合の違い
ここで著者は、「講義」などで教師がいる場合と「読書」など教師がいない場合の違いについて触れ、本書では読書のように目の前に教師がいない場合に重点を置くとしている。
学生時代には誰でも、教師の手ほどきで難解な本に取り組むものである。だが、自分の読みたいものを読むときや、学校を出てから教養を身につけようとすれば、たよるものは教師のいない読書だけである。だからこそ、一生のあいだずっと学びつづけ、「発見」しつづけるには、いかにして書物を最良の師とするか、それを心得ることが大切なのである。この本は、何よりもまず、そのために書かれている。(抜粋)
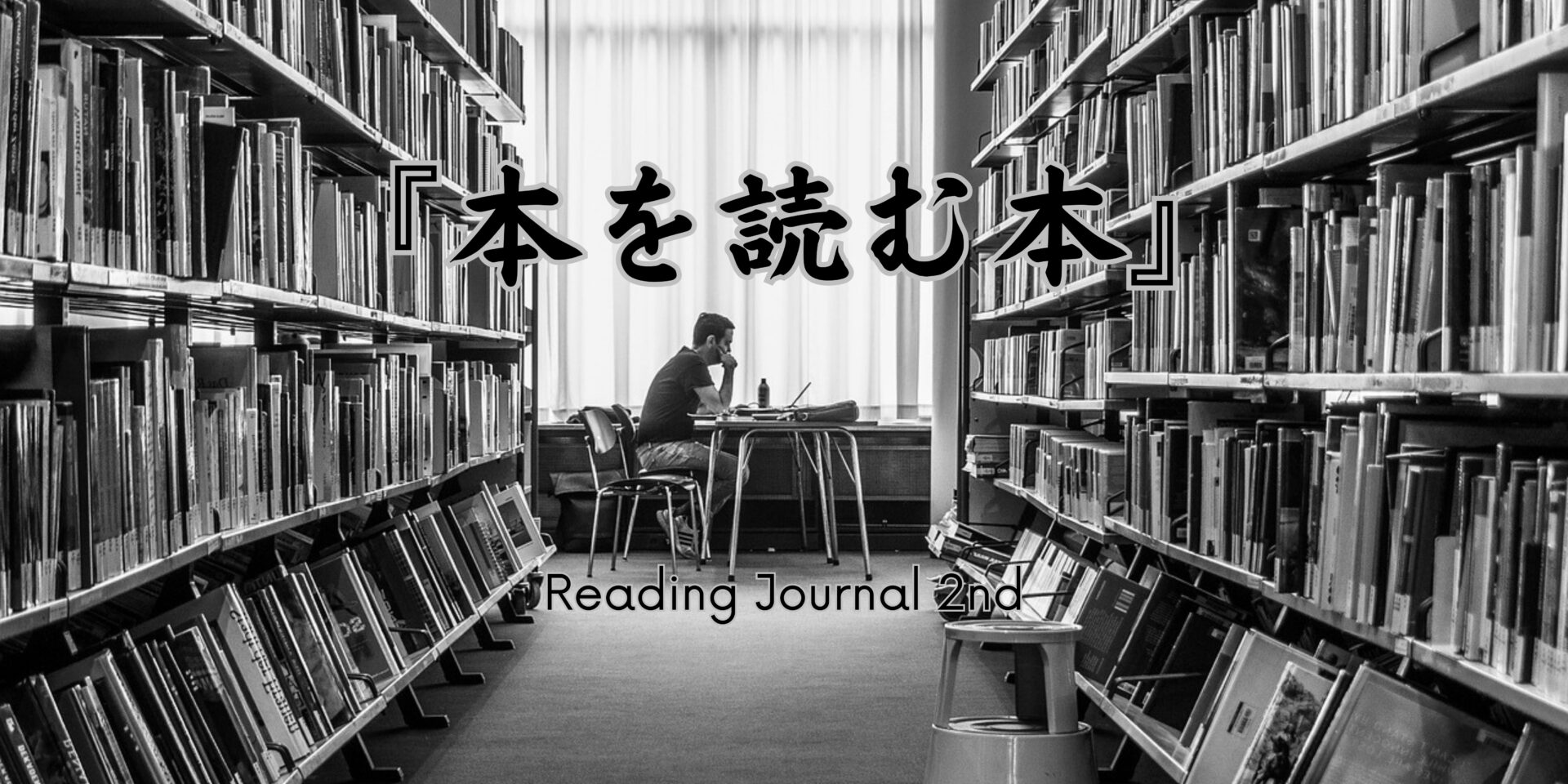


コメント