『人を助けるとはどういうことか』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
⑧ 支援するリーダーと組織というクライアント(後半)
今日のところは「⑧ 支援するリーダーと組織というクライアント」の”後半“である。“前半”では、コンサルタントが集団を支援するときの難しさについて具体的な例をもって解説された。それを受けて”後半“では「変革」における支援の役割、コンサルタントが支援する範囲をどのように広げる必要があるか、が取り扱われる。最後に第8章全体のまとめがある。それでは読み始めよう。
「変革」における支援の役割
ここで著者は組織の「変革」における支援は、特に興味深いとしている。それはあらゆる支援の形に出会うからである。つまり一対一の支援、チームという支援、組織という支援の形である。
ここでリーダーとコンサルタントは、組織のメンバーの変化をどのように促すのかを考えださなければならない。
人は変化を気にかけないが、他人に自分を変えられたくないということは、自明の理のひとつである。このわかりきったことに鍵がひそんでいる --- 変化のプロセスを支援のプロセスとして見直し、変化の対象をクライアントにするというものだ。(抜粋)
組織が変革を促すためには、そのメンバーが変革に必要な知識やスキルを知らなければならない。そのため最初は、メンバーに知識やスキルを指導する必要がある。しかし、メンバーが有能になるにつれて、変革のため要求されたスキルなどを自分のものとして吸収するようになる。この時、支援者は「どんな助けが必要ですか」と尋ねることが必要となる。
クライアントが最初に踏み出せる一歩は何かといったことを尋ねて、人間関係の均衡を保たねばならない。学ぶべきことにクライアントの注意を引きつけるため、支援者は心理的に安心できる雰囲気を作り、望ましい行動の手本を提供する必要がある。(抜粋)
支援の範囲をどのように広げるか
コンサルタントが情報を集める受け身の状態でなく、CEOや組織を助けたいと思うとき、クライアントの概念の曖昧さ、複雑さを受け入れる必要がある。
一対一のコンサルティングであっても、クライアントの概念は変わることがある。
全体的な原則は、上方向にせよ、下方向にせよ、正規の階層あるいは身分の階層の中で、層を飛ばしてはならないということだ。(抜粋)
もし正規のコンタクト・クライアントがCEOならば、次の階層の者へどう関わるかはCEOと相談して決断する必要がある。そのとき、階層を飛ばすことがあれば、その層のメンバーは、仲間外れにされた気分となり、支援に否定的となる。階層を飛ばさない原則は、コンタクト・パーソンが組織の中間層でも当てはまる。
とりわけ上層部へ支援の範囲を広げることは、注意が必要である。CEOは自分で物事を修正できるという考え方を持っている場合が多く、CEOにとって、低い層で行われるかもしれない相互の支援プロセスは生ぬるく見える場合がある。
結局のところ、究極のクライアントが組織の一単位なのか、組織全体なのかをコンサルタントは認識しなければならない。誰もが得をするためには、あらゆる階層の介入が支援となりうるのか、ほかの層への害になるのかを考慮すべきだろう。(抜粋)
第8章のまとめ
著者は、最後に第8章の内容をまとめている。
組織の支援が目的である場合、支援につきものの複雑さはすべて存在する。いつであろうと、支援者はクライアントが誰かを正確に知らないかもしれない。だが、組織のトップを関わらせることと、支援関係を築く上でどの層も抜かしてはならない。(抜粋)
変化のプロセスでは、クライアントが変わるプロセスで重要な時期がある。その時には支援者の役割はプロセス・コンサルタントと専門家・医師の間を絶え間なく行き来することになる。
リーダーシップの重大な側面は支援を受け入れる能力と組織の他の人間に支援を与える能力である。そのため、リーダーは、相互に支援し合える環境を作り、そのなかで自身の支援のスキルを明らかにする必要がある。
リーダーシップを定義するひとつの方法は、目標設定のプロセスと、そうした目標を達成するために他人(部下)を支援することの両方だと言える。(抜粋)
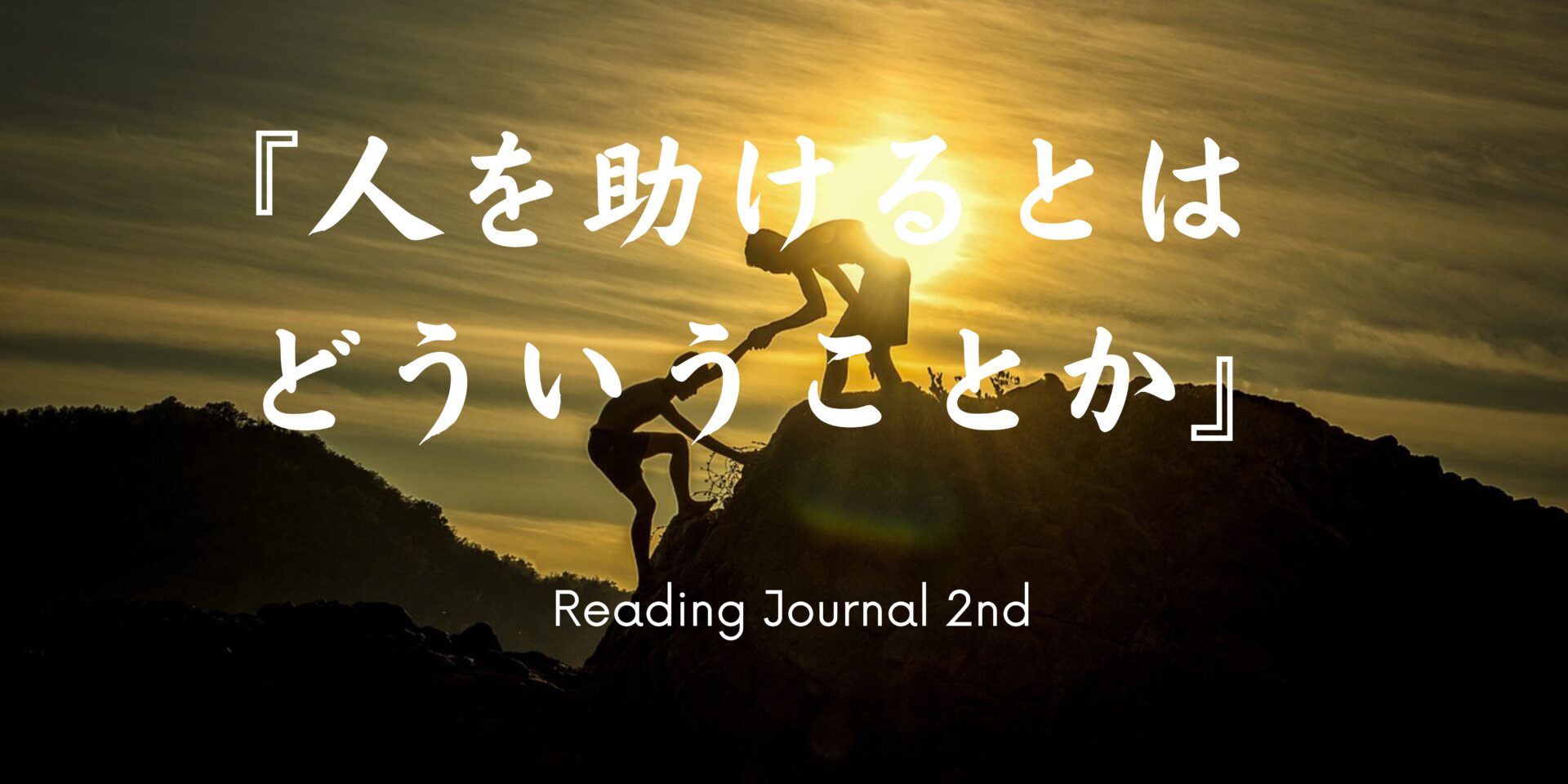
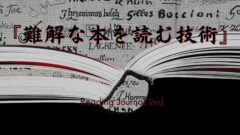

コメント