『人を助けるとはどういうことか』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
⑦チームワークの本質とは?(後半)
今日のところは「⑦ チームワークの本質とは?」の”後半“である。”前半“では、支援の理論をグループに導入し、機能しているチームの特徴とチーム・ビルディングの基本について考察した。今日のところ”後半“では、それに続き、チームの相互支援の重要度はそのグループの種類によって異なること、チームが自分たちの方向などを修正するフィードバックの方法、さらに離れた場所から支援するときの問題点について話題を広げる。それでは読み見始めよう。
仕事による相互支援の重要度の違い
あるグループがどのくらい助け合うチームになる必要があるかは、グループメンバーが相互に依存する仕事量によって違う。相互依存が同時に起こるようなチームでは、支援は最も重要になり、それはチームの各メンバーが互いに支援することをどれくらい学ぶかがによる。このように相互支援が大切なチームは、小規模の場合には全体が見えるため支援が不十分な部分を正すことが出来るが、大規模のチームでは、様々な単位に分割されるため、支援が不十分でも問題を探し当てるのが難しくなる。
一方相互依存が希薄になるに従い、相互の支援の重要性も薄れる。
問題は、相互に支援しあうことの重要度が、そのグループが行っている仕事の性質次第だということだ。どんな仕事でも相互に支援が求められるわけではないので、あらゆるグループがチームになる必要もない。(抜粋)
支援のフィードバック
支援のプロセスにおいても、支援が目標から外れてしまわないようにフィードバックは不可欠である。しかし、その為には支援者はクライアントが目指している目標をはっきりと知る必要がある。そのためにフィードバックを申し出る前に、控えめな質問をするべきである。
グループの場合には、有益なフィードバックを得ることは特に必要である。メンバー同士が進歩を確認するための会話をすることはチームワークを築き持続させるための支援のプロセスとしても大切である。
この時大切なのは、チームのメンバーが互いの顔をつぶしたり、相手を辱めたりすることなく、自分自身やほかのメンバーの作業成果を分析し、批評することである。そのためには、「オフライン」と定義される、時間や空間が必要である。
この「オフライン」の例として日本での飲み会がある。西洋での例としては「プロセス・レビュー」という会合があげられる。この「プロセス・レビュー」は、「地位や階級の規範を最小限にするとリーダーが宣言して、かなりくだけた調子で行われる話合い」である。
このような状況はひとりで生まれるわけでなく、相手の顔をつぶすことなく、役に立つフィードバックを互いに与える方法を学ばなければならない。
このフィードバックを有益なものにする場合は、支援関係に不可欠な相互の基本ルール従う必要がある。
- フィーバックは、求められるものでなければならない。もし支援者が一方的に助言やフィードバックを与えようと決めた場合、クライアントの感情を害したり、侮辱と受け止めらたりする可能性がある。
- フィードバックは、具体的で明確なものでなければならない。フィードバックを有益なものにするには、具体的な行動を再検討する中で行われる必要がある。具体的な行動へのフィードバックにのみ意味のある学習をするチャンスがある。ここで大切なのは、その指摘が手厳しいというより建設的に聞こえるようし、敬意と品行という規範を守らなければならない。
- リーダーはフィードバックを求めようと自分たちのパフォーマンスについて質問をメンバーに募るとよい。フィードバックの求めにイニシアティブを与えるとメンバーがさらに耳を傾ける可能性が増える
- フィードバックは評価的なものより、説明的なもののほうが機能する
ここまでのところを要約すると、チームのメンバーが支援者になる方法を学ぶには、互いが率直にコミュニケーションできるよう、社会規範が一時的に保留された状況を求められるということだ。そうしたフィードバックは次の条件で、最良の状態に働くだろう。強要されるのではなく、自らの求めたもので、具体的かつ明確であり、共通の目標に適合していて、評価的なものというよりは説明的なものである場合、相互に支援し合う関係を育み、仕事に伴うプレッシャーがあっても、チームは円滑に機能するだろう。(抜粋)
このフィードバックの原則は、チームだけでなく、友人同士や配偶者との間のように一体一の状況でも当てはまる。
離れた場所からの支援
次に著者は、離れた場所にいるチームでも有効な支援が出来るかという話題に移る。まず電子メールや電話での支援することは可能であるが、支援しようとする努力は失敗することが多いという事実から分析し、それにより二つの命題をもたらすとしている。
一つ目は、早いうちにチームが役割関係とお互いの地位という問題を解決すれば、距離があっても支援は間違いなく成功するというものである。早いうちにチーム・ビルディングが行われていれば、通信機器を解してもお互いの貢献の解釈をしり、電話や電子メールによる支援も行うことが出来る。
二つ目は、まったくお互いに面識がない場合は、相互に受け入れ合うという規範が、言葉だけを通じて作られなければならない。ここで重要なのは、助けになってあげたいという欲求を相手に起こさせることが出来るかという点である。この欲求を起こさせるのは、書かれたメッセージの長さと調子を通じてしか伝えられない。そして著者は次のように指摘している。
厳しい時間的制約がないかぎり、見知らぬ同士によるネットワークが、適切な質問をすることによって支援関係を築けることは明らかになっている。(抜粋)
まとめ「⑦ チームワークの本質とは?」
最後に「⑦ チームワークの本質とは?」全体のまとめが書かれている。
効果的なチームワークや協調、協力は、一貫性のある、効果的な相互の「支援」として理解される。その支援のプロセスでは、まず初期段階で全員の欲求やスキルを確認するために、お互いがよういに質問できるように親しくなることが必要である。そしてグループが活動を始めた後にも、フィードバックやさらなる役割の話合いが可能となるように定期的な再検討のプロセスが必要である。このフィードバックを容易にする環境を作るためには、リーダーの控えめなリーダーシップが求められる。リーダーは地位や役割の問題を解決するためにグループから助力を受け入れなければならない。そのためこのプロセスが機能するように全メンバーの面目を保つという規範に敬意を払う必要がある。
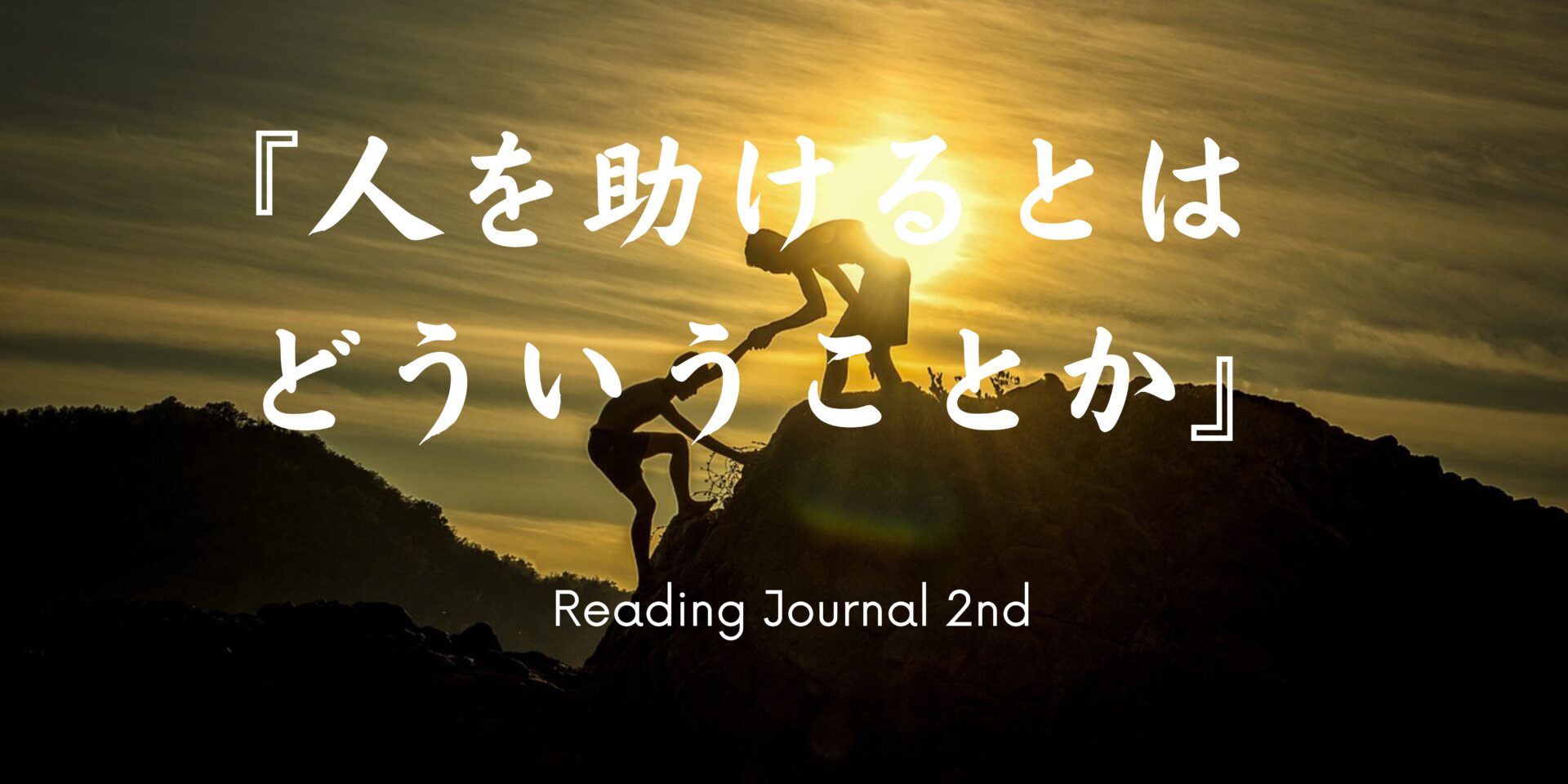
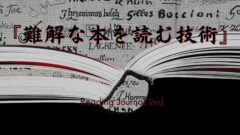

コメント