『人を助けるとはどういうことか』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
⑥ 問いかけを活用する(前半)
今日から「⑥ 「問いかけ」を活用する」に入る。ここでは、支援のプロセスで重要な部分をなす質問がどのような役割を果たすかを、具体的な6つの例をあげ、解説される。
この章をまとめるにあたっては、例の詳細は触れず、指摘される重要な事柄を中心にまとめる。また、6つの具体例を3つずつ2回に分けてまとめる。それでは、読み始めよう.
事例1 妻の頼みごと — 日常の支援
ここでは、非公式的な日常の支援においても、今まで解説された支援のダイナミクスが働くことを示している。
この例は「妻が紅茶を入れて欲しい」という支援の要求に始まる。まず著者は、このような日常の支援においても、まずはプロセス・コンサルタントの役割になり、「純粋な問いかけ」から始め、妻が本当に求めているものを考える必要があるとしている。なぜならば、それ要求が単に紅茶を飲みたいだけか、それとももっと重要なことを話すためのきっかけにしたいかを確認する必要があるからである。
ポイントは、新しい情報が現れるように、会話する余地を作ることだ。もし、何も表れなければ、当然ながら私は紅茶の支度をする。(抜粋)
ここでありそうな問題として、そのまま何もしないことがある。この場合は、支援を与えられず、その理由も与えないため、会話は開かれたままとなり、人間関係のいくらかが損なわれる。
そして、何かの理由でその支援が与えられない場合は、互いの面目が立つような理由を与える必要がある。その新しい情報を得た妻には、自分の要求を引っ込める機会ができる。
重要な点は、私の介入が相手の要求を認め、敬意を払ってそれに対処したものだということだ。私と妻との関係はバランスの撮れたものに保ったが、彼女のために会話のループを開いたことになり、それによって、妻は考慮すべき新たな情報を得たのである。(抜粋)
事例2 「議題はどこから生まれるの?」 — 無知を利用した問いかけ
事例2と事例3は、共に著者がある会社の重役会議の効率化の依頼を受けたときの話で合う。
この重役会議では、二時間の会議中に議題の半分も終わらすことができなかった。著者はその効率化のために様々な介入を行ったが効果はなかった。そして、このような会議に何度か出席した後で、「こうし長い議題はどこから来るのか」と尋ねた。すると、議題は秘書から提出されるが、そのまとめ方を誰も知らないことがわかった。そして重役たちは、話し合い議題の並べ方を変える相談をし始めた。
そのグループに最も役立ったのは、議題がどこから生まれているのかという、私のまったく無邪気な質問だった。私は自分の無知を見事に利用したのである。(抜粋)
事例3 「社外会議という解決方法」 — 対決的な問いかけへ
しばらくすると、そのグループは、議題に優先順位をつけるだけでは問題が多すぎることに気がついた。そして、議題には「即座に注意を払わねばならぬ議題」と「長期的な政策や戦略のように時間をかけて議論しなければならない議題」の2種類があることがわかった。いつもは緊急の議題が優先され会議の時間がそこに集中し、長期的な議題については、議論がまったくできていなかった。
そして、彼らは、毎週の初めに緊急の項目を話し合い、隔週の金曜日に重要な長期戦略を話し合うことを提案した。そこで著者は、対決的な質問に変えて「そうした政策や戦略といった厄介な問題に取り組むだけの時間やエネルギーが、金曜日の午後にあると思いますか」と質問した。なぜならば会社の会議室に集まっても、自分の仕事にまだ心を奪われていて、政策や戦略といった問題に集中できないことを著者は感じていたからである。
そこで著者はさらに「オフィスを離れて、邪魔の入らないところで政策や戦略についての会議を開いたら、いっそう効果があがるとおもいますよ」と提案をした。すると、すぐに同意の声が上がり、毎月、社外で会議を行うという新しい考えについて議論が進んだ。
私は対決的な質問を通じて、グループが時間や空間をどう管理するかの視野を広げたのである。(抜粋)
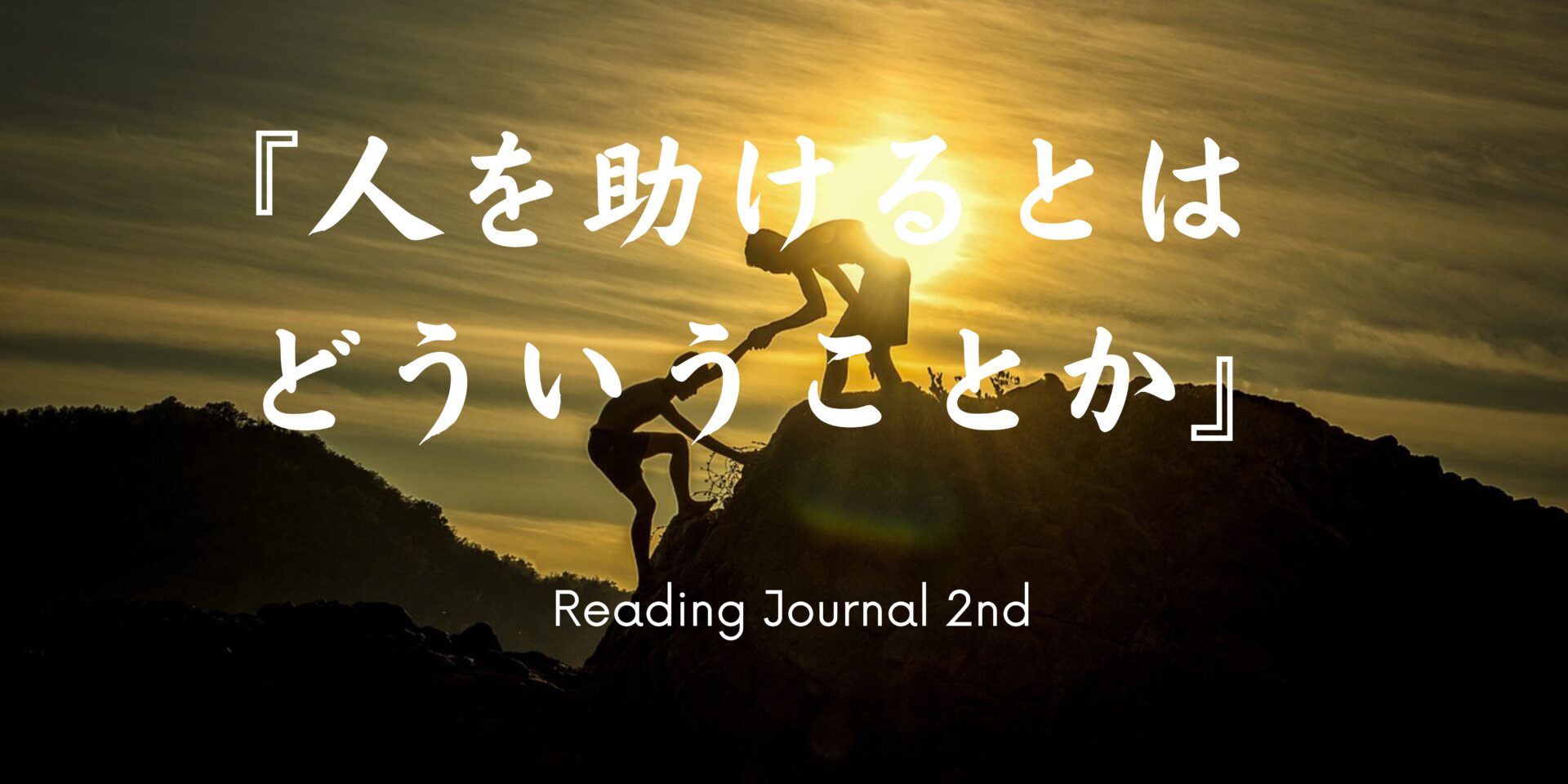
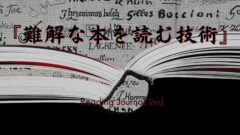

コメント