『外国語学習の科学』 白井恭弘 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第1章 母語を基礎に外国語は学習される(後半)
今日のところは、「第1章 母語を基礎に外国語は学習される」の”後半“である。”前半“では、母語と学習言語との言語間距離により、学習の困難さが異なること。その原因として母語の転移があることが説明された。今日のところ”後半“では、母語の転移(言語転移)が起こる条件を探り、母語の文化的転移もあることがわかる。さて、読み始めよう
言語転移がおこる条件
“前回”の最後にあるように七〇年代には、第二言語習得の普遍性にばかり注目が集まっていたが、七〇年代終わりごろからまた母語の影響の研究が盛んになる。そして「言語転移がおこる条件」の研究が中心となり現在に至っている。
どのような条件で言語転移が起こりやすい、またおこりにくい条件がある程度わかってきている。
たとえば学習環境で言えば、文法訳読方式中心で教えているところでは転移がおこりやすく、それに対して学習者の母語を使わず、主として外国語によってコミュニケーションを通して教えているところでは転移がおこりにくいということがあります。(抜粋)
また、「話すことを強制すると転移が起こりやすい」と言われている。学習者の外国語能力が不十分だと、母語に頼って変な外国語を話してしまう、危険性がある。ただし、ブロークンでも話せないよりは話せた方がいいので、話す練習を止める必要はない。インプット(聞くこと、読むこと)とアウトプット(話すこと、書くこと)のバランスが重要である。
言語項目の「典型性」
オランダのエリック・ケラマンの言語転移が起こる条件についての研究から、「言語項目の典型性(プロトタイプ性)」が重要な役割を担うことがわかった。
ケラマンの研究により、ある言語項目(語彙や文法など)について、人は何が典型的なものかどうかについての直感を持っている。そして典型的なものは外国語に訳せるが、そうでないものは訳せないだろう、という判断をする、ということが明らかになった。ただし、会話中でもこの原則が成り立つかについては今後の研究する必要がある。
この部分は、著者は具体的な例を示して解説している。ようするに母語で典型的な意味や使い方の言語項目はそのまま外国語に使えるかな?キット、と考え逐語的に訳してしまうが、典型的でないものは、ちょっと待てよ?これそのままでいいかな?と思うのか、慎重になるってことですね。言語項目で典型的なものほど、「言語転移がしやすい」!!っと解釈しました。(つくジー)
発音と母語の干渉
第二言語習得において音声面は、母語の干渉(負の転移)が強い領域である。
韓国人と中国人は、見かけでは区別するのは難しいが、英語を話すのを聞くと母語の干渉により大体わかる。特にイントネーションに特徴がある。
日本人の場合は、日本語でrとlの区別が無いために、発音も聞き取りも難しいことが有名である。
語用的転移(社会言語学的転移)
外国語学習では、母語の文化が明らかに干渉する。日本人は、褒められた時などは、謙遜するがこれはアメリカ人からすると奇妙に映る場合がある。
このような文化的な背景に根ざした言語転移の問題は、「語用的転移」もしくは「社会言語学的転移」と呼ばれる。
「謝る」「断る」「依頼する」「ほめる」などの「発話行為」についての研究では、文化的な知識がかなり転移することがわかっている。そして、このような文化的知識の習得は難しく、意識的な学習にたよる必要がある。
このような文化的知識を学習者に教える必要があるか、ということについては、学習者に母語話者の文化を押し付けるという問題点も指摘されている。この点について著者は、そのデメリットを知っていて使わないのであればそれでいいと言っている。
母語にもとづいた言語文化的行動をして、その持つ意味がわからない、というのは、問題があります。つまり、そういった知識がないため損をするのは学習者なので、知識を教えておいて、それを使うか使わないかは本人に任せることが大事でしょう。(抜粋)
この文化的な背景は、たとえば日本では、「動作主を隠す」という傾向があるため、自動詞が発達しているが、そのようなことが外国人には納得しずらい、というような広がりがある。
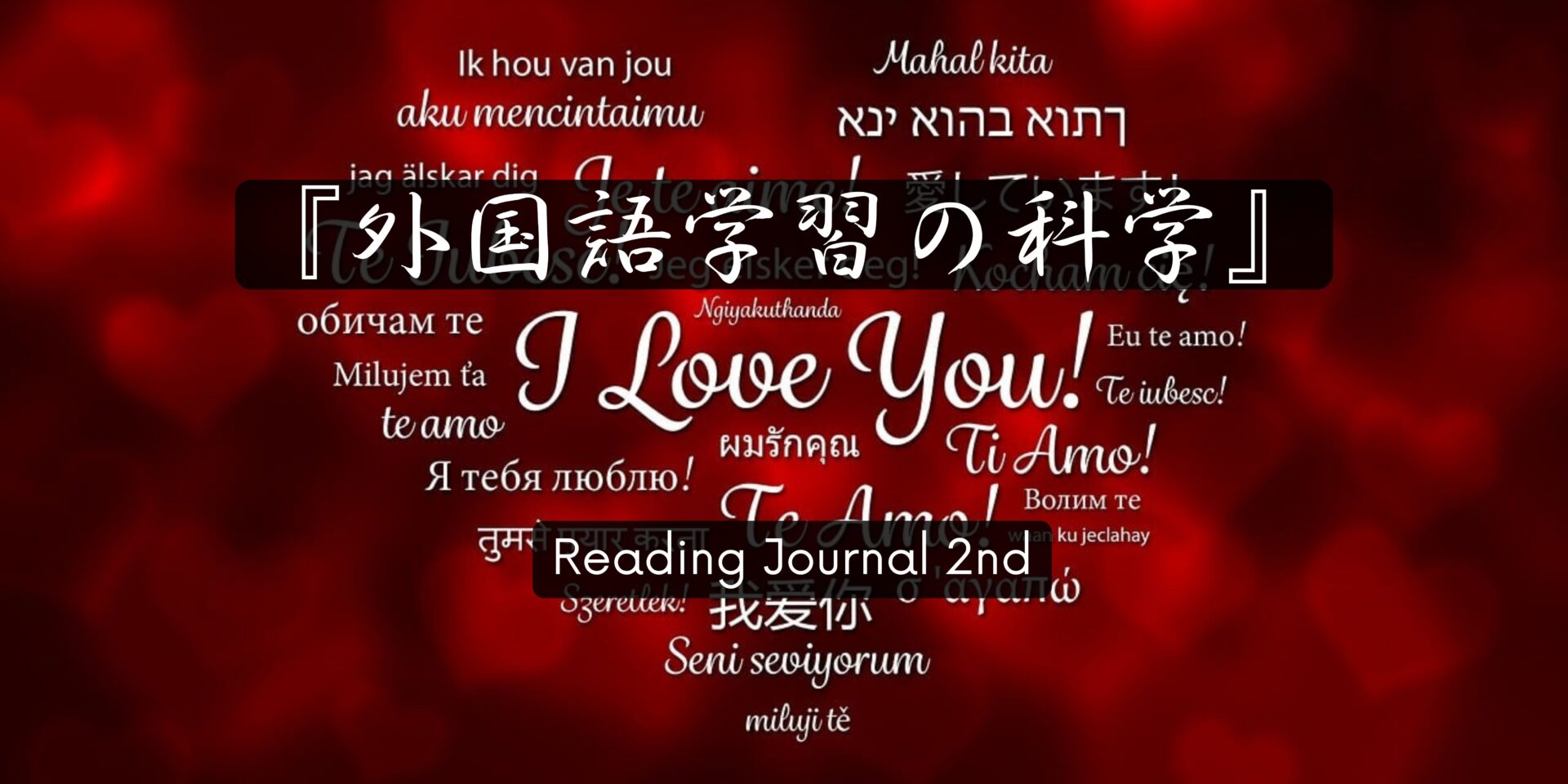


コメント