『外国語学習の科学』 白井恭弘 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第5章 外国語を身につけるために -- 第二言語習得論の成果をどう生かすか (その3)
今日のところは、第5章 「外国語を身につけるために」の“その3”である。ここまで“その1”は、第二言語教育・学習の研究の変遷について、“その2”で、外国語学習理論で重要な「習得順序」と「発達順序」について解説された。今日のところ“その3”は、外国語学習で重要な“インプット”についてである。さらにその後“その4”では”アウトプット“について解説される。読み始めよう。
インプットの必要性
まず著者は、
よい学習法というのは、目標を効率よく達成する学習法のことである。(抜粋)
としている。
ここで、昔ながらの「文法訳読方式」は、英語を日本語に訳す力をつけるのが目標ならば、効果的である。しかし、実際のコミュニケーションの場面で使える英語を身につけるのが目標ならば、これは大変効率が悪い学習法であるとしている。
現状では使える英語力を身につけるという目標を達成するには、インプットの量が不足しています。日本語に訳してからその日本語を読んで意味をとる、というのは、自然な英語習得に必要な「インプットを理解する」という機会を学習者から奪っていることになるのです。(抜粋)
ここまでの章で、インプットが言語習得をすすめる上での必要条件であること、インプットによって第二言語の音声、語彙、文法の自然な習得がなされることなどが示された。
予測文法とは
インプットを理解することにより「予測文法」が身につくため、言語習得につながる。
「予測文法」とは、ことばを聞いているとき次に何が来るかを瞬時に無意識に予測することである。このような能力は大量の英語を聞いたり読んだりして理解するうちに身についてくる。また実際の会話をすることにより、自動化が進み、またリハーサルも行える。
ここで、注意をしたいのが「ある程度の基礎もないうちから、どんどん英語でコミュニケーションする」ことにより「変な」英語が身についてしまうことである(ココ参照)。そのため、コミュニカティブ・アプローチでアウトプットを強制する場合は、注意が必要である。
インプットのみでは習得できないこと
母語を習得する場合には、教わらなくてもインプットのみで言葉は身につく。そこで成人学習者も、インプットを理解するという経験だけで、十分であれば文法事項を教えなければよい。ここで著者はかなり難しい文法事項もインプットのみで習得で来ていたという自身の経験を語っている。しかし、上級の学習者を観察していると、やはり教わらなければ、ならない部分もたくさんある、としている。どこの部分が教わらなければならない部分で、どの部分がインプットで身につくかは、第二言語習得研究で解明しなければならないテーマだとしている。
ここで、著者が出した例であるが、・・・・・なんとすごい。
(1)Open me a beer.
(ビールを一つあけてください。 = Open a beer for me.)
(2)Open me the door.
(ドアをあけてください = Open the door for me.)(抜粋)
であるが、ここで(1)は〇で(2)は×なのである。
(二重目的語構文(SVOO)では、「間接目的語」を(何らかの形で)所有することになる。そして、ビールは所有できるが、ドアは所有できない)
これは、英語ネイティブならば例外なくわかるが、アメリカの外国人留学生だとわかる人とわからない人にわかれるという。
っで、著者は、言語学の授業で初めてこの説明を聞いた時、文法性の違いについて直感的にわかったという。つまり、それまでのインプットでわかるレベルになってたってことですね。すごい!
つまりは、インプットだけでも相当のレベルまで行けるってことだと思う。(つくジー)
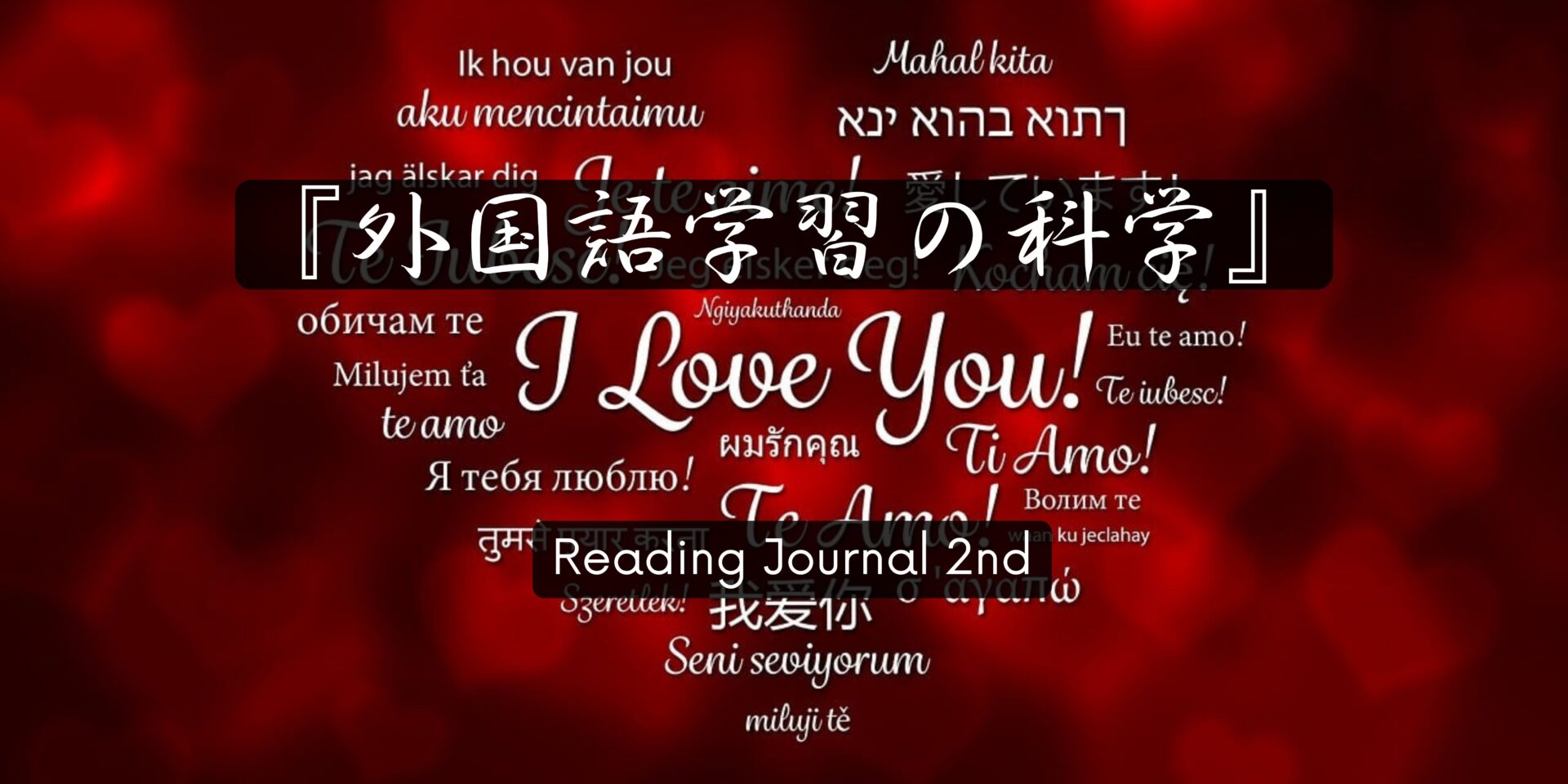


コメント