『プロカウンセラーの聞く技術』 東山紘久 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
13 相手の話に興味をもつ
カウンセラーの聞き方
プロのカウンセラーは一日八時間から一二時間も人の話を聞いている。しかし、それでも精神的には疲れないと著者は言っている。それは、相談者の話につきない興味を持っているからである。ただし、相談者の具体的な相談内容に興味があるのではなく、「相談者がどうしてそのような思いをするのか、どうしてそのような受け取り方、感じ方をするのか」に興味がある。プロのカウンセラーはそのような人間を感じる仕事をしているから疲れない。カウンセラーはどのような相談にも、常に「聞くモード」で、相手の話を聞き、決して具体的な内容に反発するような「反発モード」で話を聞くことはない。反発モードで話を聞くと、相手が十分話せないだけでなく、聞く側も精神的に疲れてしまう。
カウンセラーの興味
相談者が「日本人はみなバカですね」といった場合にも、「日本人はバカなことをする人もいるが、偉い人もいるのに」といった反発モードではなく、「どうして彼はカウンセラーに会ったときに疲れた顔をして、日本人はバカだなんて言うのか」と相談者の言動のもとになる、ものの考え方、感じ方に興味を持ち聞くモードで話を聞く。
そのため、カウンセラーは相談者が夢中になっている漫画や映画、音楽や小説などがあれば、必ずといっていいほどそれを見たり聞いたりして、相談者がどこに感動しているのかを知ろうとする。
相談者が興味をもつものを体験することによって、相談者への共感性を増し、体験差によって相談者自身を感じることができるようになるのです。(抜粋)
相談者の話の中には、カウンセラー自身も内容に深く興味がある話もある。しかし、このような時の方がむしろ聞くのが難しい。それは、自分の気持ちや感情によって相談者の話を聞いてしまうからである。これは共感しているようで、じつは共感ではない。
そのため、話の内容自体は、カウンセラーの興味を引かず、相談者がのめりこんでいる話の時の方がむしろ聞きやすい。
14 教えるより教えてもらう態度で
学びたいと思う心
人間には、教えたいという気持ちと学びたいという気持ちがある。そして「学びたいか学びたくないかを決めているのは、当人の心」である。このことは、聞き上手になるコツの一つでもある。
C・R・ロジャースの「来談者中心療法」
身体の調子が悪くて医者に行ったが、検査の結果異常なしといわれることがある。しかし自分の身体の変調は自分しかわからない(これを主観症状という)。一般的に主観症状があるのに身体の異常が見られない場合は、心身症の可能性がある。
臨床心理士の場合は、この主観症状がある場合は、それは本当の症状としてとらえる。
臨床心理士は当人が訴える以上、けっして異常なしとは言いません。「おもいすごしです」とか「気のせいです」とも言いません。臨床心理士は心の専門家ですから、「その人の心は、その人にしかわからない」ことを知っているからです。(抜粋)
「来談者中心療法」の創始者のC・R・ロジャースは、心理療法に診断も検査も必要ないと主張した。それは、評価者と当人との人間関係に対等性が失われ、真の意味での心理療法が行えないからである。
ロジャースがこのような主張をした理由は、心理療法は、医学モデルのような「なぜ(WAY)モデル」ではなく「どうすれば(HOW)モデル」の学問と捉えたからである。人の心は複雑なため、なぜを追求してもぎもんはけることがなない。
「その人の心は、その人しかわからない」
教えるよりも教えてもらう態度がわれわれに必要なのは、「その人の心は、その人しかわからない」からです。(抜粋)
ここで著者は、分裂病(統合失調症)の来談者との対応を例にして、カウンセラーがと来談者のやり取りがどんなものかを説明している。臨床心理士は、来談者の幻聴の症状を否定せずに、その人と話をして教えてもらおうとする。それは「その人のこころはその人にしかわからない」からである。また人間は否定されると心を開かず来談者との関係も深めることができない。
ここで私が強調したかったのは、分裂病の治療に関してではありません。少し極端な例をあげましたが、心のケアには教えてもらう態度が重要だということを、知ってもらいたかったのです。分裂病の人は、なかなかコミュニケーションがつかない場合も多いのですが、病的でない人ほどこのような態度が大切になります。「その人の心は、その人しかわからない」のです。(抜粋)
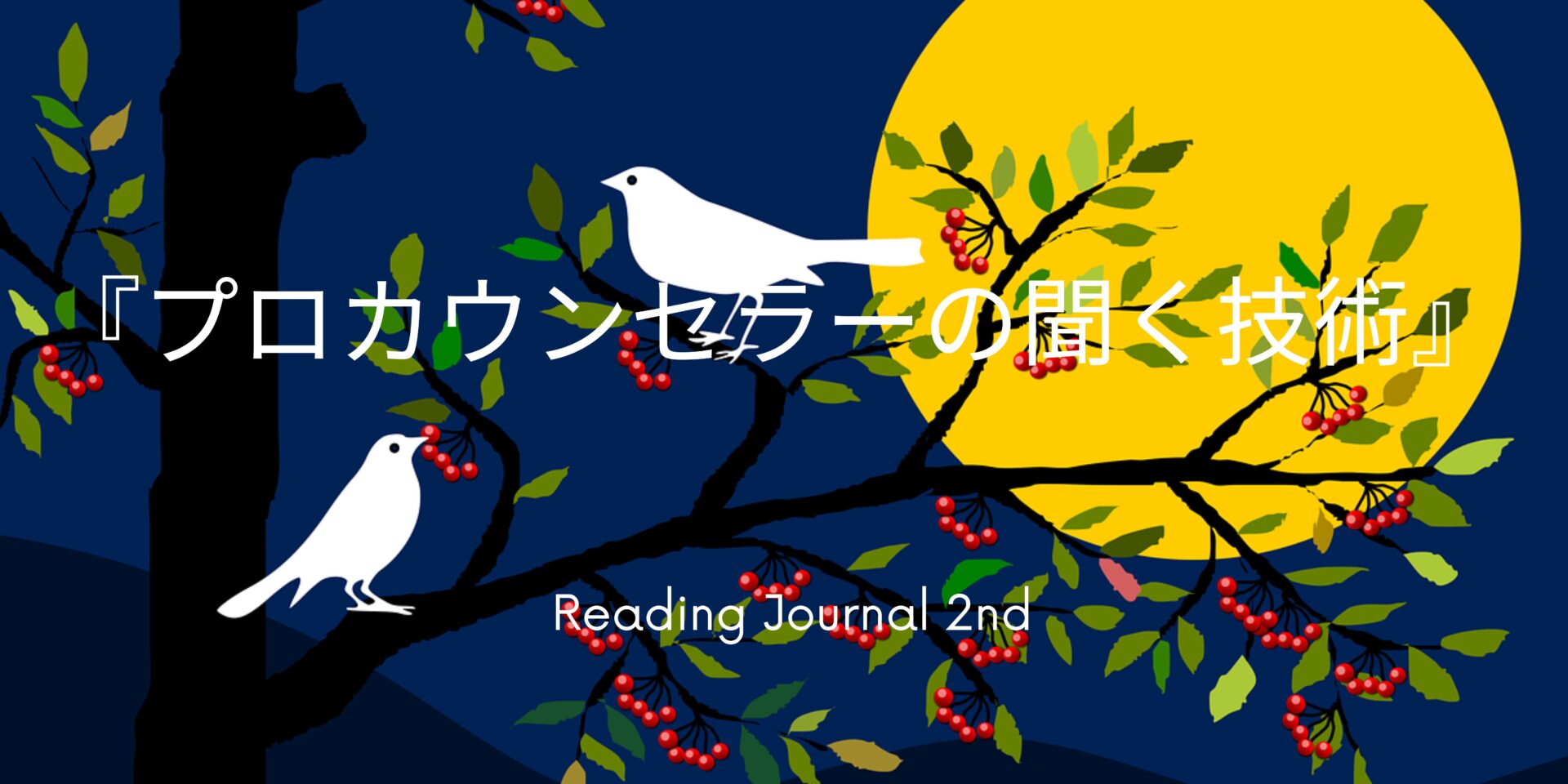


コメント