『プロカウンセラーの聞く技術』 東山紘久 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
19 相手の話は相手のこと(わかるが勝ち)
相手の話は相手のこと
来談者の相談が、男性に対する非難であることがある。著者は男性であるが、この時来談者にとって著者は男性の範疇に入っていない。もしカウンセラーが男性と気がついても、来談者からすれば「自分の話は自分のこと」である。そして逆にいえばカウンセラーからすると「相手の話は相手のこと」なのである。
客観的な立場に立って聞いていれば、「相手の話は相手のこと」というとして話を聞けるが、自分の関与が入っていくと、この原則が貫けない。たとえば、奥さんが隣の奥さんの悪口をいっている場合など、なかなか冷静に話を聞くことが出来ない。しかし、それでも「相手の話は相手のこと」なのである。
この指標が生きていないと、奥さまの話を聞いてあなた自身が隣の奥さんに腹を立ててしまいます。あなたは間接者であったはずなのに、いつのまにか腹立ちの主体に変化しているというわけです。
しかし、奥さまの腹立ちには共感してあげる必要はありますが、あなたが腹を立てるいわれなないのです。(抜粋)
「相手の話は相手のこと」と思いながら共感的に話を聞くことが必要である。
わかるが勝ち
このように聞き上手になるということは、難しいことである。それは、人格と相手の気持ちや心に対する理解力が関係しているからである。
「相手の話は相手のこと」が、温かい気持ちでできるためには、相手の心に対する理解が必要です。家族や友だちなど自分にとって大切な人を失わないためには、つねに相手を理解しようと心がけることが第一なのです。自分の立場を主張するのではなく、相手の気持ちになって、しかも相手と自分を混同しないこと、これがこの項のテーマなのです。「わかるが勝ち」なのです。これもなかなかむずかしいことですが。(抜粋)
20 評論家にならない
自我関与度
話を聞いてもらう場合、聞き手がうわの空だったり、聞いているふりをしている時、一番腹立たしく感じる。それは人は無視されるのが一番つらいからである。
この「自分の気持ちをあることにどれくらいかかわらせているかの程度」を「自我関与度」という。この自我関与度が低い発言は「評論家的」といわれる。
前項で「相手の話は相手のこと」と書きましたが、これは相手の存在を代替不可能と認めることであって、相手を突き放すことではあありません。もしあなたが話しかけている人への共感性を失いますと評論家的になってしまいます。(抜粋)
話を聞く技術は、相手中心でこちら話さずに受身である。しかし、それを形から入って相づちうって手短に「オウム返し」のように答えると消極的な聞き方になる。反対に積極的に聞こうとするとどうしても聞くよりも話しがちになってしまう。
ロジャースの「積極的聞き方」
「来談者中心療法」の創始者ロジャースは、カウンセラーの聞き方を「積極的聞き方(active listening)」と名づけたが、彼の実践記録を読むと、来談者の話を受身的に聞いているだけに思えた。そのため日本に彼の理論が導入された当初は、相談者から壁に話しているようだと非難を受けた。
聞くことは理解する事なのですが、いまでは考えられないようなことですが、ただ聞いて、相手の心を理解しなかったのです。(抜粋)
つまり、積極的に聞くということは二律相反の原理を含んでいる。積極的になろうとすると「聞く(listen)」が「たずねる(ask)」になってしまう。しかし、それを避けようとすると消極的になってしまう。
相手を理解するということ
評論家は正論をいい、相手にも正しいことをするように言う。彼らはいつも正しいく、自分では痛みを感じず、人に痛みを押しつける。そのため、正しいことばかりを言う人は評論家か傍観者に見えてしまう。彼らは正しくあるために何もできない。何かをすると失敗してしまうことがあるからである。
聞き上手は、相手の言う内容がどのようなものであろうと、そこには一理あることを認識しています。成長とは、悪をすることではないのですが、悪を受け入れる面をもって言います。(抜粋)
相手の話を聞き、相手を理解しようとする人は、正しことだけにのみ目を向けるのではなく、人間の弱い部分、影の部分も認められるということが大切である。そして、影の部分のような深い領域まで入って話をきくとなると、評論家的態度ではすまなくなる。人の話を聞くことは、聞き手にとって話し手と弱点をどこかで共有することを意味している。
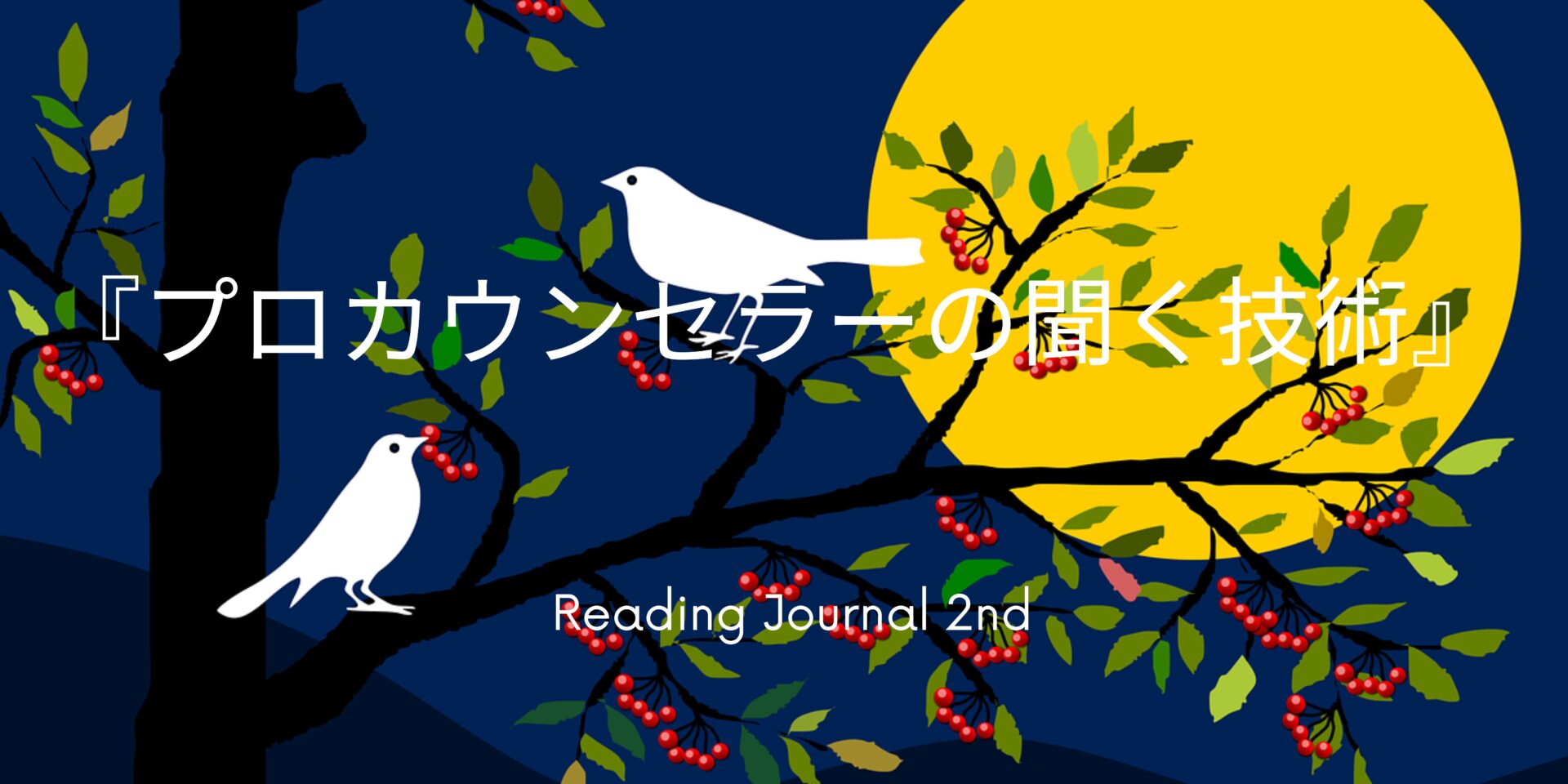


コメント