『あなたを変える行動経済学』 大竹 文雄 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第6章 ナッジとはなにか? (後半)
今日のところは「第6章 ナッジとは何か?」の”後半“である。”前半“では、行動経済学的な知見を利用して、人々に望ましい行動変容を起こす方法である「ナッジ」の概念が紹介せた。それを受けて”後半“ではナッジ選択のポイントを示し、ナッジの具体例を紹介している。それでは、読み始めよう。
ナッジの選択のポイント
ナッジの選択では、意思決定過程のボトルネックを見つけることがポイントになる。
具体的には次の四つのポイントに留意すると良い
- 本人が、自分がしなければならないことを知っていてそれが達成できないか?それとも望ましい行動を知らないのか?:もし知っているならばそれを前提とし、モチベーションを上げることである。知らにならば望ましい行動を活性化するべきである。
- 自分でナッジを課せられるだけ動機づけられるか?:十分に動機づけられる状態ならば、どのようなナッジがあるかを提供すればよいが、動機づけが弱い場合は、外部からナッジを与える必要がある。
- 知識が増えれば行動が起こせるのか?負荷が多すぎて正し情報が理解できないのか?(情報を与えれば処理できるかできないかということ):知識を与えれば処理できる場合は、正しい知識を与えることが重要となる。情報量が多すぎてどうすればよいかわからない場合は、あえて選択の幅を狭めてあげる方が良い。
- 競合的な行動のためできないのか?惰性のためにできないのか?:A(例:勉強)がB(例:遊び)と競合してできないならば、Bを減らすor Aのモチベーションを上げるナッジがよい。惰性のため(「現状維持バイアス」)ならば、それを変えるような仕組みがよい。
行動のボトルネックと対策
このようなボトルネックの原因を行動経済学的に考えると、まず「現状維持バイアス」、「損失回避」が挙げられる。そして特定の時間には限られた意思決定能力しか持っていないという「意志力」の問題、選択肢が多すぎるという「選択過剰負荷」や「情報過剰負荷」、さらには現在の好みが将来も続くと考える「投影バイアス」もある。さらには、「利用可能性ヒューリスティックス」「代表性ヒューリスティックス」「アンカーリング」なども問題になり、「同調効果」などのヒューリスティックスも行動のボトルネックとなる。
その対策としては、
- 自分がしなければならないことを知っているができないケース:自制心を活性化するコミットメントの提示や社会規範ナッジの利用。
- 望ましい行動を知らないケース:「情報提供」「デフォルト」「社会規範」が有効。
- 自分自身にナッジを課するだけの意欲がないケース:「デフォルト」「コミットメント」などの提供。
- 情報を正しく提供すればよいケース:「損失回避」「社会規範」の利用。
- 情報負荷が多すぎるケース:シンプルに必要な情報だけ絞って提供。
- 引き起こしたい行動と競合する行動が存在するケース:競合的な行動を抑制するために「社会規範」「ルール化」などの利用。
ダイエットの例
ここで、「ダイエット」の例が紹介される。
まず、ダイエットは、今日初めてもすぐに効果が得られないため「現在バイアス」が起こりやすいため、多くの人にむずかしくなる。また、ダイエットのような健康行動は不確実性がある。私たちは、確実なこととほんの少しでも不確実性があることを比べると、少しの不確実性のあるに大きなギャップを感じてしまう(「不確実性効果」)。
そこでダイエットのナッジとしては、「今日の行動を目標にする」ことがあげられる。また、目標達成に対しては報酬を与えるなどをするとよい(これは勉強にも応用できる)。また、決めた目標を達成できなかった場合は、罰則を決めておくなどのコミットメントを利用することも考えられる。さらには、仲間と励まし合うなどの贈与交換、運動や食事にルールを作るなどのデフォルトに利用などもある。
社会規範を使った残業削減のナッジ
次に病院の残業を減らすためのナッジの例が紹介されている。
そのナッジは、日勤と夜勤の看護師のユニホームを赤(日勤)と緑(夜勤)と分けることである。これを導入すると仕事量は変わらないのに残業時間が大きく低下した。このナッジは、誰が日勤で、誰が夜勤かはっきりさせることで、時間をオーバーして働いていると社会規範的につらいことになることを利用している。
ナッジに対する批判
ここで、著者は話を少し変えて、ナッジに対して次のような批判もあると紹介している。
- 「ナッジは人々の選択を特定の方向に誘導する」
- 「デフォルトで意志決定を変えるのは問題」
- 「アンカリングを使うのは問題」
- 「学習の機会を奪う」
- 「政府や官僚のバイアスや偏見が反映されている」
- 「ナッジにより市場競争が歪められる」
- 「ナッジは人の自主性を失わせる」
などである。ここで著者は、これらの批判に対して丁寧に、反論を行っている。
ナッジの種類
次に著者はこれまで説明したナッジの種類を3つに分類している。
- 「情報提供ナッジ」:利得と損失、社会規範、社会比較、返報性などを利用したナッジである。
- コミットメント手段を使ったナッジ
- デフォルトや自動化を用いたナッジ
デフォルトを利用したナッジ
ここでは、上の①.と②.を応用したナッジについてはこれまで紹介されたとして、③のデフォルトを利用したナッジを紹介している。
男性職員の育児休業取得をふやすナッジ
これは千葉市の例であるが、男性職員が育児休業を取得するときに、
- これまで:「育児休業を取得しない」がデフォルトになっていて、育児休業はオプションで取得する(オプトイン)。
- 改正後:「育児休業を取得しない」場合に上司が理由を聞き取る(オプトアウト)。
とした。このようにデフォルトを変更したナッジにより育児休業の取得が促進された。(同様な例は、警察での宿直明けの休業がある)
ジェネリック薬品の事例
国の方針でジェネリック薬品の促進するために、ジェネリック薬品の使用をオプトインからオプトアウトに変更した。変更後にジェネリック薬品の使用が大幅に増加した。
著者が関わったナッジの例
最後に著者が直接かかわったナッジの例として、コロナ感染症が流行していた時の「人との接触を8割減らす、10のポイント」の制定の話。手指消毒に関するナッジ、さらに「はみ出し喫煙禁止」のナッジについて詳細な解説がある。
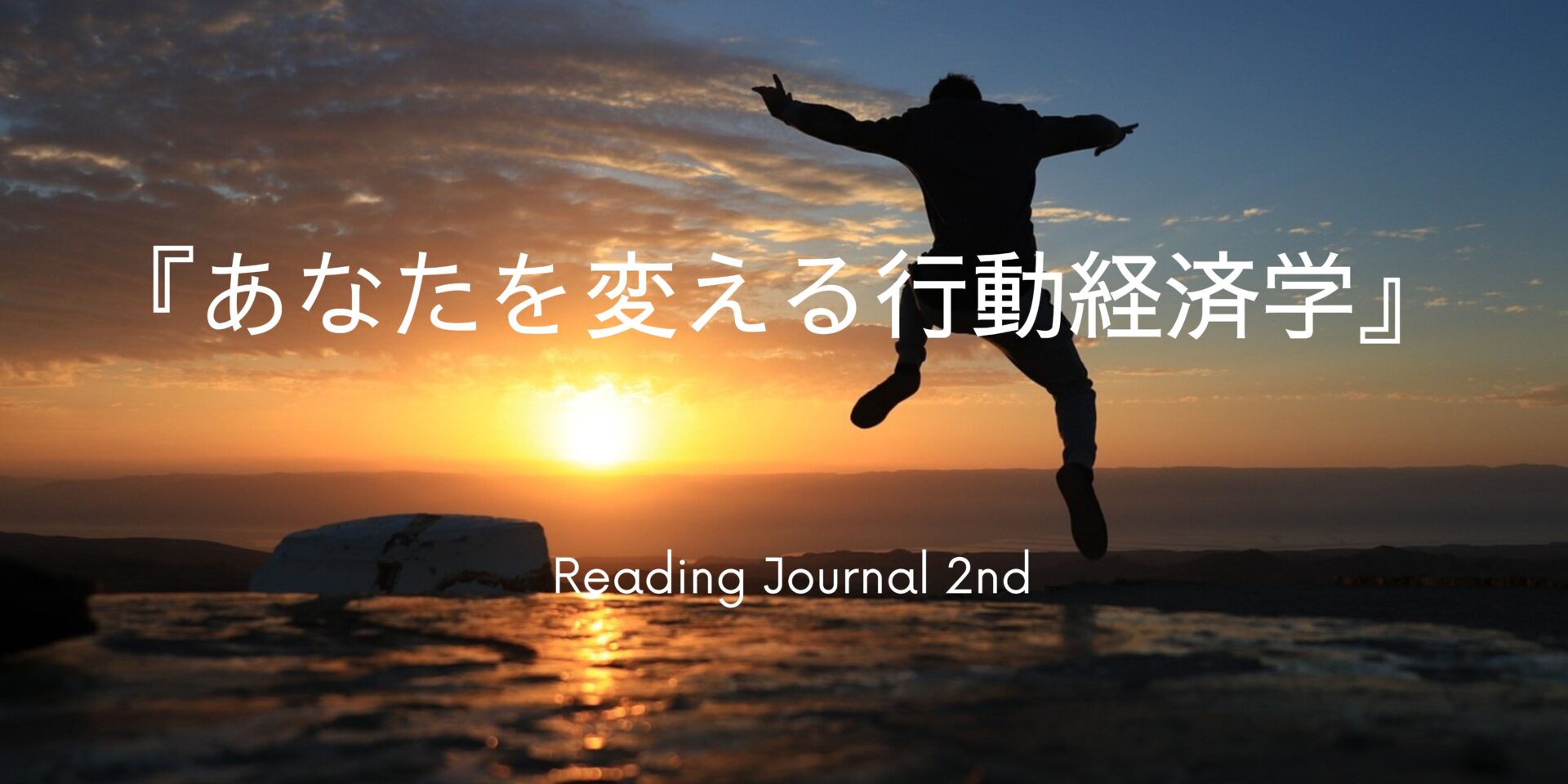


コメント