『あなたを変える行動経済学』 大竹 文雄 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
序章 直感が邪魔をする
今日のところは「序章 直感が邪魔をする」である。前回の「はじめに」に書かれていたように、ここでは「私たちの直観的意思決定が合理的な意思決定からずれてしまうこと」が紹介されている。それでは読み始めよう
「ホモエコノミカス」な人とは
はじめに著者は、3つの問題を出している。これらの問題は、小学校の算数レベルであるが、“直観的”に間違った答えを思いついてしまい、一流大学の学生でも正答率が高くないものである。
この問題はどれも普通の人は直観的に間違えた答えを出しがちだが、それを全問正解する人は、そうでない人に比べて
- 「時間割引率(=人間が将来の価値を割り引く率)が低い」人で、つまり将来を重視している。
- 「期待効用理論(=ある意思決定をするときのリスクの確立計算が得意)と整合的」
- 「損失回避をして、損失局面でギャンブルしない」(損失回避などは後述)
という特性がある。
即ち従来の伝統的経済学の前提となっている「ホモエコノミカス(合理的な経済人)」、つまり利己的で高い計算能力を持ちすべての情報を用いた意思決定を行う人である。
伝統的な経済学では、このような人間、つまり冒頭の問題を間違えない人間を前提としているが、行動経済学では、冒頭の問題を間違ってしまう人を前提に議論する。
「錯視」とバイアス
次に著者は、有名な「ミュラー・リアの錯視」や「エビングハウスの錯視」さらに「シェパード錯視」の図を持ち出し、このような「錯視」はそれとわかっていても、そう見えてしまうと説明している。
それと同じように、これから学ぶ「損失回避」「現在バイアス」「ヒューリスティックス」などの行動経済学的なバイアスも直観的な意思決定であるとしている。しかし、これらの「錯視」との違いは、「錯視」はわかっていてもそう見えてしまうのに対して、行動経済学の心理的バイアスは、わかっていたら対応できるようになれる事であるとしている。
ここで「錯視」と「行動経済学的なバイアス」の違いは、重要であると思った。錯視がわかっていてもそう見えてしまうのに対して、行動経済学のバイアスはわかれば対応できる!そうそう、そういうわけでこの本でそのようなバイアスについて勉強して、ちゃんと対応しようというわけですよね!
ついでですが、ここで取り上げている「ミュラー・リアの錯視」と「エビングハウスの錯視」は、「同じ同じ」と呪文を唱えてからガンバって見ると…同じかなぁ~と思えるのだが、「シェパード錯視」は、まったく呪文が効かない!これは同じに絶対に同じに見えない・・・・・(つくジー)
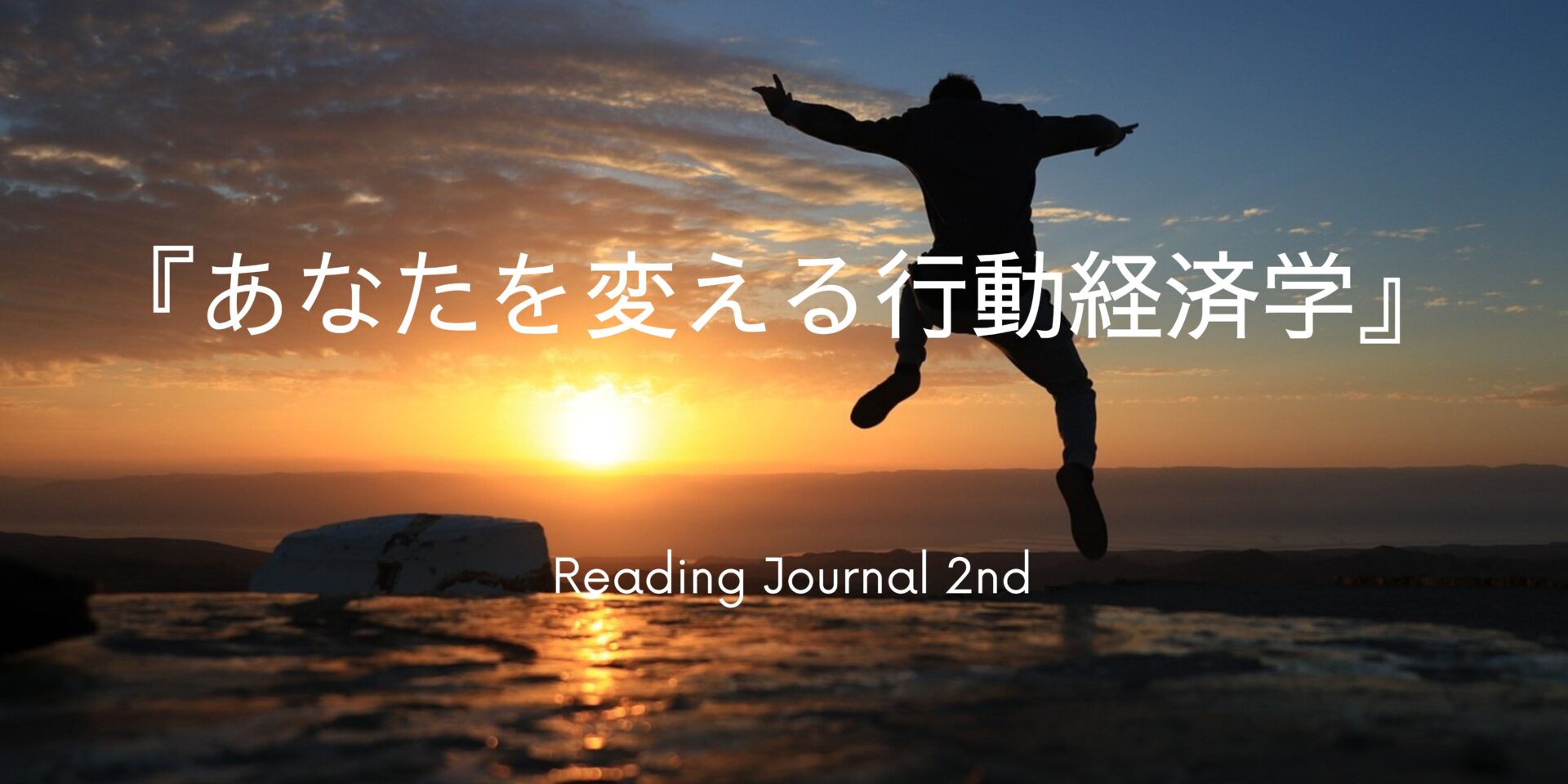


コメント