『アメリカ革命』 上村 剛 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
序 章 国家が始まるということ――ローマ、アメリカ、日本
今日のところは、「序章 国家が始まるということ」である。ここでは、本章に入る前に、著者の立場を明確にしている。まず、始まり、国家の始まりとは何かを、マキャヴェリを援用して論じ、アメリカの始まり、革命とは、と論を重ねる。そして成文憲法がアメリカ革命の最大の功績であり、それがアメリカの始まりを意味すると論じる。それでは、読み始めよう。
国家の始まりとはなにか
著者はまず「国家の始まり」について考察している。
始まりにはいろいろなものがあるが、すべての始まりは、「持続の裏返し」という特徴がある。つまり、実際には持続しているものを、ある時点で切り、そこに新たに意味を与えることが「始まり」である。
この「始まり」を「国家の始まり」とすると、理解はいっそう難しくなる。
西洋の政治思想家たちは、しばしば国家の始まりに立ち返ることで、独創的な思考を紡いできた。(抜粋)
一六世紀のイタリアの思想家マキャヴェリは、国家の繁栄に必要な、市民の活力や徳がどうしたら腐敗することなく保たれるか、を検討するため、国家の始まりを論じた。
彼の答えは、私利私欲を持たない国家の創始者(立法者と呼ばれる)が宗教的な力も借りて素晴らしい法律や統治機構を作り、その制度設計によって市民たちを涵養し続ける、というものだ。(抜粋)
マキャヴェリは、このような国家の代表例として古代ギリシャの都市国家スパルタをあげ、ローマも幸運にも恵まれ、繁栄の基礎を築けたとしている。
このような国家の繁栄をその始まりに求める考え方は、「第一原理への回帰」と呼ばれ、ある政治制度がダメになることを乗り越えるためには、国家が原点回帰をすればよいという考え方である。
国家の始まりを考えることが、その国家の原理の解明になる。これがマキャヴェリの発見だった。(抜粋)
このように、国家の繁栄するためには、始まりをどうするかが決定的に重要だという考え方は西洋政治思想の伝統の中で継承されている。
日本国の始まりと八月革命説
ここで著者は国家の始まりの例として、日本の始まりを八月革命にあるとする説に言及している。
西洋思想史における議論の延長上に、現行の日本国の始まりを社会契約というフィクションに求める立場がある。(抜粋)
この立場では、一九四五年八月を境にして、秩序が崩壊し自然状態の社会が誕生したとする。そして、国民が社会契約を交わしたという論理だてで日本国家を理解する。この国家の始まりは法的には革命である。これを八月革命説という。
第二次世界大戦後の日本国憲法は、明治憲法の改正という形で制定がすすめられたが、明治憲法では国民主権がうたわれていなかったため、国民主権を原理とする日本国憲法との連続性が保たれない。この矛盾を説明するために、一九四五年のポツダム宣言を受諾した際に、その中で歌われている国民主権を認め、主権が移動したと考えるのが、八月革命説である。戦後の日本が新憲法を手にしたとき革命という学説を必要としたのは、革命が始まりを意味するからである。
重要なのは、個人の始まり同様に、国家の始まりもまた、持続の裏返しである、ということだ。だから、国家が持続しているかいないか、という議論はそれ自体にはあまり意味がない。意味があるとすれば、どこに国家の始まりを見出すか、という点を問うてみることだろう。(抜粋)
アメリカ革命とアメリカの始まり
アメリカの建国は、日本ではアメリカの独立、独立革命と呼ばれているが、英語では単にアメリカ革命 (American Revolution) と呼ばれる。
著者は、このアメリカ合衆国の建国の始まりを考える際に、このアメリカ革命が重要であるとしている。
アメリカ革命は革命とは言えないという批判
ここで著者は、アメリカ革命は、その連続性を強調して革命とは言えないという批判があることについて触れている。
その骨子は、
- 独立で達成したものは、遅れてヨーロッパの争いに参入したこと
- 自由や平等は、黒人や先住民にはまったく達成できなかった
- 独立宣言の自由や平等といった理想の政治原理も支配の口実である
である。
また、独立後の政策もイギリスの真似であり、独立は一時的な離脱であり、革命的な出来事ではないという批判もある。
そのように考える立場からは、アメリカで起きたのは革命ではなく、せいぜい脱植民地化 (decolonization) といった程度の変化、とも言える。(抜粋)
このような立場に対して、著者はその主張に一理あるとしながら、後付けの評価によってある歴史的事象を簡単に修正してしまうことに慎重にならなければならない、と批判している。
革命とは何か
ここで著者は、革命という言葉の意味に立ち返り、革命が歴史の中でどのような意味で用いられるかを解説する。
革命 (Revolution) は、ギリシャ語、アナキュクローシスに由来している。アナキュクローシスは、ある政治体制が別の政治体制へと変動し、長い歴史のなかで元の政治体制に循環して戻ってくる(政体循環論)という一連の流れを意味する言葉である。
そして一六世紀に、ポリュビオスの『歴史』が、イタリア語、フランス語、ラテン語に翻訳された際に、アナキュクローシスは、革命にあたる各国の言葉に翻訳された。
そのため、革命という言葉は二つの意味が混在していた。
- ある政治体制から別の政治体制への変動という意味
- 長い歴史のなかで循環するという意味
マキャヴェリは、これを②の意味で理解し、第一原理への回復という考え方を示した。この考え方は後の思想家たちにも支持され、アメリカ独立を目指そうとした人々も慣れ親しんでいた。
だが、肝心なのは、同時代のアメリカの人々が、革命という言葉遣いの意味を、マキャヴェリとは異なって、一つ目の意味で捉えたことだ。(抜粋)
つまり、革命を新しい何かを始めることと捉えた。そして、それはヨーロッパでも同じであった。
このように、アメリカ革命は新たな時代の始まりである、という感覚は、同時代の人々に自覚されていたものだった。だからこそ、本書はアメリカ革命というタイトルを冠した。(抜粋)
誰の革命だったか?
ここまで議論により、アメリカ合衆国が革命によって新たに始まったことがわかった。次の問題は、誰がアメリカ革命を始まりとみなしたかである。
ここで著者は、近年のアメリカ革命研究で進展した三つの研究分野を紹介する。
- 白人エリートにとどまらないアクターの拡大 : 「建国の父 (Founding Fathers)」に焦点を絞ったスタイルは、あまりに一部の人たちの見解に偏りすぎている。政治史に対して社会史、文化史やミクロでの日常的な歴史の視点を取り入れる。
- スケールの拡大 : 東海岸の沿岸部に視点を集中させるだけでなく、より大きな国際的視点や大陸の内部の視点から検討する。(アラン・テイラー『アメリカ諸植民地』(二〇〇一年)、その入門書『先住民 vs. 帝国』 はその代表例)
- タイムスパンの拡大 : アメリカ革命の終わり従来のように一八一二年戦争終結ではなく、より長い時間軸でアメリカ革命を理解する
ここで著者は、このような人物と時間軸でアメリカ革命を描く場合には、多くの人が広い地域で躍動するさまを描くため、新書の紙面では難しいと言っている。そのため本書では、統一した切り口が必要となる。
なぜアメリカの独立は「革命」と呼ばれるにふさわしいのか?何が政変と異なるのか?アメリカ革命を考えるうえでは、そのような疑問に答えられなくてはならない。本書の答えは、連邦憲法という始まりである。これが統一した切り口となる。(抜粋)
憲法制定という始まり
ではなぜ、連邦憲法の制定(一七八七年)を始まりとするかについて、著者は、それが人類史上の新しい試みだったからだったから、と答えている。
憲法のもとにさまざまな権利を保障され、主権国家のなかで生きる。私たちにも馴染みがあるそんな生活は、太古の昔からあったものではない。むしろ近現代に特有のものであり、その出発点となった出来事こそが、アメリカ革命である。(抜粋)
世界発の成文憲法であるアメリカ合衆国憲法がその後世界中に伝搬した。
つまり、このアメリカ合衆国で行われた憲法を書くという行為が、ある国家の始まりを明確にする。
この始まりは、個々人の人生の連続性を無視することではない、重要なのは、始まりが確定されると、第一原理として働き、社会に何か問題が起きたときの解決法として原点復帰が可能となる。
今日のアメリカ合衆国でも、アメリカ革命は常に政治的理念の原点となっている。憲法を理解するとき、オリジナルな意味は何だったかを重視すること(原意主義)は、強い。そのため、アメリカ革命を理解することは、現在アメリカ政治に対する理解にも通じる。
最後に著者は、次のように言って本章を閉じている。
以上のように、本書は連邦憲法を第一原理として定めるという意味で、アメリカ革命が革命だったと理解するものである。成文憲法の歴史でもアメリカ合衆国の連邦憲法に起源が求められることから、これは二重の意味を持つ。第一に、アメリカ革命における始まり、アメリカ合衆国という国家の第一原理である。これは太平洋を挟んだ超大国の現在の政治理解に寄与する。第二に、成文憲法の歴史における始まり、である。
日本でも近年、憲法改正をめぐる議論がかまぶすしい。その際、そもそも憲法を書くとはどんなことなのか、成文憲法とはいったい国家においてどのような意味をもつのか --- 。そんな根源的問いかけを、再度始まりに戻って検討することは、私たちの未来にとっても重要な道しるべとなるに違いない。(抜粋)
関連図書:アラン・テイラー (著)『先住民 vs.帝国 興亡のアメリカ史:北米大陸をめぐるグローバル・ヒストリー』、ミネルヴァ書房、2020年
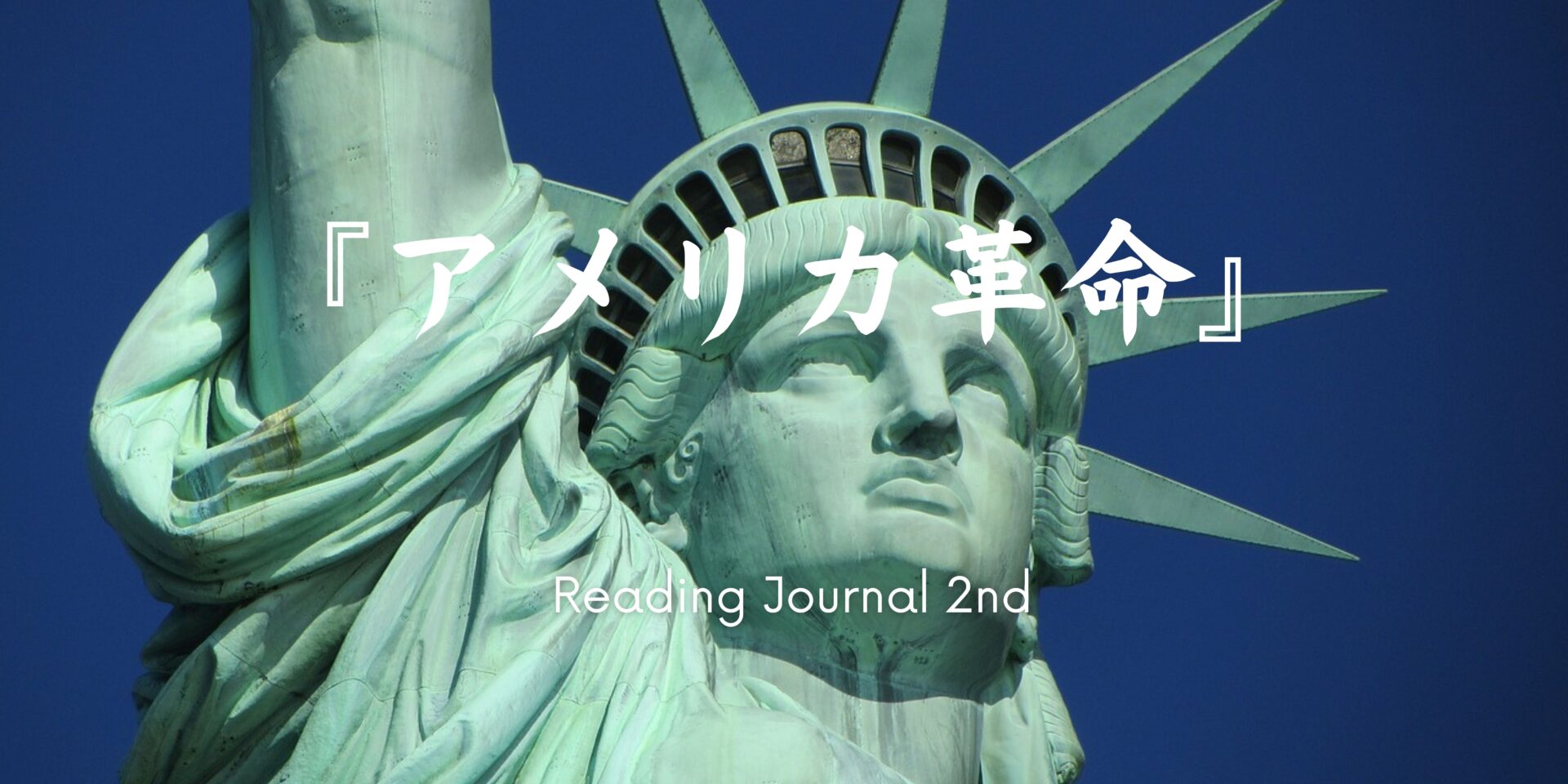


コメント