『100分de名著 安克昌 『心の傷を癒すということ』』 宮地 尚子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
もう一冊の名著 『エランベルジェ著作集』全三巻
最後に、「もう一冊の名著」として『エランベルジェ著作集』全三巻の紹介がある。これは安克昌の恩師である中井久夫の翻訳である。それでは、ラストスパート。
エランベルジェ著作集
アンリ・F・エランベルジェの著作集の日本語版は、1999年から2000年にかけて出版された。翻訳を手掛けたのは、安克昌の恩師であり日本の精神医学の権威でもある中井久夫である。また、中井は、エランベルジェの大著『無意識の発見(上・下)』の翻訳も共訳として手掛けている。
精神科医で精神医学史家のエランベルジェは、精神医学や心理学、精神分析が歩んできた歴史を社会的・文化的な広がりを持って辿り、心の治療を問い続けた人である。精神医学や心理学の理論・治療法などは、フロイト派、ユング派のように個別に語られることが多いが、エランベルジェは、一次資料を用いて事実の誤認を正しつつ、各派の体系を明らかにして、全体を俯瞰した形で比較を試みている。また、すぐれた先人の理論を掘り起こし、光を当てたという功績もある。トラウマや解離に関する理論や治療のあり方を示したピエール・ジャネの再評価などもエランベルジェの仕事である。
病理性の“秘密”
『著作集』第二巻に心にしまい込んだ”秘密“についての考察「病原性秘密とその治療」という章がある。
誰にでも、人に告げず心の中にしまい込んだ秘密があるが、そのような秘密により、さまざまな症状をきたし生活に影響がでることがある。そうした病原性を持った秘密に対してどのようなアプローチが可能かということを、この章では、歴史的経緯を踏まえながら論じている。患者の症状の奥には、このような語られない“秘密”が隠されている可能性があり、そのためステレオタイプに判断しないことの大切さが示唆されている。
今の状況を見直す種として
エランベルジェは、史的手法を用いながら常に現在や未来の精神医学のあり方を考えていた。彼の著作には、弱い立場にある人への共感が貫かれ、そうした人たちの持つ力や視点をとても大事にしていた。
このような視点は、中井や安の視点とも通じるものがあり、その範[はん]となったのがエランベルジェであった。中井は、『著作集』に寄せた文章で、著者への深い敬意と共感を示している。さらに中井の著書『西欧精神医学背景史』のあとがきで、「ありきたりの西欧を越える視点」を持つエランベルジェからの影響と、直接の交流が出来た喜びを明記している。
この『著作集』には、現代社会や世界状況を考える上でヒントとなる視点や指摘がたくさんあります。今読んでも新しく、今こそ読んでほしい名著。かつてこんなに豊かなものの見方をしていた人がいたということを、精神医学や心理学の専門家のみならず、多くの人に知っていただければと思います。(抜粋)
関連図書:
アンリ・F・エランベルジェ(著)『エランベルジェ著作集(全三巻)』、みすず書、1999 – 2000年
アンリ・F・エランベルガー(著)『無意識の発見(上・下)』、弘文堂、1980年(エランベルガーは、エランベルジェのドイツ語読み)
中井久夫(著)『西欧精神医学背景史 【新装版】』、みすず書、2015年
[完了] 全7回
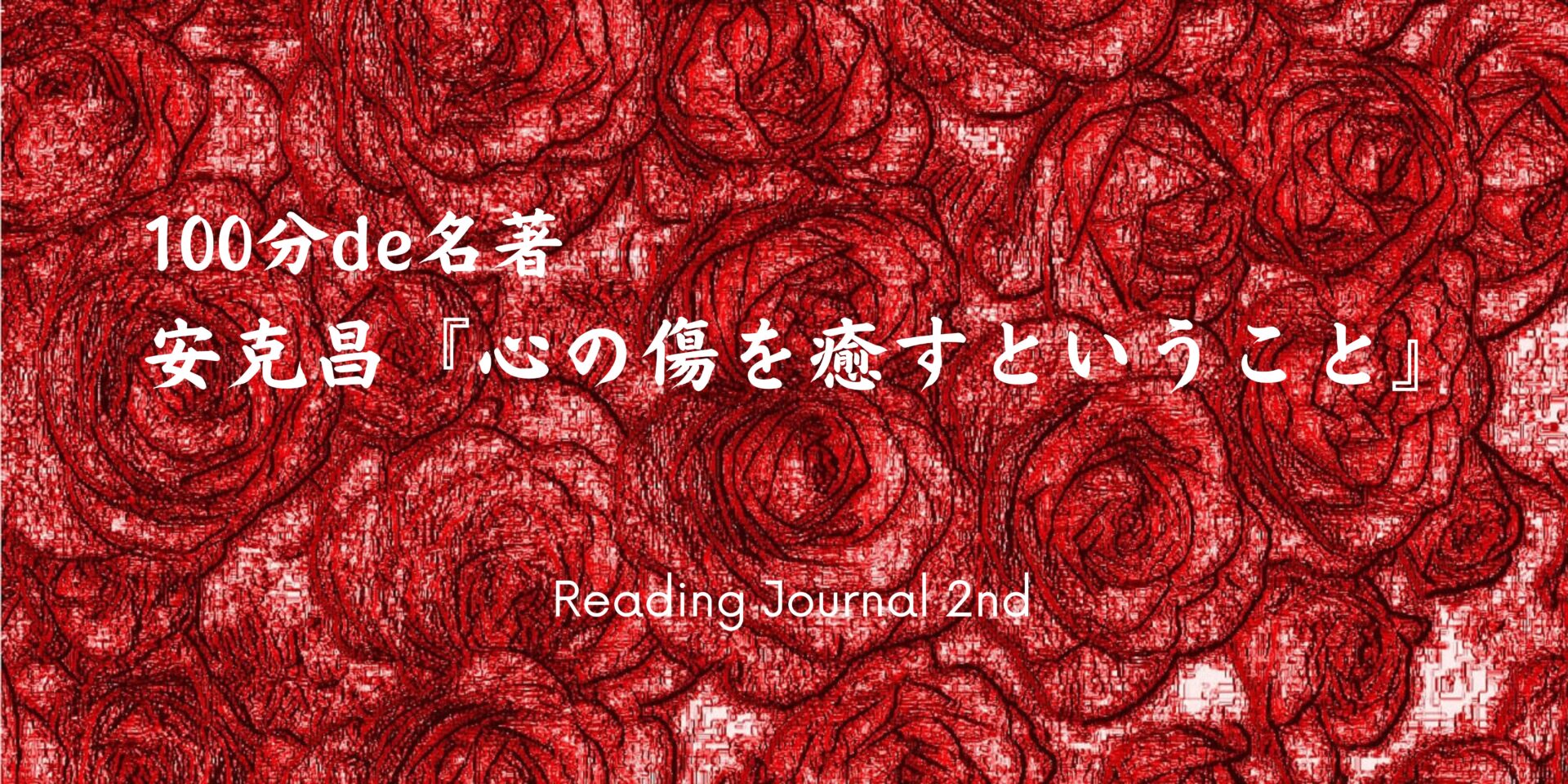


コメント