『100分de名著 安克昌 『心の傷を癒すということ』』 宮地 尚子、NHK出版、2025年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
はじめに 生きづらさを感じている、すべての人に
2025年のはじめの100分de名著は、安克昌の『心の傷を癒すということ』である。これを見たとき、ちょっと、あれ?と思った。もちろん『心の傷を癒すということ』は、名著に違いないが、100分de名著って、哲学の本とか仏教の本とか西洋の名著みたいな、ちょっと一般の人は読み解けないような本を扱っていて、ちょっと違う?って思った。
何でだろうと考えると、そうそう、今年は「阪神淡路大震災」から30年目の節目の年だったからですね♬
ちなみに『心の傷を癒すということ』は、他の本・・・・なんだったけ?・・・・で、紹介されていて、その紹介の仕方の熱量から、かなり良い本であると、目星をつけていた本です。今回は、まずは、放送を見て(録画だが)、この解説書を読んでみようかなと思ったのでした。それでは、読み始めよう。
きょうのところは「はじめに 生きづらさを感じている、すべての人に」である。ここでは著者というか解説者の宮地尚子が、安克昌との交友と、この本の書かれた背景などについて説明している。
安克昌の『心の傷を癒すということ』は、阪神・淡路大震災が起こった時、自ら被災した安克昌が、自らの奔走をまとめたルポルタージュである。安は、外側からの震災報道に違和感を持ち「被災地の内部から」誰かが書く必要があると強く思い、それこそ骨身を削ってこの本を書いた。しかし、その内面では被災地のことを文章に書くことは不謹慎ではないかと思い、それは「書くことはつらいことだった」と綴っている。
解説をしている宮地も安と同様に精神医であるが、実際に臨床の場で一緒に仕事をしたことはないと言っている。しかし、精神医療の基本的な考え方は一致していたとしている。それは、
精神医療にできることは限られているということ。心の傷は、社会のなかで生活を豊かにしていくことによって、少しずつ楽な付き合い方を見つけ、癒していくことが大事だということ。『心の傷を癒すということ』もそうした生活支援を重視した内容になっています。(抜粋)
であるとしている。
この本は、震災の翌年に出版され長く読み継がれていくのだが、安自身は、2000年12月に病気で亡くなってしまう。
そして2011年の東日本大震災が起こったとき、メディアで本が紹介されるのだが、初版もその後出版された文庫本も品切れ状態であった。そこで、宮地が出版社に掛け合い、ほどなく増補改訂版が出版された。さらに、2020年にはNHKでドラマ化され、そのごドラマ化のプロセスなども加わった新増補版が出版された。
日本では、東日本大震災の後にも2016年の熊本地震、2024年の能登半島大地震を始め多くの災害が続いている。このような時にこの本は助けになると宮地はいう。
『心の傷を癒すということ』は、そうしたときに、とても助けになる名著です。被災地のなかから見た心の傷つきは、それが時間とともにどのように変化していくのか。どのように癒され、あるいは傷を抱えつつ生きていくのか。周囲の人が、どのように関わるとよいのかということについても書かれています。(抜粋)
関連図書:
安 克昌(著)『心の傷を癒すということ』、角川書店(角川ソフィア文庫)、2001年
安 克昌(著)『新増補版 心の傷を癒すということ: 大災害と心のケア』、作品社、2019年
目次
はじめに 生きづらさを感じている、すべての人に [第1回]
第1回 そのとき何が起こったか [第2回]
第2回 さまざまな「心の傷」を見つめる [第3回][第4回]
第3回 心のケアが目指すもの [第5回]
第4回 心の傷を耕す[第6回]
もう一つの名著『エランベルジェ著作集』全三巻 [第7回]
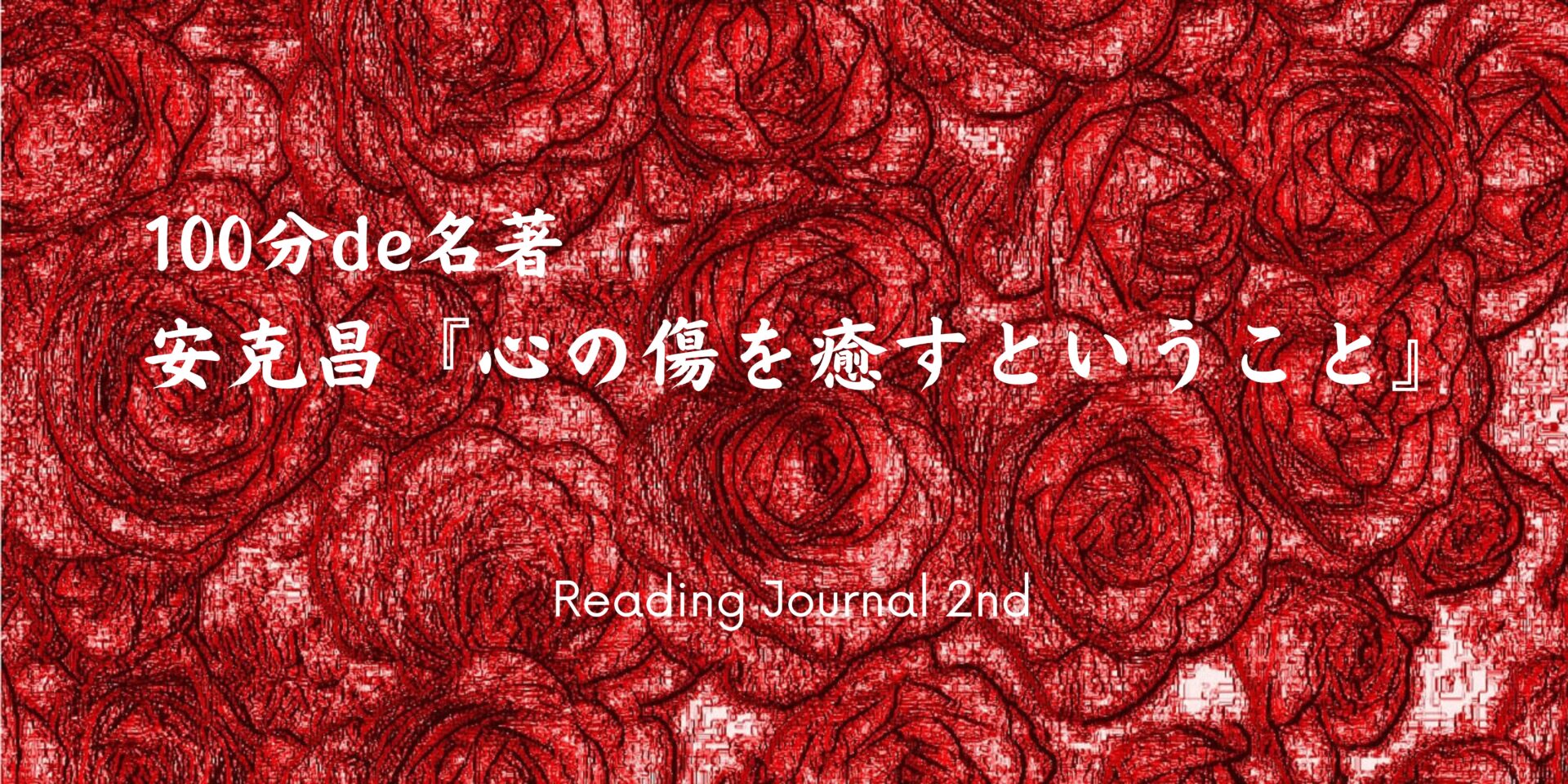

-1-120x68.jpg)
コメント