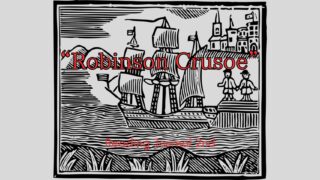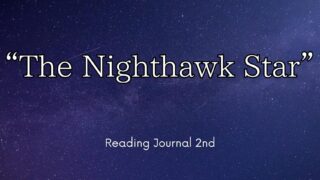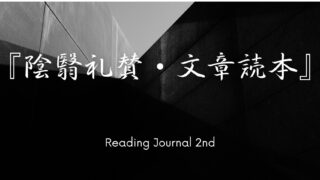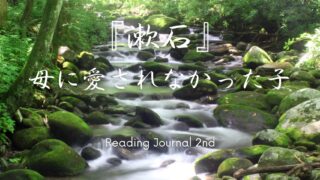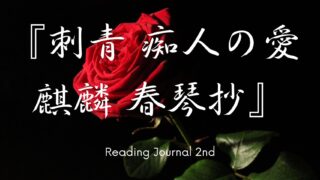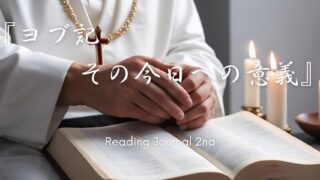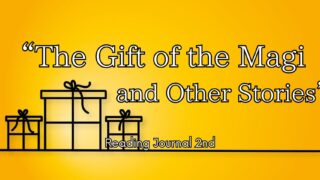 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd [review] “The Gift of the Magi and Other Stories”
by O. Henry [PENGUIN READERS LEVEL 1]
“The Gift of the Magi and Other Stories “は、PENGUIN READERS 版のO.HENRYの短編集である。O.HENRYの味わいある世界を300語レベルの英語で書かれている。:” The Gift of the Magi and Other Stories “より