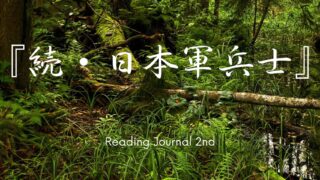 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 離島守備隊の惨状 — アジア・太平洋戦争末期
吉田 裕 『続・日本軍兵士』より
アジア・太平洋戦争の戦局悪化により食糧生産は大きく落ち込んだ。さらに、食料の輸送が困難になり離島などでは食料自活の方針となる。そのような状況で栄養失調による死者が増え、さらに食料を巡る日本軍内の争いまで起こる事態となる
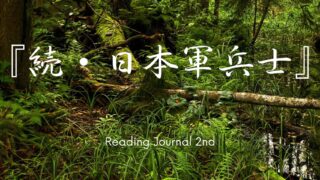 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 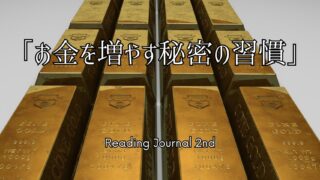 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 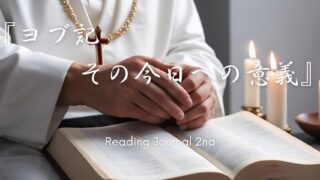 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 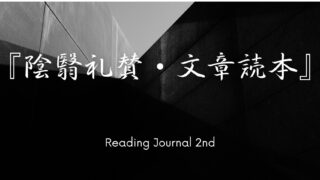 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 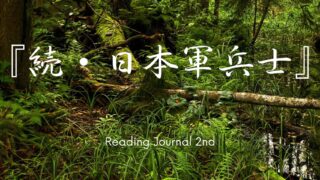 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 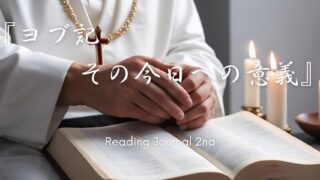 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 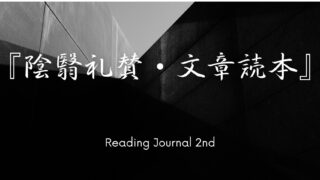 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 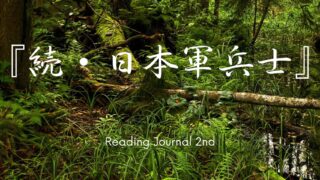 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 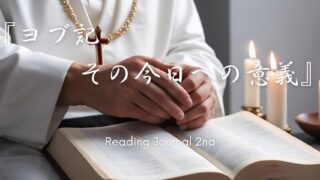 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 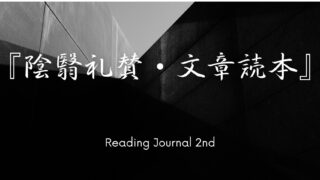 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd