 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 生きものの眼差し、人間の眼差し / どうぶつが生きる、ひとが生きる
柳田邦男 『人生の一冊の絵本』より
ここでは、動物と人間との関係を描いた絵本が紹介されている。まず前半は、柳田邦男が、感動したという『ジャガーとの約束』である。そして後半は、動物からいのちや生きることを学べる絵本である『コウノトリ よみがえる里山』を含む3冊の絵本である。:『人生の一冊の絵本』より
 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 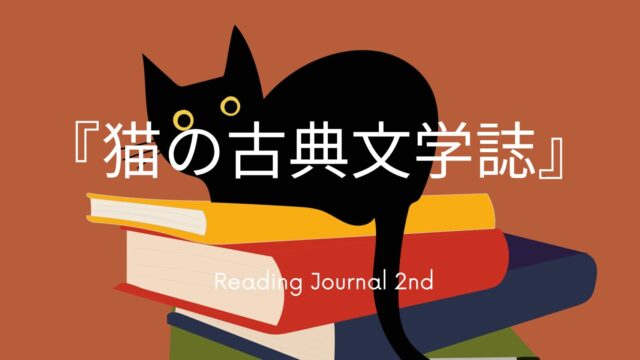 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd