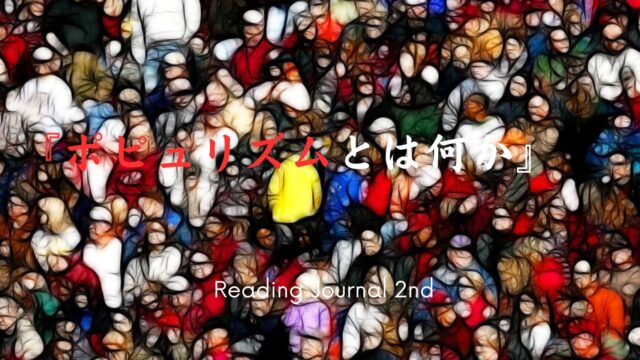 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd ポピュリストが語ること(その2)
ヤン=ヴェルナー・ミュラー『ポピュリズムとは何か』より
ポピュリズムを理解の共通のアプローチ、「投票者の感覚に焦点を当てた社会心理学的視座」「特定の階級に着目する社会学的分析」「政策提案の質の評価」などは、どれもその概念化に有効ではない。ここでは、その理由について議論される。:『ポピュリズムとは何か』より
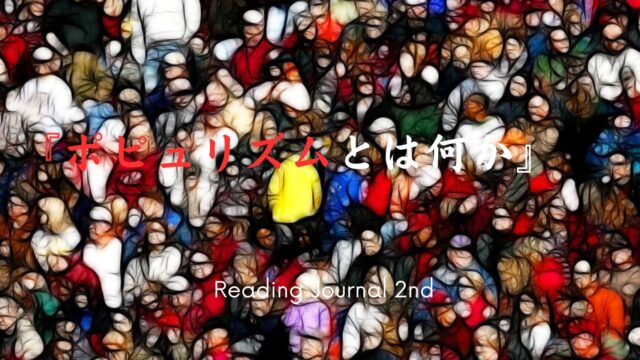 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 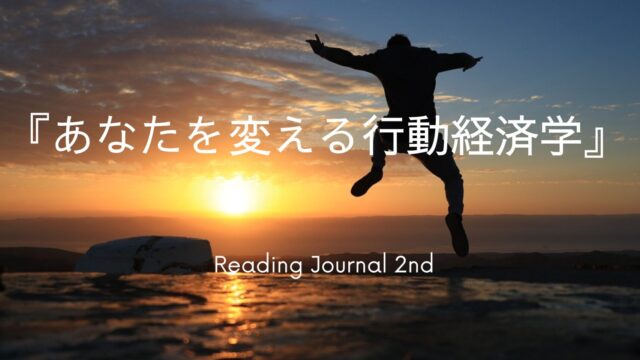 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 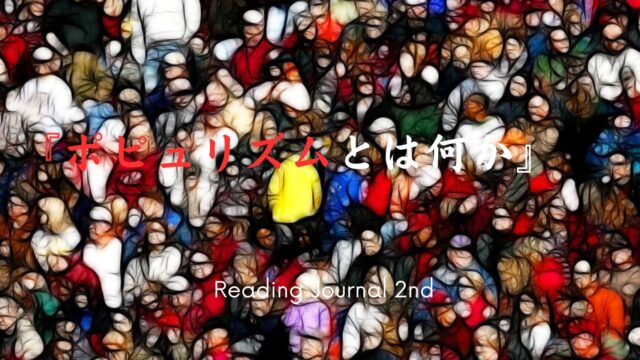 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 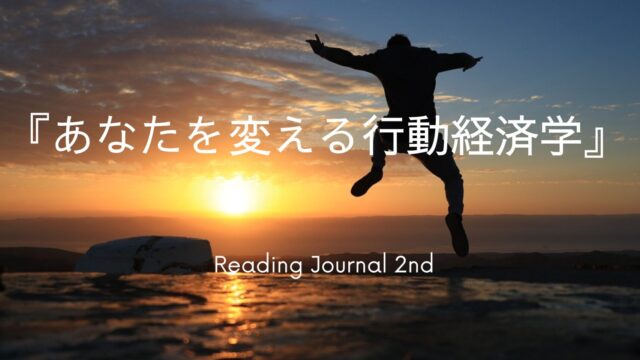 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd