『人を助けるとはどういうことか』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
⑦ チームワークの本質とは?(前半)
今日から「⑦ チームワークの本質とは?」に入る。ここでは、今までと違い、チームワークとチーム・ビルディングの話となる。著者はアメリカン・フットボールと外科チームという二つの事例を用いて、機能するチームはどのようなものかについて説明する。
この「⑦ チームワークの本質とは?」は、”前半“と”後半“の2回に分けてまとめていくことにする。それでは読み始めよう!
チームワーク、チーム・ビルディングの課題
チームワークとチーム・ビルディングは組織のパフォーマンスとして重要だが、その本質はまだまだ明確でない。
しかし、「組織の全メンバーが、そのグループが達成しようとすることに関連した何らかの役割を果たすこと」は、はっきりしている。そのためには、自分が与えるものが、何かを得るという形で埋め合わせされていると感じる必要がある。メンバー全員が同じ地位にあるわけではないが、どのメンバーも、自分が貢献したものと釣り合いがとれた地位に就かねばならない。
こうした観点からすると、成果をあげるチームとは、各メンバーが自分の役割を適切に果たすことによって、ほかのメンバーを助けているチームだと定義できるだろう。・・・中略・・・・つまり、チームワークの本質とは、すべてのメンバーにおける相互の支援を発達させ、持続させるということだ。(抜粋)
ここで著者は、アメリカン・フットボールと外科チームの事例をあげて具体的な説明をする。そして、次のような指摘をしている。
ここで大事な教訓は、グループのより高い地位にある人間が、他人の言葉に積極的に耳を傾けることによって謙虚な姿勢を見せるチームは、ほとんどの場合、うまくいくという点だ。傾聴は、よい結果を出すには他者が重要だという認識を伝え、皆がグループの中で公正・公平だと感じられるアイデンティティや役割を育む心理空間を作り出す。(抜粋)
チーム・ビルディングの初期で解決すること
著者は、「チームワーク」を「一緒に働かねばならないグループの全メンバーを含めた、相互に多様な支援関係状態」と定義する。そのため、チーム・ビルディングは、メンバー全員における人間関係を作ることになる。
この関係を築くためには、時間をかけ資源を提供することが必要である。チームリーダーは、初めのうちはプロセス・コンサルタントの機能をする必要があり、メンバーに次の四つの問題について安心感を得られるようにしなければならない。
- 私はどんな人間になればいいのか。このグループでの私の役割は何か
- このグループで、私はどのくらいコントロール、あるいは影響を及ぼすことになるのか
- このグループで、私は自分の目標、あるいは要求を果たすことができるか
- このグループで、人々はどれくらい親しくなるだろうか
誰もがさまざまな能力があるため、自分の役割が何かということがわかるまで緊張や不安を感じる(①)。そしてメンバーを選ぶときは、各自がチームで働く能力、人の役に立とうとする性質に寄ることが必要である。逆にメンバーが取り換えが効く存在と感じるとき、そのチームは失敗する。
これを一般論と考えると、ほかのメンバーよりも低い地位で終わる結果になったとしても、取り換え可能な資源としてでなく、貢献している欠かせない人間として各自が扱われれば、地位が高められるということだ。(抜粋)
誰もがある程度の影響力を備え、ある程度の影響力を及ぼしたいと思う②。そのため、自分があまり重要でない存在と感じると、仕事への責任感が減り完璧な仕事をしようとしない。
各自がそのグループに入る理由が必要である③。成功するチームを築くには各自の欲求や目標がグループの目標にあっている必要がある。
グループのメンバーは個人的に、感情的に関わることが必要である。そのため新しいグループに入る前にそのグループの要求が過剰か不十分化を確認し検討する時間があることが必要である。訓練やチーム・ビルディングの期間がある場合は、本当に合わない場合に、グループが行動を起こす前に逃げることが出来る。
チームを育てるリーダーが心得ておかなければならないのは、ここにあげた四つの質問に満足な答えを得られるまで、メンバーはうわの空となり、不安を感じるため、実行されるべき本来の任務に心から没頭できないということだ。(抜粋)
チームは相互に受け入れられるというプロセスの期間が必要である。そして、そのような接触から、信頼や支援といった態度が生まれてくる。
初期段階のパフォーマンスの見直し
このようなテスト期間は、任務を遂行する初期段階でも継続する必要がある。それは、
- パフォーマンスそのものを分析し、何がうまくいき、何を向上させる必要があるかを知るため
- さらに役割を検証し、話し合えるようにするため
である。
この再検討のプロセスでは、グループ内の形式的な地位を最低限に抑えることが重要である。(このようなプロセスは厳密にはフィードバックと呼ばれる。これについては、後に触れる。)
成果を上げるチームの特徴
成果を上げるチームとは、メンバーが自分の役割を心得て、その役割を果たすことを快いと感じることである。そのためには自分のパフォーマンスでチームに貢献し、公式・非公式な報酬というかたちで見返りを受け取る。そしてメンバーはたがいに、チーム全体とし支援しあい、誰もがクライアントであり誰もが支援者である関係を築いている。
不測の事態の支援
このチームの支援は、「実行する実際の課題と、メンバー相互が依存する度合い」によって定義できる。ここで大切なのは、不確実性の把握、つまりチームのメンバーがどのくらい不測の事態に対処できるかである。
通常の支援は当然のものであるが、この予想外の事件に対する支援はとりわけチームから認められなければならない。このような支援が出来るような相互関係には、均衡と役割の明確さが意味を持つ。そしてハイレベルの協調は、長期にわたる訓練による相互の信頼関係が必要となる。そして、注意したい点は、そのような信頼し合う関係でもなお、敬意と品行のルールが守られなかったり、支援の要求や提供の公平さや妥当性という点で適切でない場合は、相手を怒らせるような結果となる。
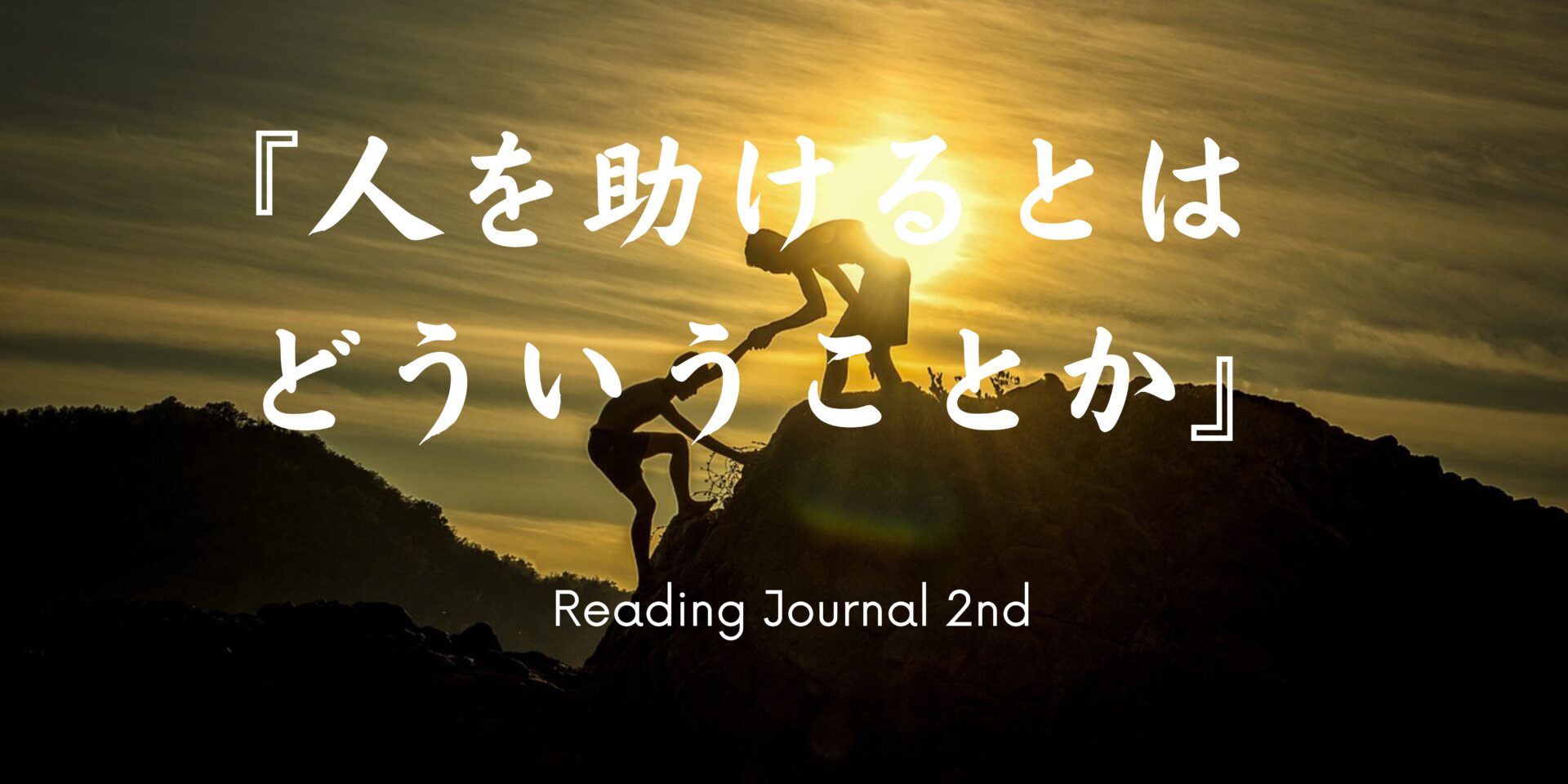
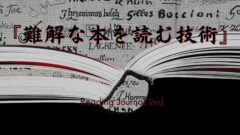

コメント