『難解な本を読む技術』 高田 明典 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第2章 準備
今日から「第2章 準備」である。「第1章 基本的な考え方」(“前半”、“後半”)において、本の型の分類、読み方の態度の違いなどを学んだ。ここからいよいよ具体的な読書についてである。今日のところは、まず読書のための準備として、「どのように読むべき本を見つけるか」について書かれている。そして、著者はこの選書は重要で、単に読書の準備という意味合いでなく、読書そのものに含まれる営みと考えている。それでは読み始めよう。
選書(本の選択)の意義
読書の技術の最初の段階は、本を選ぶことです。(抜粋)
この選択を間違え、悪い本を選んでしまうと、そこから得られるものが無いだけでなく、有害ですらある。
選書で大切なことは、「自分にとって最も好ましい本」を選ぶということである。またその本を「自分自身で」選ばなければならない。
「棚見」の技術
ある分野の知識を得ようとした時に、最初に行うべきことは「棚見」、つまり「書店の棚を見ること」である。出来るだけ大きな書店に行き、その分野の棚に並ぶ本を、まずはタイトルだけ眺めるつもりで、横から見る。少し気になった本があったら目次をみたりしながら漫然と眺めてゆく。これにより、頭のなかに「知識の容器」を作ることが目的である。
ここでいう「弁当箱」のような知識の入れ物を作らずに、本を読み始め知識を得ようとするのは、とても無謀であり、また、非効率的な作業となる可能性があります。自分が知りたいと考えているものが、どの分野の範疇に含まれているものかなのかを予め知っておけば、無駄な本を読まなくてもすみます。(抜粋)
この「棚見」は
- ①ある分野の棚を、横から順に眺めていく
- ②になるものがあれば、手にとり、目次を眺める
- ③さらに気になるものがあれば、パラパラとページをめくり、本文を眺めてもよい
- ④いったん全部のタイトルを見たら、もう一度最初からタイトルを見直していく
を何度か繰り返す。
このようにして「なんとなく、その分野の全体像が見えてくる」瞬間を待つ。これは、全体像見え、その分野が主として持っている「問題」が認識でき、その問題を解決する細分化された下位分野の構成図がなんとなくわかるということである。そして次の段階へ移る。
- ⑤その分野の全体像を、簡単にスケッチする
このスケッチは、その分野の構成図を書くという程度の意味で、自分の知り得た範囲で書けばよい。
スケッチから関心「分野」へ
そしてそのスケッチをもとに、さらに細分化して下位分野の内、自分が最も興味があるものに印をつけておく。それが購入する本のより明確な「分野」となる。
ここで重要な事として、著者が指摘するのは、この「分野」は、高度に専門的な分野であっても構わないということである。いきなり高度な本を読むのは難しそうだと考えて入門書などを手に取るのは、決して良い判断ではないと指摘する。
「自分が知りたいこと」が講義されている本を、最初から購入すべきです。・・・・(中略)・・・・自分の興味の対象から離れてはなりません。まず「知りたいこと」が書かれている本から読み始めるのが最も効率的な方法です。(抜粋)
もし読み始めた段階でわからない概念や用語に遭遇したら、その時入門書や概説書を買って読めばよい。
「必要になったときに、必要な知識を習得する」というのが最も効率的な方法です。(抜粋)
ネット検索のやり方
ここで著者は、棚見は書店に行くことが基本としながら、インターネットでの検索の方法についてふれている。
インターネット検索の問題点は、効率が悪いということである。またネットには余計な情報が氾濫しているためそれに翻弄されて、知りたい情報になかなかたどり着けないという問題もある。
ネット検索の方法は様々ですが、まずは分野にあたりをつけて、Googleなどで検索ところから始めるのが一般的です。適当な書名や人名に遭遇したら、今度は、それを検索語として検索します。Wikipediaは役にたつ項目などが検索結果の上位に来るので、そこを軽く眺めます。・・・・中略・・・・Amazon.comのサイトが上位の検索結果として表示されたら、とりあえず見てみましょう。Amazon.comの書籍レビューは、こと名著と呼ばれるものに関しては、とても役に立つ場合が多いと言えます。特に「ベストレビューアー」によるレビューは、さすがに参考になります。(抜粋)
本のタイプを決める
これまでで、読みたい本の方向性が決まってきたら、自分が読む本のタイプを選ぶとよい。
「外部参照」が必要な本と必要でない本
「外部参照」が必要な本と必要でない本のどちらを選ぶかは好みの問題である。外部参照が必要でない本は、それ一冊で完結し他の知識や参考書が必要でない本であるが、読む作業に集中力を必要とし、忍耐力が必要である。
「閉じている本」と「開いている本」
これもどちらを選ぶかは、好みの問題だが、「開いている本」は、読者自身が前向きに思考を展開して、考えを構築する必要があるため、難しい場合が多い。
購入する本を決める
ここでやっと購入する本を決める段階に入る。購入する本で重要な事は「自分にとってベスト」であることである。「自分にとってベスト」とは、「自分の理解しうる範囲の上限を少し超えたところに位置している本であり、かつ、その分野の中で名著とされている本」という意味である。そのためにまず名著のリストを作り、次に自分の理解できる範囲に線を引く。そして、その線の範囲から一つ上にある本を選ぶようにするとよい。
名著のリストの作成は、名著の意味の曖昧さもあって難しいが、しかし、得られた情報をもとに自分で判断することが重要である。また、自分の理解できる範囲の判断は、最初の部分を少し読んでみて「これならなんとか読めそうだ」と判断することになる。
読む態度を決める
購入する本を選ぶ際には、「同化読み」をするか「批判読み」をするかをある程度決めておくことも必要である。本書では、基本的に「同化読み」を取り扱うが、評価が固まっていない本、最近出版された本を選ぶ場合には、「批判読み」で入ることも重要である。
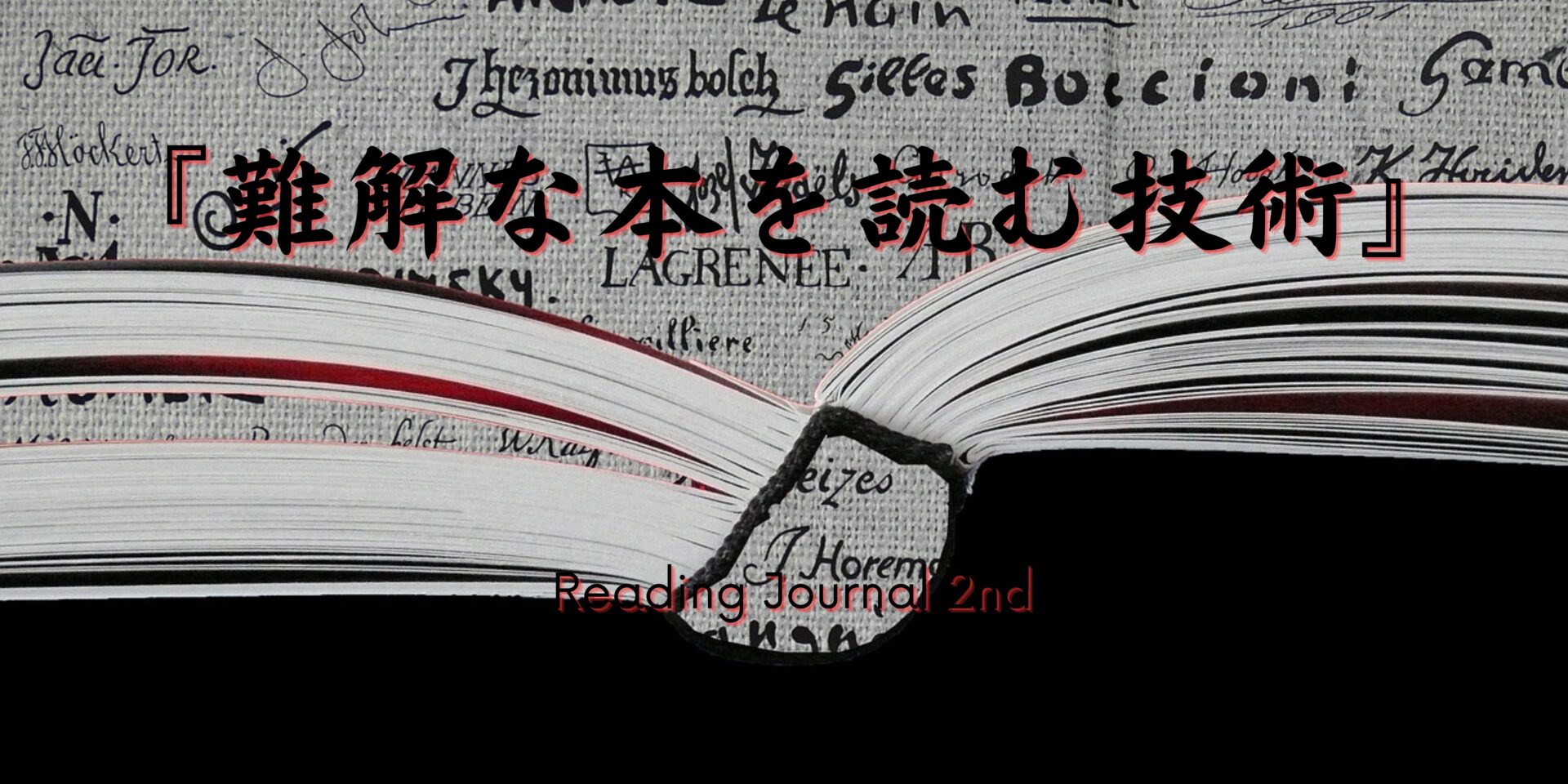


コメント