『故事成句でたどる楽しい中国史』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第二章 「呉越同舟」 — 乱世の生きざま 2 孔子の登場
今日のところは、「第二章 呉越同舟」「2 孔子の登場」ある。春秋時代の後半は乱世であった。そのころ魯の国に大思想家・孔子が誕生した。ここでは、孔子の生涯がその逸話と共に紹介されている。さらに同時期に現れた思想家の墨子についても紹介される。それでは、読み始めよう。それでは読み始めよう。
孔子の出現
春秋時代も後期となると、大国・小国を問わず下剋上の風潮が強まった。この険悪な時代、大国の斉に晏嬰、小国の鄭に子産という賢人宰相が現れる。
そのような時代に、魯の国に大思想家・孔子が生れる。孔子が生れたころの魯は、下剋上の嵐が吹き荒れ、君主も三桓と称される人たちが実権を握りあってない状態だった。そして、孔子は貧しい生まれであるが、学問に励む少年時代をおくる。
ここで著者は、孔子が自分の人生を振り返って述懐した言葉を引用する。
吾れ十有五にして学に志し、三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順う。七十にして心の欲する所に従って、矩を踰えず。(抜粋)
これが元になり、十五歳を「志学」、三十歳を「而立」、四十歳を「不惑」、五十歳を「知名」、六十歳を「耳順」という表現が生れた。
「累累として葬家の狗の若し」孔子の生涯
孔子は学者であるだけでなく、同時代の大政治家である鄭の子産や斉の晏嬰を評価し自身も社会や政治に関与したいと望んだ。そして五十三歳になった孔子は、三桓の専横に悩まされていた魯の定公に抜擢される。孔子は、三桓に対抗し獅子奮迅の活躍をするが、あえなく失脚し、魯を去ることになる。
以来、孔子は十四年にわたり、「仁(思いやり)」と「礼(道徳習慣)」を基礎とする社会をめざす、みずからの政治理念を理解してくれる君主を求めて諸国を遊説しました。(抜粋)
しかし、下剋上の世に彼の理想に耳を傾ける君主はいなかった。そのありさまは、
「累累として葬家の狗の若し(ぐったり疲れて宿無しの犬のようだ)」(抜粋)
のようだった。
孔子は十四年間の諸国の旅を終え、六十八歳になってから魯に帰国した。それ以降、七十三歳でこの世を去るまで、弟子の教育と『詩経』『書経』などの編纂に専念した。
「剛毅木訥、仁に近し」孔子の弟子
孔子には七十二人(七十七人ともいう)の高弟がいた。その中で、顔回と子路は特にお気に入りだった。
孔子は顔回については、
「先生(孔子)は、言われました。顔回は賢明だ。竹のわりご一杯のごはんに、ひさごの椀一杯の飲み物、狭い路地裏に住む貧乏生活をしている。ふつうの人はその苦しさに耐えられないが、顔回はその暮らしを楽しみ、改めようとしない。顔回は本当に賢明だ」(抜粋)
と言っている。また、顔回が若死にしたとき孔子は、
「天、予をと喪せり」(抜粋)
と嘆いた。
子路に関しては、孔子は次のように言っている。
「先生が言われた。私の理想とする道は行われない。いっそ桴に乗って海を渡ろうか。そうなったら、私についてくるのは由(子路)かな。これを聞いた子路が喜ぶと、先生は言われた。子路よ。おまえは私以上に勇敢なことが好きだが、しかし、いったいどこから桴をつくる材木をとって来るかね」(抜粋)
孔子は、十四年の放浪生活も厭わぬ偉丈夫である。そんな孔子は、「暴虎馮河」(素手で虎に立ち向かい、大河を歩いてわたること)」的な子路を可愛がった。
孔子は、虚飾の多い人柄や生き方をきらい、あるいは「巧言令色、鮮し仁(飾りすぎた言葉、とりつくろった表情、そういうものを操る人間には仁〔真の思いやり〕が少ない)」と言い、またあるいは「剛毅木訥、仁に近し」と言っている。(抜粋)
墨子の思想
孔子が亡くなったころ、もう一人の思想家墨子が生れた。彼は儒家の思想に違和感を持ち、「兼愛」「尚賢」「非攻」を中心とした独自の思想を作った。
「兼愛(博愛)」は、人間一般に無差別に注ぐ愛であり、これは家族から出発し、これを大きくし他者に広げるという、儒家の思想への批判である(儒家の思想を「別愛(差別的な愛)」と批判)。
「尚賢」は、出身階層にかかわらず、賢明な人間、能力のある人間を尊重すべきというもの。
「非攻」は、戦争をしないというもの。彼は言論をもって反対するだけでなく、大勢の弟子と共に大国の攻撃を防御した。この墨子の鉄壁な防御技術を「墨守(墨子の守り)」という。
墨子は儒家と激しい論争をするが、結局儒家に駆逐されてしまった。
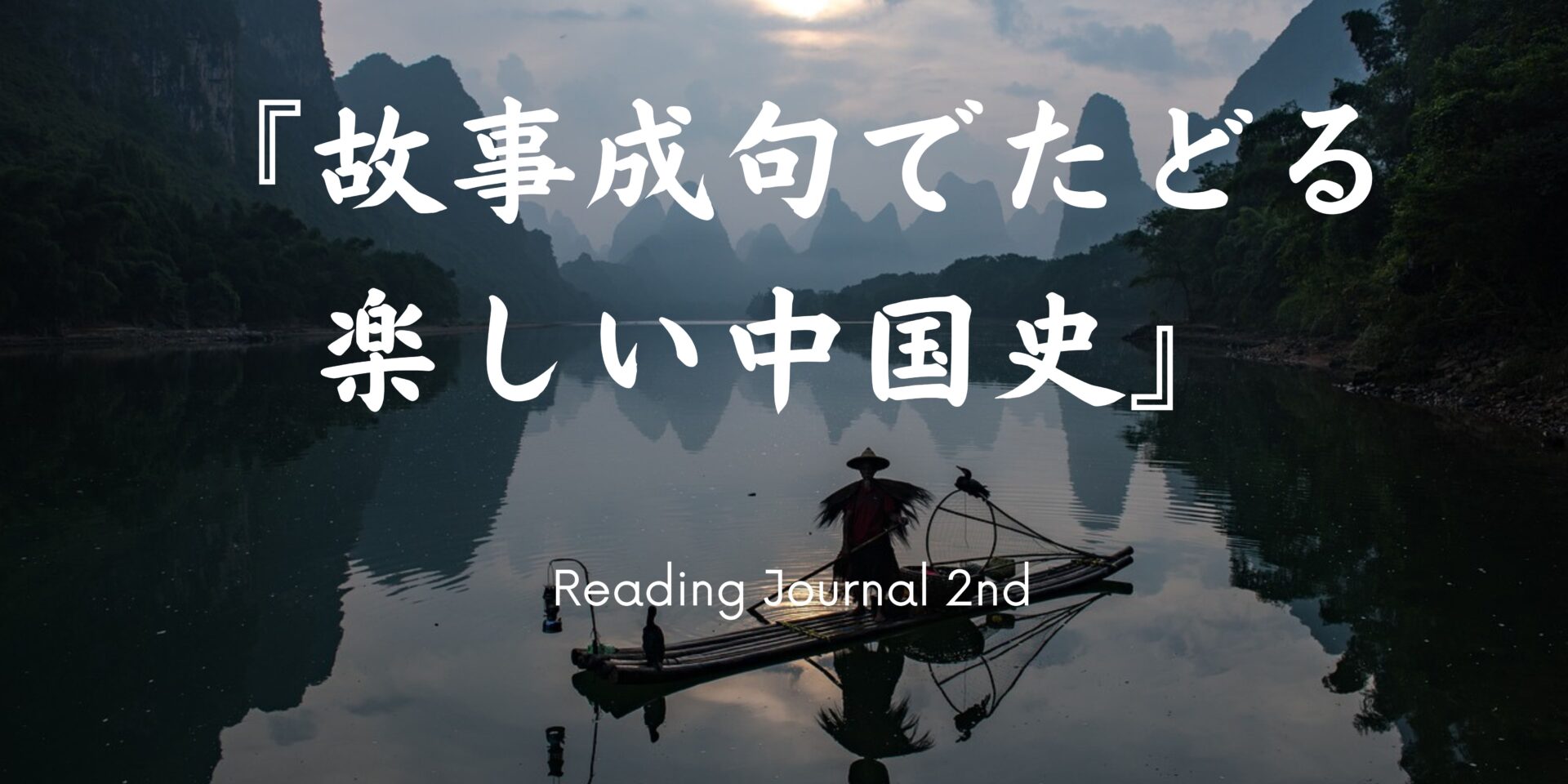


コメント