『難解な本を読む技術』高田 明典、光文社(光文社新書)、2009年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
はじめに
ただ今、現在進行形で『ポピュリズムとは何か』という本を読んでいるんですが・・・・・難しい。今やっている方法、つまり「重要と思える箇所に付せんを貼って、その付せんを頼りにブログにまとめる!」というやり方で何とか読んでいました。でも、「第二章 ポピュリストがすること、あるいは政権を握ったポピュリズム」の最終盤「人民は「われら人民」といえないのか?」の節に入ると・・・・冒頭から全く分からない。
(そらそうだわ、ある意味、学術的な専門書だし、何と言っても・・・基礎知識がなさすぎる)
これは困った。そこでパラグラフごとにノートに意味を「ぐちゃぐちゃ」書きこんで読むという作戦に変えました。(そして現在は、ゆっくりとなんとか読んでいる・・遅々として進まないが。)
そう思うと、ちょっと前に難しい本を読むって本を読んだよなぁ~と思い。本棚からこの本『難解な本を読む技術』を取り出しました。この本は、難解な哲学の本を研究者による、読書の技術に特化した本である。一度、読んではいるのだが、再度、読んでみようと思った。
今日のところは、「はじめに」である。ここでは、この本の狙いと各章の概要が書かれている。
まず、著者は「「本」というものが最も安価で効率的に知識を習得できる優れた道具である」、というところから話を始める。もちろん実体験に勝る教師はいないと認めるが、でも価格という面で考えると本は安いという。そして、
実体験に比べれば読書は圧倒的に安価ですが、読書というのは決して「情報を受け取る」という受動的な営みなのではなく。そこに表現されている知識や思想を、自分の内部に取り込むという能動的な営みなのです。すなわち、読書という能動的な営みによって、私たちは知識や思想を自分のものとすることができます。(抜粋)
そして、この「能動的営み」には技術が存在し、この本はその「読書の技術」について書かれている。また、この本では「本を読む」という営みを、ただ文字を追っていく営みでなく「わかる」ことを目的とした行動であるとしている。そして、この本の狙いを次の方に言っている。
この本では、特に「難解」とされる本に関して、それを読んで理解するために必要となる技術について説明しています。(抜粋)
この本の構成は、
- 第1章、第2章:読書という技術の基本的要素を解説
- 第3章、第4章:「読書ノート」の取り方
- 第5章:読書後の知識の維持管理の方法、さらに進んだ読書について
- 付録1:実際の読書ノートの例
- 付録2:代表的な難解本と呼ばれる10冊についてそれを読み進めるための技術
となっている。
そして最後に
この本で説明している技術には、まだまだたくさんの改良の余地があると考えています。多くの人が、「読書の技術」の存在を認識して、ここでの技術を改良したり、もしくは、まったく別の新しい技術を開発したりすることが増えれば、本の世界や読書の世界の景色は、ずいぶんと変わるのではないかと考えています。この本が、そのような有機的営みの一助となれば幸いです。(抜粋)
と言って「はじめに」を結んでいる。
なるほどなるほど、まずは読書ノートの取り方を学ばないとね♬。それからそれから、やっぱり本書の技術を発展させて、「つくジー流」を興さないとね!(つくジー)
関連図書:ヤン=ヴェルナー・ミュラー (著)『ポピュリズムとは何か』、岩波書店、2017年
目次
はじめに [第1回]
第1章 基本的な考え方 [第2回][第3回]
第2章 準備 [第4回]
第3章 本読みの方法(1) 一度目:通読 [第5回][第6回]
第4章 本読みの方法(2) 二度目:詳細読み [第7回][第8回]
第5章 さらに高度な本読み [第9回][第10回][第11回][第12回]
付録1 読書ノートの記入例 [第13回前半]
付録2 代表的難解本ガイド [第13回後半]
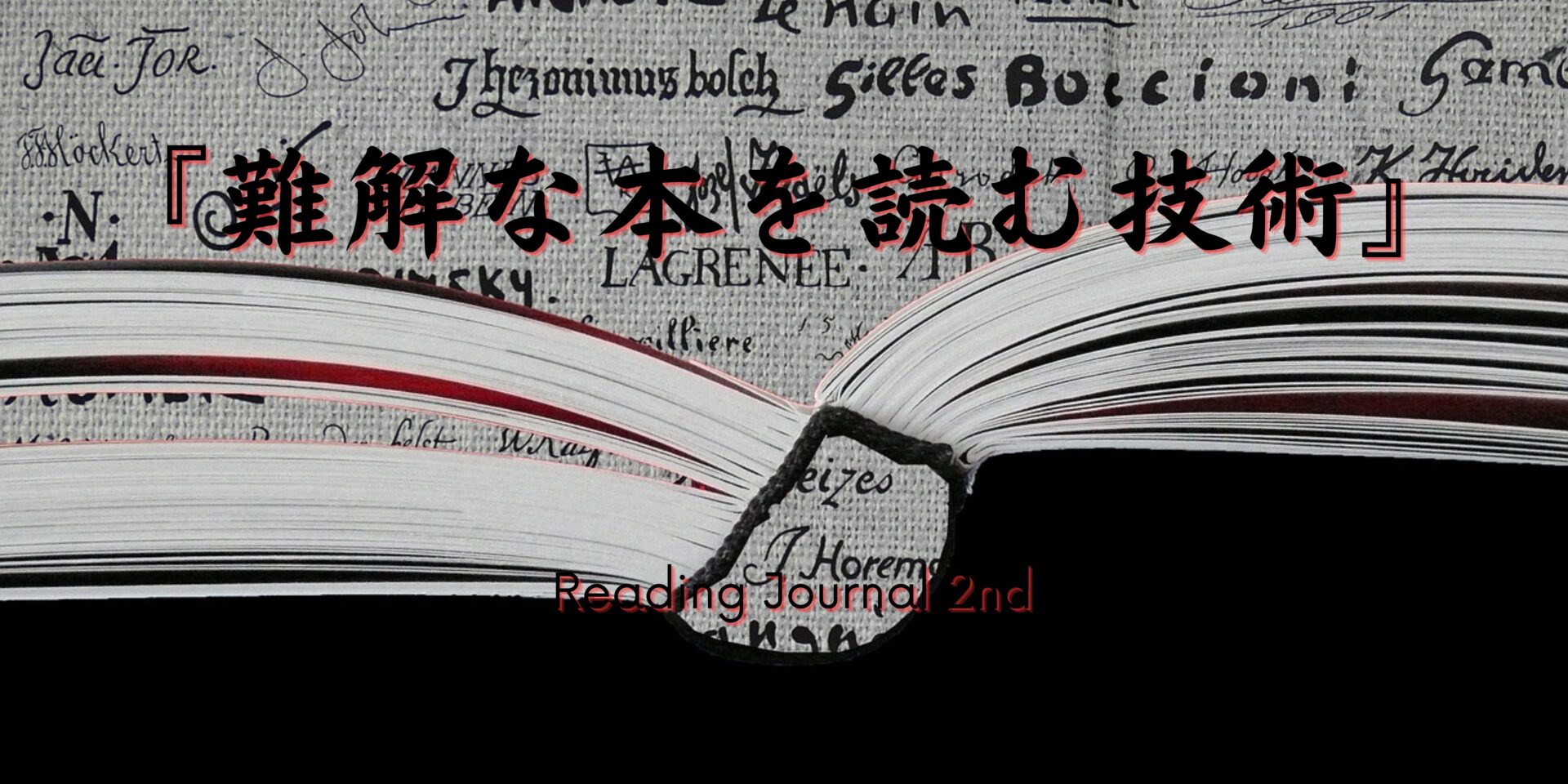


コメント