『人を助けるとはどういうことか』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
② 経済と演劇 人間関係における究極のルール(後半)
今日のところは、「② 経済と演劇」の”後半である。著者は、人間関係を「経済」と「演劇」にたとえて、その仕組みについて考察している。まず”前半”において、人間か関係の「社会経済的ルール」について説明された。それを受けて”後半“では、人間関係の「演劇」的な要素についての説明がある。それでは、読み始めよう。
人間関係の演劇的要素
ここまでも述べたような社会経済は、人生という劇場を反映している。劇場と呼ぶ理由は、状況そのものが、その場にふさわしい役割を担う俳優や観客の感じ方によって、定義されるからだ。(抜粋)
人生の役割関係は早い時期より学習され、人は日々のプロセスで適切な行動を演じる。演じ方は日々の社交の中で俳優と観客の両方の役割をどう適切に演じるかについて学んだことを反映している。
役割として最も重要な「親子関係」をはじめ、「部下になる方法」「権威や権力なしでものごとをやり遂げる方法」「人間関係が公平だと感じられるよう、権力を備えた人に必要なものを与える方法」などを、人生の早い時期から生涯にわたって学び続ける。
われわれには常に自分より上位の者が存在する。社会学者のアーヴィング・ゴッフマンが「敬意と品行」というルールとして表現した、子供や部下として適切に敬意を表す方法、親や上司として目下の者の敬意を勝ち取り、それを維持する方法なども学ぶ。
人間関係の間でふるまいにも多くのルールがあり、どのような態度が適切かについては、子供は大幅な自由があるが、親や上司はもっと制約を受け、社会の上位に行くほどこの制約は強くなる。『幸福になる関係、壊れてゆく関係 — 最良の人間関係をつくる心理学 交流分析より』のなかでハリスは、人は大人になるまでに「子供」か「大人」あるいは「親」として状況に直面することを選ぶ、と指摘している。
こうした人間関係の均衡があらかじめ保たれるとすれば、支援 --- 真の意味でよく考えられた支援 --- は、大人対大人の行為であるのが最適ではないかと思われる。(抜粋)
支援者が親らしい行動をとれば、クライアントは保護されていると感じるが、支援者が子どもの役割を演じると、クライアントは混乱してしまう。
与えられた状況で自分が演じる傾向のある役割について、特に依存関係では、個性が関係してくる。依存心の強い人と依存に否定的な人では、どのような状況が公平であるか変わってくる。重要なことは自分を知ることである。また、ルールをどのように適用するかについては、特定の状況で与えられた関係という社会的機能によって異なる。
相手がセールスパーソンや店員の場合は、その関係は形式的で非個人的なものである。そこに親密さは期待されない。しかし、クライアントがより個人的で具体的な支援を求めた場合、弁護士や医者、証券アナリスト、牧師、セラピストの場合は、状況は複雑である。最初はその関係は形式的であるが、しかしこのような専門知識をもった支援者にたよる場合、クライアントは弱体化する。このような場合支援者は、権力を持ちクライアントを食い物にし、利用できる。そのため、このようなカテゴリーの支援者はより広範囲にわたる訓練を受け、専門的な基準や倫理観を遵守しなければならない。
社会経済的ルールと演劇との関連性のまとめ
社会をうまく機能させるためには、非公式な支援が必要である。面目を保つというルール、敬意と品行のルールなどは、あらゆる人間関係に必要である。
どんな種類にせよ、関係を築くためには、社会経済や面目保持という文化的なルールに敏感であることが求められる。人がそれぞれの関係から自分に見合った何かを得ていると確信できるとように。人生という日々のドラマの中で、人は自分の面目や他人の面目がつぶれないように役を演じている。成長するにつれて、われわれは無数の状況への対処法を学ぶ。どの状況も、役者や観客の役割を適切に果すことを求めている。(抜粋)
良い支援者になるためには、このような社会経済学と、社会という劇場を意識することである。それにより支援者の役割がわかり、人間関係を公平で適正なものとする交換手段や価値観がわかるようになる。
さらに、誰もが支援そのものが社会的通貨であり、それが適切に対応されなければ不均衡が起こるということを心得ておかなければならない。
いつ、どのように支援を与えるか、他人からの支援をいつ、どのように受けとるかを知っていると、人間関係はさらに生産的で喜ばしいものになるだろう。(抜粋)
関連図書:トーマス・A. ハリス(著)『幸福になる関係、壊れてゆく関係 — 最良の人間関係をつくる心理学 交流分析より』、同文書院、1999年
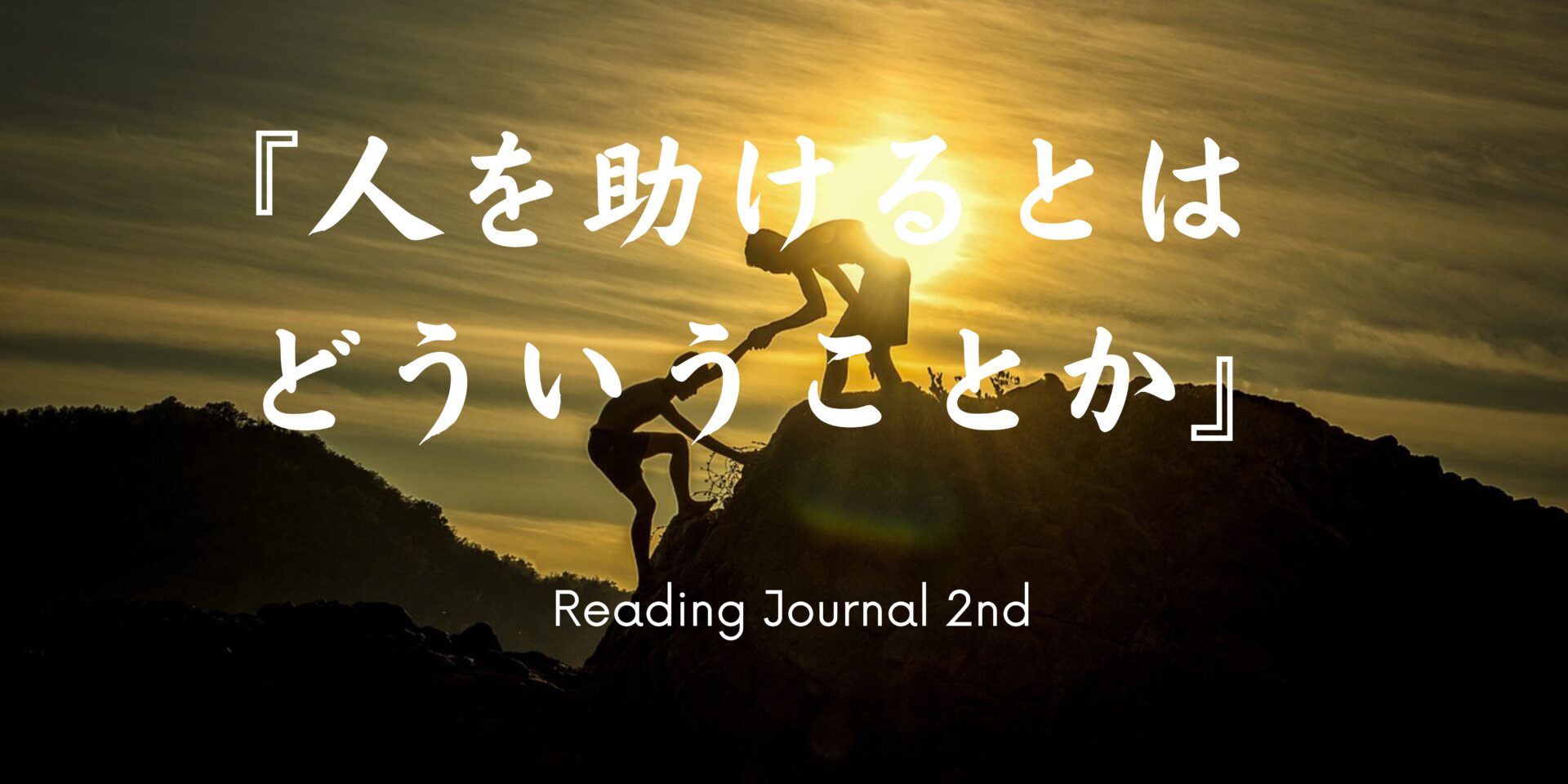

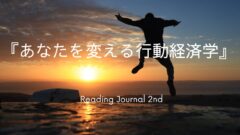
コメント