『「モディ化」するインド』湊 一樹 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
エピローグ
今日のところは、最終章の「エピローグ」である。ここでは、本書の全体を俯瞰してのまとめが書かれている。さて、読み始めよう。
モディ政権下での変化
モディ政権の一〇年でインドは大きく変わった。(抜粋)
著者は、このように語りはじめる。
まず、人口は中国を追い越し世界一となった。経済成長も一時期より落ちているが、経済規模は拡大をつづけ、米中につづく第三位の経済大国になることが現実味を帯びてきた。そして中国の脅威とグローバルサウスの台頭を背景に国際社会での存在感も急速に高めている。
しかし、著者はこれらの変化は、ここ四半世紀の間の一貫的な流れてあり、モディ首相がインドを率いていなくても同じ変化は起こっただろうと指摘している。そしてさらにモディ政権下において、これらの根拠は、それほど確固たるものではなく多分に誇張されていると指摘している。
ここで著者は次のように、インドにおける最大の問題を指摘している。
モディ政権下で起きた最も大きな変化は、メディアがインドについて盛んに取り上げる、人口増加、経済成長、国際的な存在感の上昇といった側面ではない。そうではなく、インドという国のあり方そのものが、この一〇年で大きく変質したことである。「世界最大の民主主義国」と呼ばれてきたインドが、民主主義の後退を経て権威主義化の道を足早に歩んでいるのは、まさにその表れである。(抜粋)
インドではこれまでも民主主義の規範からの逸脱が多々あったが、それが逸脱という言葉で片づけられないほど悪化している。著者はその例としてインド人民党(BJP)政権下の州では、法的根拠無しにイスラーム教徒の家や商店をブルドーザーで破壊することが繰り返されていることをあげている。
民主主義の後退と選挙至上主義
このようにモディ政権は非民主主義的である。民主主義の規範にも憲法の理念にも反する立法が可能となっている。そして、司法府やメディアの積極的、消極的協力もあり、それが問題になっていない。
このような状況に至った原因は、二度の総選挙及び重要な選挙でモディ首相率いるBJPが勝利を収め「モディ政治が国民から支持されている」という錦の御旗があったからである。そのため、ヒンドゥー至上主義の理想の実現と非民主主義的な行為の正当化には、あらゆる手段をつかって選挙に勝たなければならない。
そのため、モディ政治には、ヒンドゥー至上主義に加えて選挙至上主義という特徴がある。(抜粋)
そして著者は、来たる二〇二四年の総選挙について、次のように言及している。
二〇二四年前半に予定される総選挙に向けて、政府・与党は「モディ化」と大国幻想をより強固なものにしようとすることは間違いない。…中略・・・総選挙での勝利を確かなものにするために、モディ政権は民主主義の規範に反する手段はもちろんのこと、違法な手段も含めたあらゆる手段に訴えるだろう。そして誰もが予想しないような一手をつぎつぎと打ち、その「歴史的」な決定の「意義」と「成果」を派手に演出するだろう。
「カリスマ」には、つねに「奇跡」が必要なのである。(抜粋)
日本とインドの関係について
日本は、インド系移民が圧倒的に少ないこと、他国の民主主義や人権をめぐる状況に概して無関心なこと、などがありインドでの権威主義化、宗教的少数の迫害が政治的な争点となることはない。
しかし、日印両国が経済や外交・安全保障の分野で関係を深めている以上、インドの実情を正しく理解しておくことは重要である。(抜粋)
しかし、現在の日本では、インドが着実に権威主義化していることはあまり認識されていない。現在の日本人はインドを中国というレンズを通して「民主主義国・インド」として見ている。
これらは、日本が中国を意識し「普遍的な価値の共有」を強調しつづけたこと、「グローバルサウス」を宣伝したインドにメディアが呼応したこと、さらに、日本のメディアでは、インドの位置づけが低いため取り上げられる機会が少ないこと、が原因として挙げられる。
また、自身の認識や願望に沿った報道ばかりに触れてしまうという、ニュースの受けての私たちの姿勢にも問題がある。
そして著者は、つぎのように「エピローグ」を閉じている。
「インドを知るには、インドという対象そのものを見なければいけない」と言えば、あまりにも当たり前に聞こえるかもしれない。しかし、インドについての現実離れしたイメージが大手を振ってまかり通る現状を考えると、実は当たり前とも言い切れない。(抜粋)
二〇二四年の選挙であるが、終わってみるとモディ首相は政権を維持したもののインド人民党は議席を減らし、大勝利とはならなかった。そして、この選挙のころから、本書で取り扱われているモディ政権の負の部分の報道が日本でもなされるようになったと思う。
モディ首相が政権を保ったものの、思ったような勝利とならなかったのは、インドの民主主義がまだ何とか機能しているということだろうか?日本としてもこれからも注意深く見ていく必要があるように感じました・・・よ。(つくジー)
あとがき
やっと「あとがき」まで到達した。「あとがき」の前半では、「逆張り」という言葉をキーワードとして、客観的な事実をもとに議論すると「逆張り」に見えてしまうのがインドの現実であると説いている。
つまり、インドは民主主義国家とはいえなくなり、「普遍的価値の共有」は実態を伴わず、「大国化するインド」「グローバルサウスの盟主」などのイメージも内容を伴わなくなっている。そして著者は
インドの国章の下部には、「真実こそが勝利する」というウパニシャッド聖典の一説が記されている。しかし、インドを取り巻く現実は、「真実こそ勝利する」からはほど遠い。それどころか、真実を語るには勇気と覚悟がますます求められるようになっている。(抜粋)
と言っている。
「あとがき」の後半では、本書が日本貿振興機構アジア経済研究において、二〇二〇~二〇二二年に行われた研究会「インドのポピュリズム —モディ政権下の『世界最大の民主主義』」の成果であるとし、さらに刊行にあたってお世話になった人への謝辞が続く。そして最後は、以下のように結んでいる。
本書が、読者のみなさまの「ものの見方」に少しでも影響を与えることができたならば、それは私にとってこのうえない喜びである。(抜粋)
[完了] 全21回
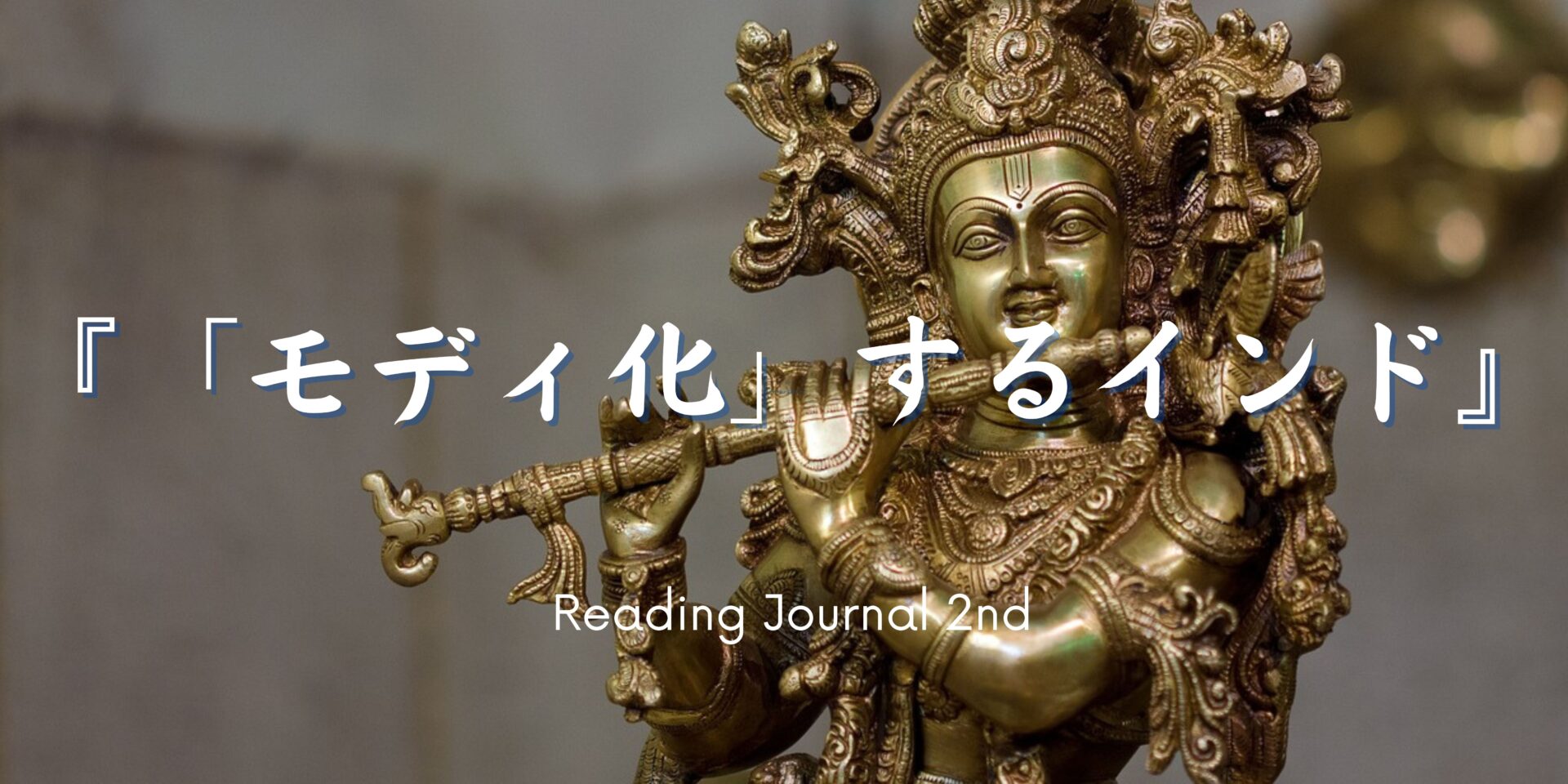


コメント