『行動経済学の使い方』大竹 文雄 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第6章 本当に働き方を変えるためのナッジ
今日のところは第6章「本当に働き方を変えるためのナッジ」である。ここでは、「シーシュポスの岩の実験」から働く意欲を高めるナッジを探り、そして、現在バイアスを回避することにより目標を達成を援助するナッジについてである。それでは、読み始めよう。
「シーシュポスの岩」の実験と仕事へ意欲
「シーシュポスの岩」というギリシャ神話がある。シーシュポスは、神々を欺いた罰で、巨大な岩を山の頂上まで押し上げるように命じられる。しかし、岩が頂上にあと少しのところまで近づくと、底まで転がり落ちる。そのためシーシュポスは際限なく苦行をつづける必要がある。
また、日本には「賽の河原の石積み」という話がある。小さい子供が親に先立って死んだ場合に、賽の河原の石で仏塔を積み上げる。しかし、毎晩、鬼がその仏塔を壊してしまう、というものである。
どちらも永遠に完成しない仕事を続けていく話であるが、このように無駄とわかっている仕事がどれだけ私たちの意欲を奪ってしまうかを明らかにした実験(「シーシュポスの岩の実験」)がある。
実験では、レゴブロックでバイオニクル(レゴ社のキャラクター)を組み立てて、組み立てた個数によって賃金を支払うというものである。そして
- 「意味ある条件」・・・完成したバイオニクルを学生の前に並べる
- 「シーシュポス条件」・・・完成したバイオニクルをすぐに隣に座った担当者が壊してしまう
という条件で比べた。すると意味ある条件は明らかにシーシュポス条件の場合よりも完成した個数も賃金も上回った。
つまりバイオニクルを作ったことを時間できる条件なら努力するが、すぐに壊されてしまって仕事をしたことが実感できない状況では、やる気が出ないということだ。(抜粋)
すなわち、人々は意味のある仕事には、金銭的な価値以上の価値を見いだしている。
この実験結果は、仕事への意欲を高めるためのヒントを与える。
一つは「仕事そのものに意味があると実感できること」である。仕事から非金銭的な喜びを感じることができれば、同じ仕事であってもつらさが和らぎ労働意欲がわく。
もう一つは「仕事をしたことが実感できるということ」である。自分がした仕事はどれだけなのかを一目でわかるようにしておくことは、自分が意味のある仕事をしたと認識しやすい。そのためには自分がどれだけ仕事をしたかを毎日記録すると良い。
現在バイアスの回避と目標の達成
目標の達成と行動経済学
目標を立てたけれど、行動が伴わずに達成できないことが多い。行動経済学では、計画したが実行できない現象を現在バイアスで説明することが多い。現在バイアスが原因で、目標の達成が出来ない場合は、先延ばしすることが難しい状況に自分を追いこむことが解決策である。
計画した目標が達成できない理由として、
- 目標そのものを忘れてしまう
- 目標があっても、それを達成するために毎日何をすればいいかがはっきりしない
という理由がある。①の場合は、忘れないような仕組み、たとえばカレンダーに記入することやリマインドメールを送るなどがある。②の場合は、目標を達成するために、何をするかまでを書き出した実行計画を立てる。
この実行計画の重要性については、アメリカで失業者の職探しの行動による研究がある。その研究によると失業者に行動計画書を書いてもらった場合は、採用提示や雇用数が増え、また求職手段も多様なることがわかった。
目標達成のために、毎日何をすればいいかを明確にしておけば、私たちは、毎日の課題さえこなせば、自動的に目標を達成できる。つまり、目標を達成するためには、目標達成必要な具体的行動は何か、それをいつやるか、ということまで計画に書き込むようにすればいい。まずは、具体的な行動予定までスケジュールに書き込むことが、目標達成の第一歩である。(抜粋)
合理的な行動とその落とし穴
仕事などの評価は一日単位で決まるわけではない。そのため、毎日の仕事量を決めて、それを達成するまで働くという働き方は、非効率である。一日単位で仕事量を決めた場合は、調子のよい日は働く時間は短くなり、調子の悪い日に働く時間が長くなるからである。
そのため、一日の成果でなく長い視野をもって仕事をする方が合理的である。また、成果はすぐに出るもので無いため、短期間の指標で成果を測ると本当に大事なことが疎かになり、成果の出やすいことばかりに集中してしまう。
しかし、長期的な視野に立って合理的な計画を立てる場合、そのよう計画を実行する段階になると、計画の実行を先延ばしにしてしまうことが多い。
それなら、どんなことがあっても毎日一定の課題をこなすという非合理的なルールの方が、最善の計画を立ててそれを実行しないということよりもマシなルールになる。(抜粋)
また、毎日の行動に制約をつけることは、毎日それを達成するたびに達成感を感じることができ、課題を先延ばししにくい。そして習慣化して何も考えずに行えるようなルールに作っておくと、長期目標を達成しやすい。
長期目標を達成するためには、その目標を達成するために、その時点その時点で最適な行動をとるのがベストである。しかし、それがベストであることがわかっていても、ベストの計画を実行できないのであれば、次善の計画を立てることが必要である。
長期目標を達成できるような毎日のシンプルな行動ルールを決めて、毎日その行動を達成したことを喜びにするという工夫が、非合理的なように見えるけれども、次善の策なのかもしれない。(抜粋)
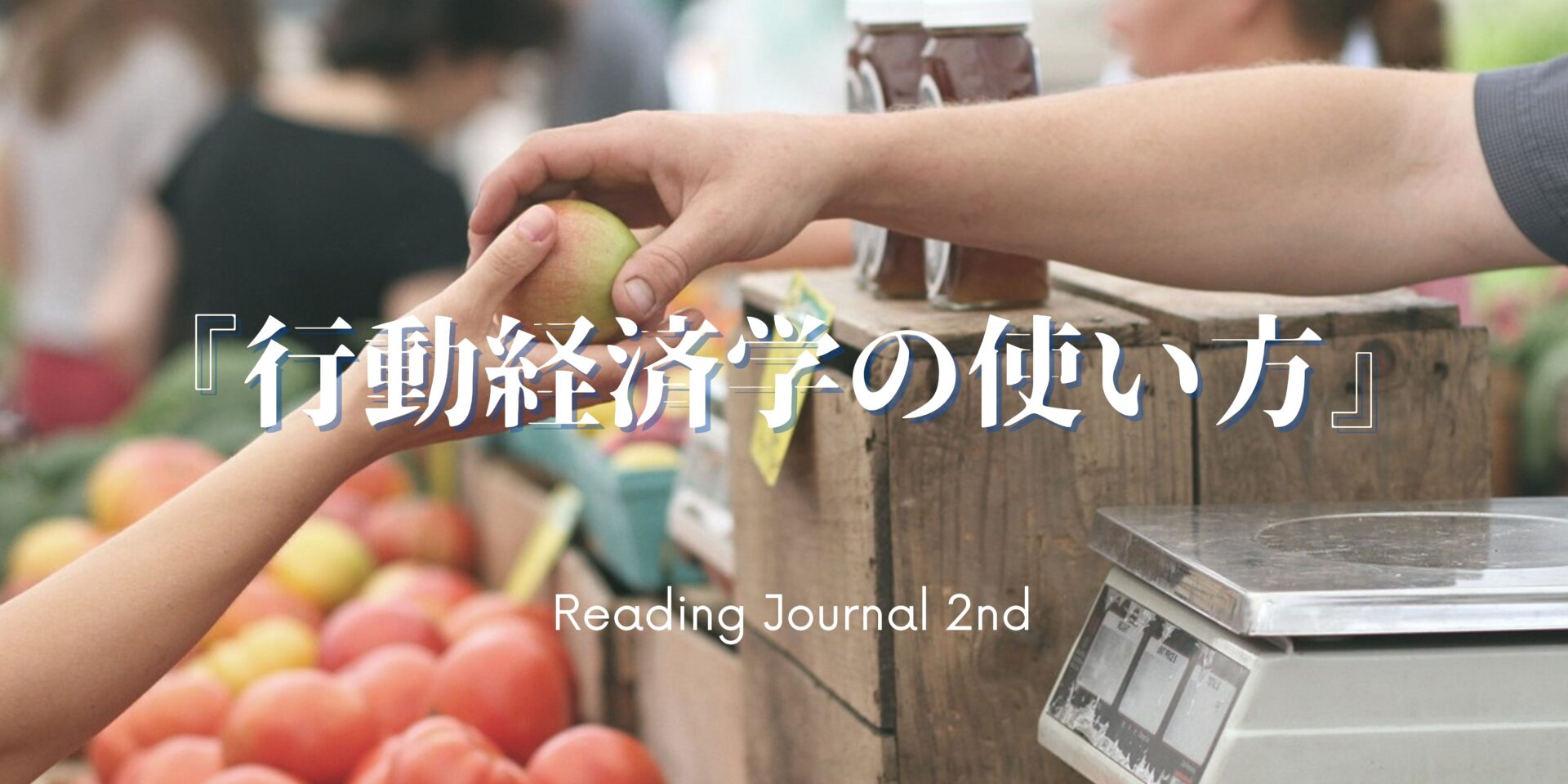


コメント