『成長を支援するということ』 リチャード・ボヤツィス 他 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
1 支援の本質
前回の「監訳者序文」につづき、ここから本編に入る。まずは「支援の本質」である。ここでは、具体的な例を通して「思いやりのコーチング」の全体像を描き出している。そして「本書のてびき」として2章以下の章の流れを紹介する。
思いやりのコーチングとは
思いやりのコーチングや支援が効果的に行われれば、支援を受ける人々に次の3つの変化をもたらす。
- 人々はパーソナルビジョンを発見、もしくは再確認し、未来像、情熱の対象、パーパス、価値観などを明確にすることができる。
- 行動、思考、感情に変化が生じそれによって理想の実現に近づいていることを実感する。
- 彼らはコーチや支援者と「共感する関係」を築き、その関係を維持するようになる。
一般的なコーチング(「誘導型コーチング」)の場合は、支援を受ける人々がやるべきことを見つけてあげるようなことを行う。しかし、そのような問題を正そうとする方法、つまり現状とあるべき姿の間のギャップに注目し、人々を修正しようとする方法は、その場しのぎの矯正にしかならず持続的な解決にならない。
しかし、長期的な夢やビジョンがありときは、そのビジョンからエネルギーを引きだし、変化のために努力を続ける。「思いやりのコーチング」はこのような状況を創り出すことを目指している。
本書では、この「思いやりのコーチング」を、従来の「誘導型のコーチング」と比較しながら論じている。
思いやりのコーチングの原理
変化を持続するためには、それが外から圧しつけられたものでなく、自分の意志であることが重要になる。そのため、思いやりのコーチングは、理想的な自分を明確にすることから始まる。このような状態のとき、頭と心は「ポジティブな感情を誘引する因子(Positive Emotional Attractor = PEA)」に結びついていて、変化をもたらす可能性や興奮に心を開くことができる。このPEAは、「ネガティブな感情を引き起こす因子(Negative Emotional Attractor = NEA)」と比較して論じられる。ただし成長のためにはPEAとNEAの両方が必要になる。本書ではPEAが転換点として働き、重要な成長プロセスを進める助けとなることを示す。そして、このような進展が「意図的変革理論(Intentional Change Theory = ICT)」により導かれる(3章)。
各章の構成
- 2章:コーチングや人と人が助けあう方法についての定義と実践について
- 3章:「誘導型コーチング」と「思いやりコーチング」を比較しながら思いやりコーチングのやり方を説明する。意識的変革理論(ICT)における5つディスカバリーについて
- 4章:受容能力やモチベーションがより高い状態を創り出すためにどのようにPEAを刺激するかについて:脳分野の研究成果から論じる
- 5章:PEAとNEAを科学的な側面から探り、PEAとNEAの適切なバランスについて説明する
- 6章:パーソナルビジョンについて追及する
- 7章:相手と共鳴する関係を築き、学びと変化を引き起こすための、適切な問いかけについて
- 8章:組織内にコーチングの文化を育てるための規範について
- 9章:「コーチングに適した瞬間」の活用法について
- 10章:締めくくりの章として2章でのエクササイズに立ち返り、支援してくれた人がいまの自分の一部になっていることを再確認する
なるほどなるほど、「思いやりのコーチング」が各自の夢や目標などを達成するために支援するってことなんだね!!でも「そんなことは当たり前じゃないか!(# ゚Д゚)」というところを、PEAやNEAといった脳科学からの知見を使って具体的に論じるってことなんだと思う(違うかもしれないが)。まぁ4章、5章まで読め!ってことですね♪(つくジー)
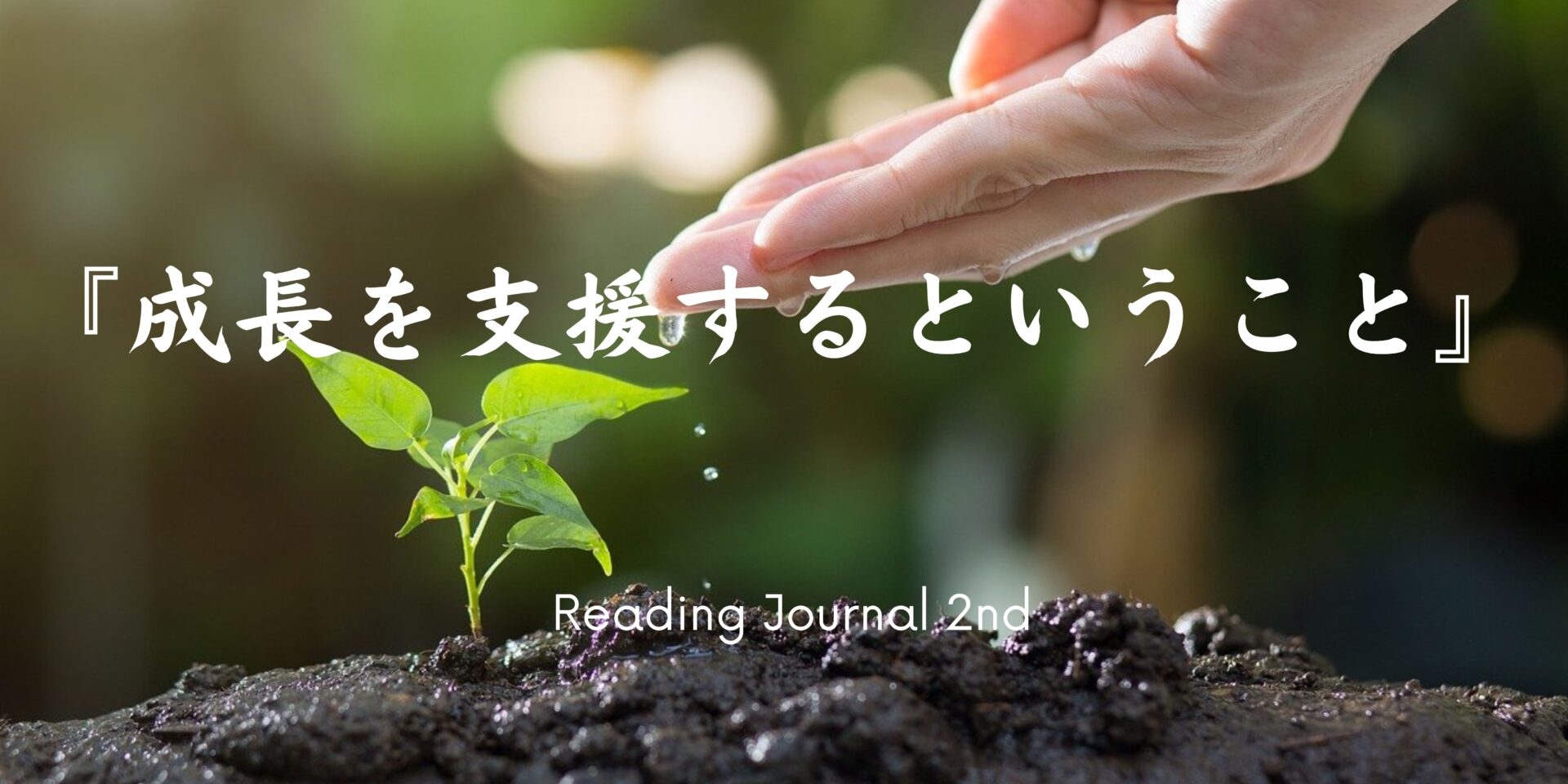


コメント