『外国語学習の科学』 白井恭弘 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第6章 効果的な外国語学習法 (後半)
今日のところは、最終章・第6章「効果的な外国語学習法」”後半“である。”前半“では、個々の学習項目の学習法について、説明された。そして”後半“では、学習ストラテジー、学習プログラムが紹介され、さらに「おわりに」で本書全体をまとめている。それは、読み始めよう。
学習ストラテジー
第二言語学研究では、一九七〇年代に「優れた学習者(good language learner)」の研究が盛んになり、そのような研究から「学習ストラテジー」(学習者が第二言語の知識を身につけるために使う方略)の分類が生まれた。
レベッカ・オックスフォードは、以下のような分類を提案した。
- 学習ストラテジー
- 直接ストラテジー(言語材料に直接かかわる)
- 記憶ストラテジー(語呂合わせ、類語など)
- 認知ストラテジー(習った項目を整理するなど)
- 補償ストラテジー(文脈から未知語を推測するなど)
- 間接ストラテジー(言語に直接かかわらない)
- メタ認知ストラテジー(学習計画、評価など)
- 情意ストラテジー(不安や緊張などを緩和する)
- 社会的ストラテジー(他人と協調するなど
- 直接ストラテジー(言語材料に直接かかわる)
このようなストラテジーは、個人の適正もあるため、自分に合ったストラテジーを使うことが大切である。
学習プログラム
次に学習プログラムとして、二つの例を紹介している。
一つ目は、著者が日本の公立学校で英語教師をしていた時の例で、「ナチュラル・アプローチ」という教授法の応用である。「文法は家庭学習にまわして、教室では理解可能なインプットをあたえる」を方針として、授業では、文法訳読をつかった精読と、内容理解中心の多読を併用、さらに再度リーダーの授業を取り入れ、大量の英文を読ませる。
二つ目は、甲田慶子が開発した日本語プログラムで、インプット=インターアクションモデル(ココ参照)の例である。授業は「その日に導入された文法項目を使った学生同士のインタビュー」を中心とする。学生はお互いにインタビューし、インタビューで得た内容をノートにメモし、宿題でクラスメートや自分について書くというものである。そして各課ごとに、よく使われる構文・表現が多数入ったダイアローグを暗記する。
このように、初級の段階から身近な内容について意味と形式の両方に注意を払って自然なコミュニケーションをしていけば、比較的短期間で、「限られた文法、単語を使って、限られた内容について」流暢なコミュニケーションができるようになります。(抜粋)
おわりに
最後の「おわりに」で本書全体のまとめが書かれている。ここでは、「おわりに」の前半を長文引用する。
本書では、外国語学習に関して科学的アプローチをとる研究を概観し、その全体像を示し、さらにそれを実際の外国語教育・学習に応用するにはどうすればよいか、ということを論じました。話題は多岐にわたるので、ここで短くまとめてみます。
まず、外国語学習の成功は、主として、学習開始年齢、適正、動機づけによって決まるので、学習開始年齢は早い方がよく、理由はどうであれ、動機づけを高めることが大事です。適性についてはあまり変えられないのですが、自分の適性にあった学習方法をとることが必要です。
そして、外国語は母語を基盤に習得されえるので、母語の知識を最大限生かし、また邪魔になる部分を最小限にすることが重要です。母語と外国語が違う部分が学習の邪魔になるので、そのような部分を、第二言語のデータベースを増やすことで克服しなければなりません。そのための最も重要なメカニズムは「インプットの理解とアウトプットの必要性」であり、さらにそれを例文暗記などによって補足していくことも重要です。意識的な知識の学習とその知識を自動化していくことも重要ですが、それだけで不十分だということを理解しておく必要があります。インプットの理解と、意識的学習の自動化という両方のプログラムを最大限に生かすことが外国語学習の成功のカギとなります。(抜粋)
[完了] 全17回
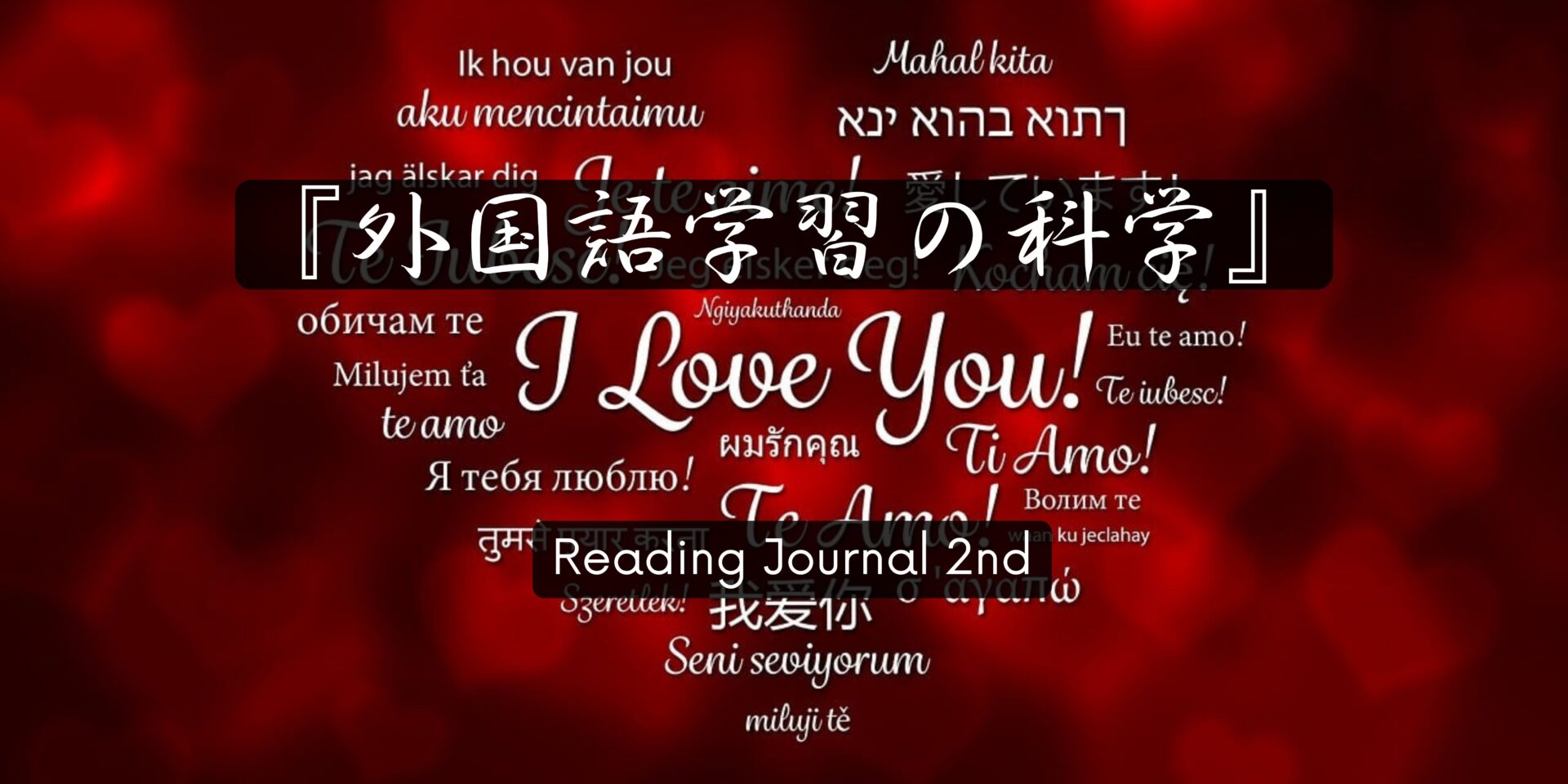


コメント