『日本語のレトリック』 瀨戸賢一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
逆説法 常識を裏返す(構成のレトリック1 仕掛けで語る)
まず著者は、逆説法を解説するために、森毅の「違う意見がよい」(『ふるさとの幻想』)から、一文を引用している。
「心を一つにして」なんて、ちょっともいいことだと思わぬ。「意思統一」なんてのは、よっぽどせっぱつまったときでないかぎり、する必要はない。意見がバラバラ、というのはとてもいいことだ。(抜粋)
我々は、不変の真理ではないにしても、常識という、まあまあの真理に踏みとどまって暮らしている。
しかし、常識はそれほど不動のものでないし、不動の真理といってもそれほど不動ではない。常識をさかさまにしても、いくぶんかは真実らしい姿が見える。
逆説は、一般に、明らかに矛盾していたり、非常識に思われるなかに一条の真実らしい光が差し込むときに生ずる。
もう一つ大切なことは、常識が動くということである。「コペルニクス的転換」と言葉のように古い常識は通用しなくなってしまう。
この逆説は、考えるきっかけを与えてくれる。逆説を通して常識からは見えない、もうひとつの「真実」が明らかになる。しかし、この逆説をそのままにしていてはいけない。逆説は、正説と合わせてみる事に意義がある。
正説と逆説がぶつかりあうことによって、考えが深まります。第三の、より優れた考えが生れることもあるでしょう。逆説が退いて、正説がそのまま残ることもあるでしょう。しかし、そのとき正説は、いったん逆説との対決をくぐり抜けたぶん、より確かな正説となっているのです。(抜粋)
関連図書:森毅(著)『ふるさとの幻想』、青土社(数学のすすめno.11)、1990年
諷喩 たとえ話で語る(構成のレトリック1 仕掛けで語る)
諷喩(アレゴリー)とは、意味に一貫した隠喩の連続である。その例として、著者は鴨長明の『方丈記』を引用している。
ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとゞまりたるためしなし。世中のある人と栖と、又かくのごとし。(抜粋)
ここでは、河とあぶくが人生の隠喩である。
諷喩は凝縮されると「猿も木から落ちる」「犬も歩けば棒に当たる」のような譬えとなる。
ストーリーに展開した諷喩は、「寓喩(寓話による比喩)と呼ばれることがある。寓喩では、『イソップ童話』や『グリム童話』のように人間に似た動物たちが活躍している。ここでは、井伏鱒二の『山椒魚』を例に、寓喩を説明している。
また、より広い諷喩では、話を人間の世界にかぎって、人生のある面を喩える事によって話を展開することがある。これについては、養老孟司の『考えるヒト』からの例を紹介している。
関連図書:
鴨長明(著)『新訂 方丈記』、岩波書店(岩波文庫)、1989年
井伏鱒二(著)『山椒魚』、新潮社(新潮文庫)、1948年
養老猛司(著)『考えるヒト』、筑摩書房(ちくま文庫)、2015年
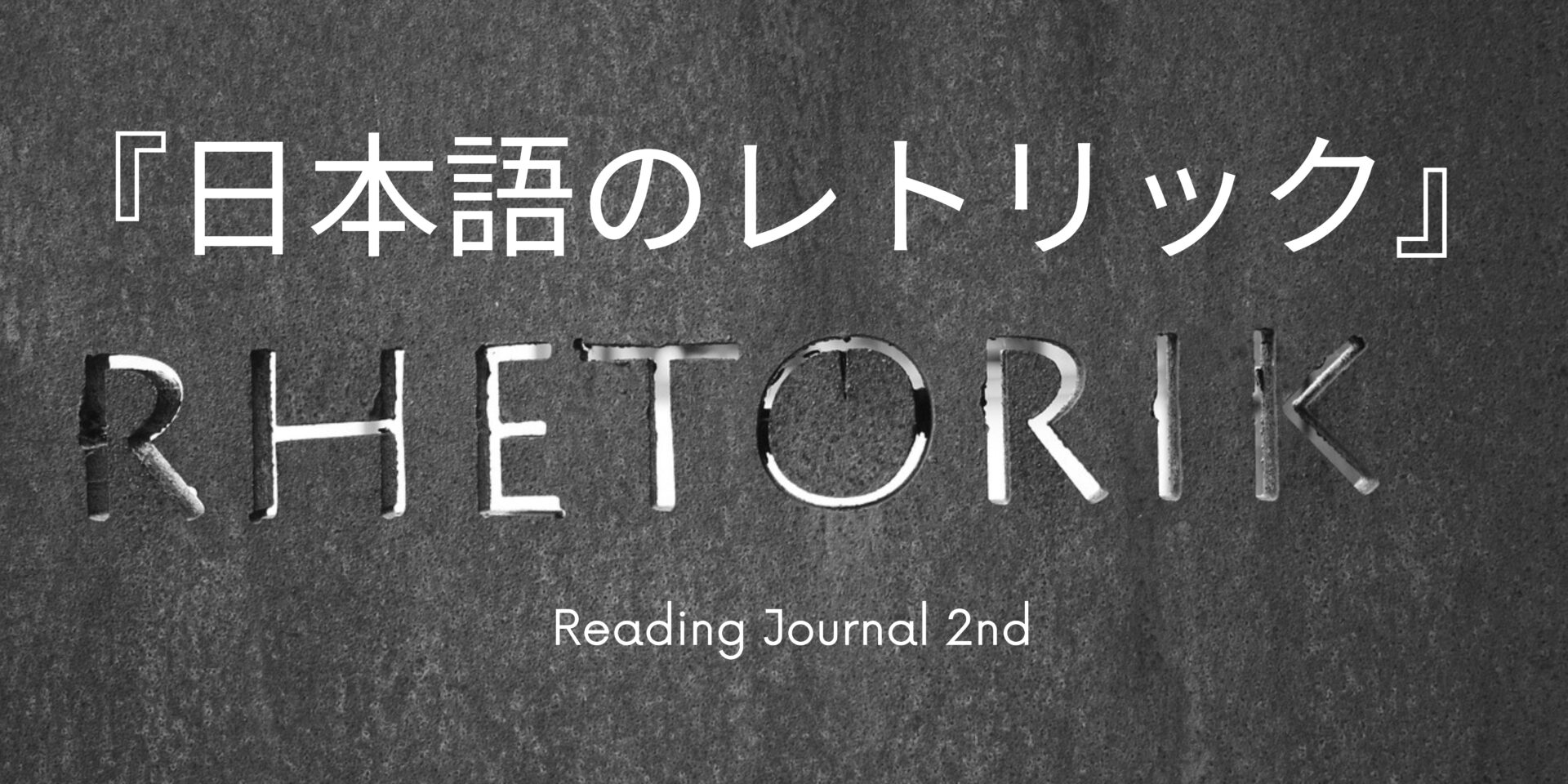


コメント