『外国語学習の科学』 白井恭弘 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第4章 外国語学習のメカニズム -- 言語はルールで割り切れない (その2)
前回 “その1”では、外国語は単に「発音」「単語」「文法」の知識だけでは習得できず「言語はルールだけでは割り切れない」ものであることが書かれていた。では、どのような過程で自然な外国語が習得できるか。今日のところ“その2”では、言語の習得メカニズムとして重要な「インプット仮説」についてである。
言語習得の生得説と学習説
子どもは複雑な文法をもつ言語を教えられることもなく習得する。これを「言語習得の論理的問題」という。この問題について、
- ノーム・チョムスキーは生得知識(普遍文法)
- マイケル・トマセロは、「使用依拠モデル(Usage-based Model)」
を提案した。①は、子どもが生まれながらに言語に関する知識を持っている、というもので、②.は幼児が言語の使用パターンにもとづいて徐々に知識を身につけるというものである。どちらの立場をとるにせよ子どもの第一言語習得のメカニズムは、はっきりわかっていない。さらに複雑な第二言語習得のメカニズム(SLA)はわからないことだらけである。
言語習得研究の課題の一つは、第一言語と第二言語習得の共通点と相違点である。第1章から第3章では、相違点に注目したが、本章第4章では、共通点にも注目する。
インプット仮説
言語習得研究の世界では、インプット(聞くこと・読むこと)だけで言語習得が可能か、それともアウトプット(話すこと・書くこと)が必要か、という論争があるのです。(抜粋)
「インプット仮説」とは「言語習得は、母語も外国語も言語内容を理解することによってのみおこる」というもので、「自然な順序」の提唱者であるスティーブン・クラシェンが主張した。
その証拠としてクラシェンは、「なかなか話しはじめない子どもの中には、ある日突然、完全な文を話しはじめる子どもがいる」ことをあげた。
そして同様な例が第二言語学習でも起こることが知られている。親の転勤で海外に行った子どものうち、最初はずっと黙っていたのに、突然話しはじめるケースが随分とある。そして、このずっと黙っている期間を「沈黙期(silent period)」という。
聴解優先教授法(全身反応教授法とイマージョン)
このインプット仮説を基礎としてクラシェンが提案したのが「聴解優先教授法」で、外国語学習にすぐれた効果をあげている。 この教授法のなかで、効果が立証されているのが「全身反応教授法(Total Physical Response = TPR)」である。この教授法は、先生が外国語で簡単な指示をだし、生徒が全身をつかって反応するというものである。
学生に無理に話させることをしない、ということがポイントで沈黙期を保証してあげるのです。(抜粋)
そして最後に、先生がその日に扱った命令文を黒板に書き、学生がそれをノートに書き写し授業を終える。
そのほか、バレリアン・ポストフスキーは、ロシア語学習の実験により、「インプットが他の技能に転移する」ことを示している。そして、文法項目にふれずに大多数の教科を第二言語で教えるという「イマージョン」という教授法では、聞き取りに関してネイティブと有意な差がないくらいのレベルに達することがわかっている。
インプットとアウトプットの必要性
これまでの研究や事例から、インプット仮説はかなりの信憑性があることがわかる。しかし、それだけでは、説明できない現象がある。
ひとつは、「テレビからは言語習得ができない」という現象で、また「受容バイリンガル」(母国語を聞いてわかるが、話せないバイリンガル、ココ参照)のケースもインプットだけで言語習得ができるという仮説では、うまく説明できない。
このような例は、インプットだけで言語習得をすることは不可能で、アウトプットも必要だという証拠だとも解釈できます。(抜粋)
アウトプットの必要性とリハーサル
ここで、「沈黙期を経て、完全な文で話始める子どもたちの例」より、「アウトプットそのものは言語習得の必要条件でない」ことがわかる。一方、「テレビでは言語は習得できない」ことや「受動バイリンガルの例」より「インプットだけでも言語習得はできない」ことになる。
ここで、突然完全な文で話す子どもが、沈黙期に何をしているかを考えると、頭の中で話し、「リハーサル」を行っていると予想される。テレビを見て育った子どもや受動バイリンガルの子どもは、インプットを理解する必要があるが、話す必要がないため頭の中でリハーサルが行われず、話す能力が発達しなかったと考えられる。
これらを考えあわせると、言語習得に必要な最低条件は、「インプット」+「アウトプットの必要性」ということになります。(抜粋)
つまり、実際にアウトプット(話しこと)をしていなくても、必要性があれば頭の中でリハーサルをすることによって、話せるようになる。このリハーサルは無意識的に起こることもあれば、意識的に行われることもある。
ここで著者は、この仮説を支持するクラシェンの実験について解説した後、自身の「英語で考える」という実体験をしたと述べている。またこのリハーサル効果は、fMRI(機能的時期共鳴画像法)での実験でも支持されている。
インプットのみの場合に比べ、リハーサルをするためには、頭の中で文を組み立てるレベルまでもっていく必要あるため、集中度も言語処理のレベルも上がる(これについての説明は、第5章)。
なるほどなるほど、アウトプットの“必要性”ってところが肝なのね。実際に話してなくても必要性があれば頭の中でリハーサルすることにより話せるようになるってことだ!(つくジー)
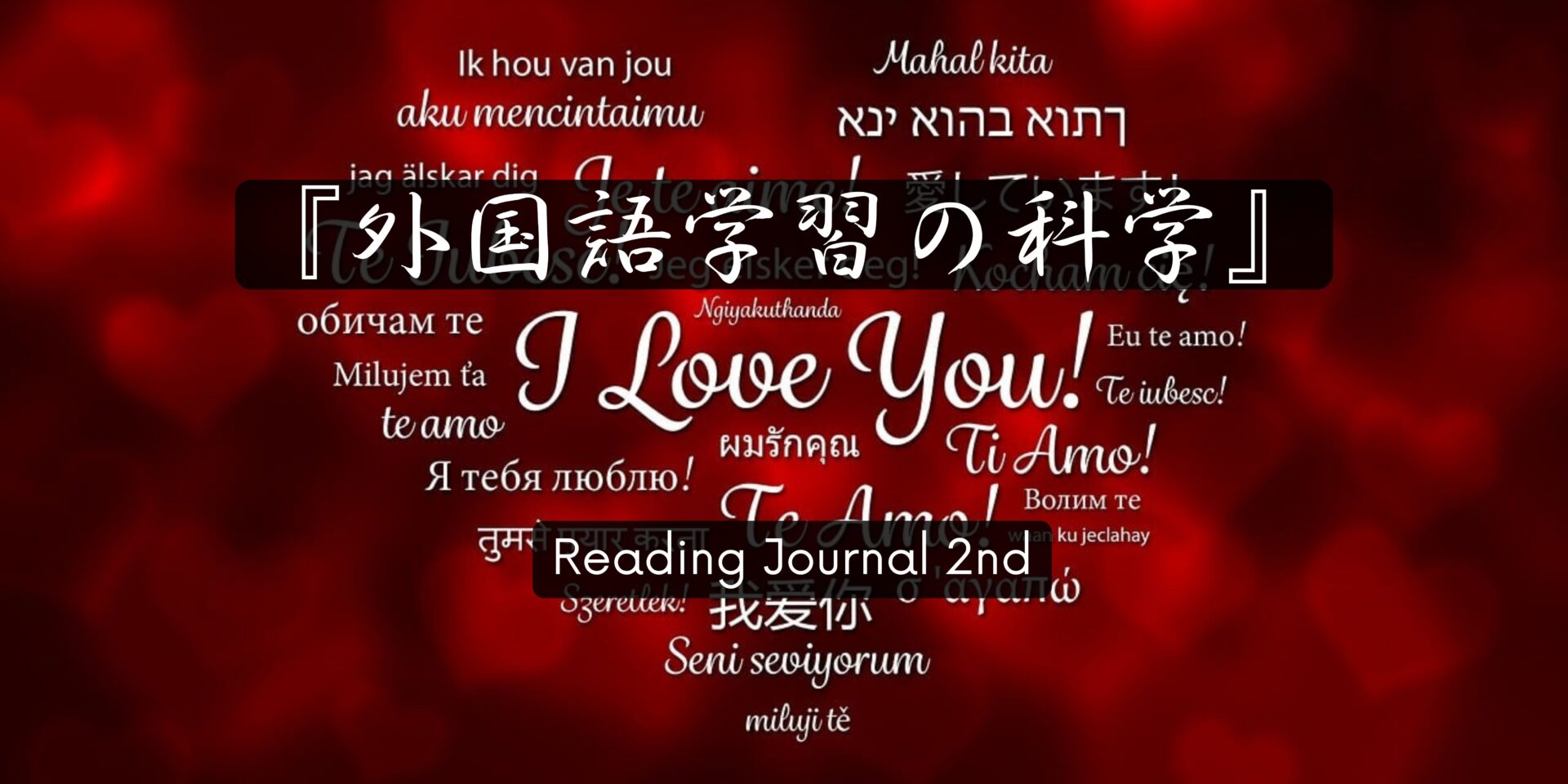


コメント