『プロカウンセラーの聞く技術』 東山紘久 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
27 お茶室は最高の場
お茶室と会談
「お茶室」は会談の場として最高である。お茶室には小道具(ココ参照)もそろい、お茶室ほど雰囲気のいい部屋はない。
適度な光が間接的に入りこみ、お花が活けてあり、掛け軸がかかっており、四畳半という部屋の広さは、広すぎず狭すぎもしません。庭からは小鳥の鳴き声は庭園のせせらぎが聞こえます。遠くの鹿威しの音が間遠に入ってきます。炉には火が入っており、湯が煮える音が静かに鳴っています。部屋は質素ですが、掃除が行き届いており、心を落ち着かせる香りがします。外界との出入り口は狭く、人は存在を殺して部屋に入ってきます。(抜粋)
そして、お茶の後には、食事へと発展する。会食は人の心を開く作用を持っている。
またお茶室のよさは、儀式的な作法があることである。作法のために堅苦しくなると話ができないのは確かであるが、それは作法の問題ではなく場の雰囲気の問題である。
作法があると、かえって場が定まり、それぞれの役割が決まり、雰囲気さえあれば、話し合いに最高の場となるのです。(抜粋)
著者のカウンセリング室には、コーヒーと紅茶と日本茶と抹茶が用意されている。単に日本茶と言った場合は、著者は抹茶を出すといっている。それは、抹茶が一番落ち着かせるからである。
おいしいお茶を差し上げ、それを美味しく飲んでいただく、これがお客をもてなす心です。この点、コーヒーでも、紅茶でも、中国茶でも同じです。それぞれみんないれかたに凝って言います。(抜粋)
また、お茶室というと、わび・さびが強調されすぎて道具などに高価なものを使用する傾向があるが、大切なのはもてなしの心づかいである。
相手中心のおもてなしの心
ここまでの話をみていると、お茶は作法にしても、作りにしても、すべて相手中心である。これは実は聞き方の極意と同じである。
聞き方の極意は、相手中心なのです。心理療法はもてなしの心です。傷ついた魂をいなにもてなすかが、心理療法の精神だと思っています。(抜粋)
ここまで、なるほど!なるほど!と思いながら読んできたが、次の一文に驚いた。
私の師匠の一人は、ロジャース先生と言って、「来談者中心療法」という心理療法の創始者です。(抜粋)
え!著者は、ロジャースの弟子なんだ!!C・R・ロジャースっていうと、ボクでも知ってる心理療法の大家じゃないの!本文に何度も出てきた理由もそれだったのね!(つくジー)
心を育てることと花を育てること
著者は、アメリカ留学から帰国したころ花を育てることに興味を持った。心理療法は、心を育てることであり、それは花の栽培に似ているからである。そして
相談期間が長くかかると思われる来談者が来たとき、7年後に花をつけるような花を実生から育て始めました。(抜粋)
そしてこの花を育てるお茶に興味を持ったとのことである。
28 したくない話ほど前置きが長い
本題と前置き
しなけらばならないが、したくない話というのがあります。こういう話は、話さねばと思うのですが、なかなか本題を切り出せません。このような場合は、聞き手の態度が重要になります。(抜粋)
なかなか話し手が本題に入らないので、聞き手が焦れると、よけい話し手は話せなくなってしまう。しかし、本題に入る前の前置きの話に乗ってしまうと、そこで盛り上がって終わりになってしまう。
プロのカウンセラーの場合は、相手が長々と前置きを話す場合は「前置きが長いのは、話しにくい話」であると思って、前置きの話を聞く。しかし、カウンセラーの方から横道に入ったり、横道へ誘ったりもしない。そうしていると自然と本題の話に入っていく。時に時間いっぱい、本題からそれた話をする人もいる。そういう場合は、今日は本題を話す予行演習だったと思って焦ることはない。自発的に来談しにくる人は必ずいつか本題に入る。
本題で話される内容は、本人にとっては乗り越えなければならない課題を含んでいます。それだけなかなか話せないのです。(抜粋)
話し手が前置きの話を長く話す場合は、自分自身が話しにくかった体験を思い出し、聞き手のどういう態度が心を開かせてくれたかを考え、そのような態度をとると自然に本題に入っていく。
本題に誘い込まない
話し手が本題になかなか入れないのは、「無意識」が本題に入るのを嫌がるからである。このような時は、本題に誘い込んだり無意識をあからさまにするようなことをせずに無意識の心に触れるように、話し手の話を聞く必要がある。
無意識に抑圧していることは、その人にとってはいやなことなので、それを強引に白日に晒してしまっては話し手の心が傷ついてしまいます。そうなれば話し手の抵抗が高まり、ますます聞き手を避け、話をしなくなります。(抜粋)
したくない話ほど前置きが長くなるものである。前置きを十分に聞いてあげ、本題に入るまで待ってあげることが大切である。
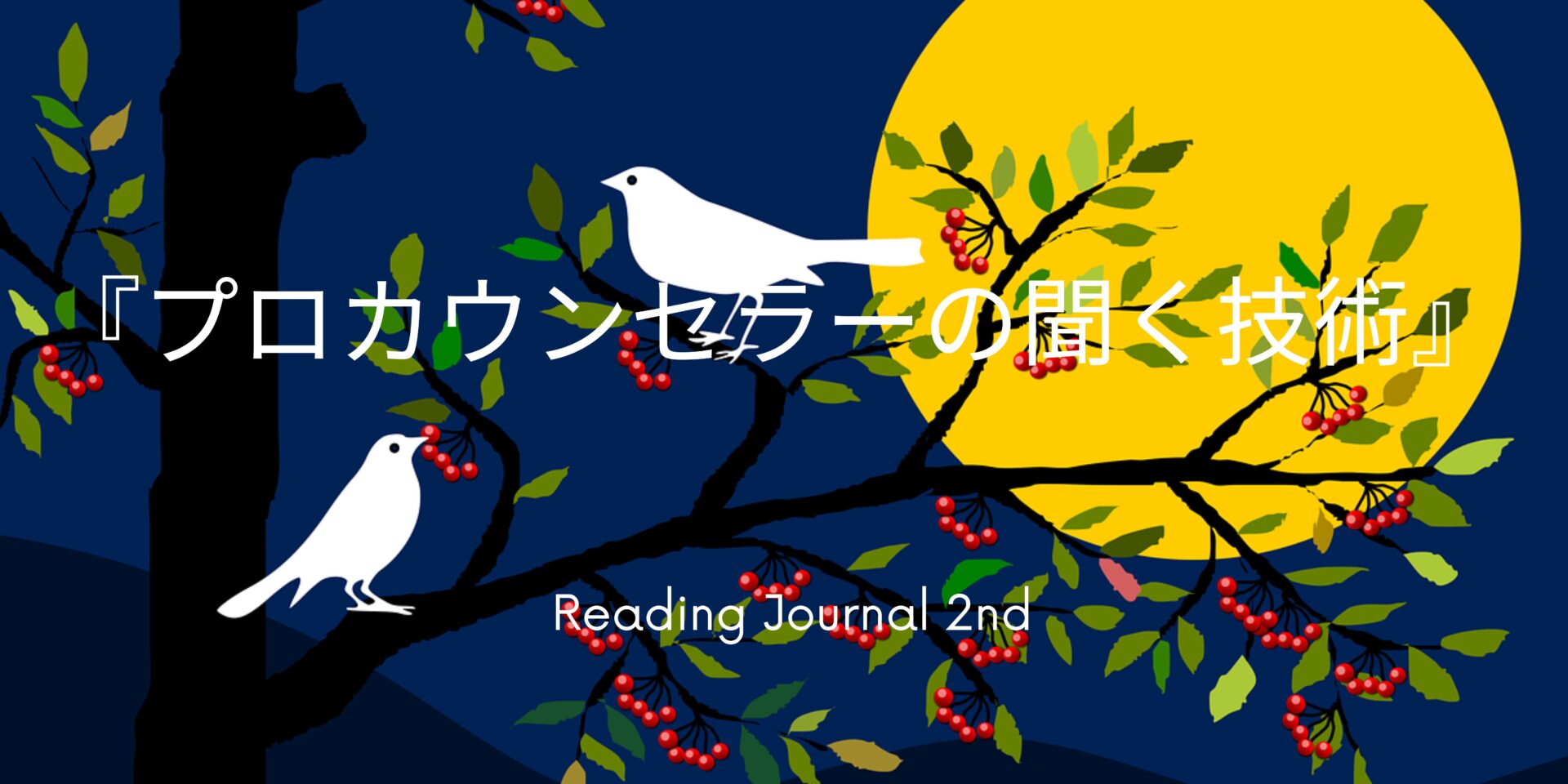


コメント