『日本語のレトリック』 瀨戸賢一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
緩叙法 ひかえめに伝える(意味のレトリック2 意味を調整する)
「緩叙法」は、「誇張法」が度を超すのに対して「ことばをひかえる」。しかし、ひかえて目立たなくするのではなく、うちに秘めた強い感情を伝えようとする。
ここで著者は、夏目漱石の『こころ』の一節を引用する。
そのころからお嬢さんを思っていた私は、勢いどうしても彼に反対しなければならなかったのです。(抜粋)
ここで「思っていた」は緩叙法である。ことばはひかえめだが、ひかえめであるからこそ強い感情を表す。
また、緩叙法には「少し・・・」「ちょっと・・・」あるいは「・・・のようだ」という使い方がある。この「少し」「ちょっと」「ようだ」が文字通りでない時である。
たとえば「少し気がある」「ちょっと来なさい」「少し酔ったようだ」など
このように緩叙法の手段には二種類ある。
- ひかえめな語をえらぶ
- 「すこし」「ようだ」のような控えめな語で修飾する
関連図書:夏目漱石(著)『こころ』、新潮社(新潮文庫)、1952年
曲言法 反意語を否定する(意味のレトリック2 意味を調整する)
「曲言法」は、「半端じゃない」「悪くない」のように、言いたいことの反対を否定して言いたいことを言うという表現法である。「緩叙法」と同じように言葉をひかえることにより、かえって強い意味を伝えようとする。
ただし、曲言法では、ことばの上でマイナスの部分を否定しているだけであるので、直ちにプラスを意味するとは限らないという危険性がある。著者は、このことを芥川龍之介の『六の宮の姫君』の文を引用して説明している。
この危険性は、「悪くない」などのよく用いられる曲言法にも当てはまります。
親 成績は?
子 悪くない
親 じゃ、いいの?
子 良くもない (抜粋)
ここでの「悪くない」は、プラスになっていないので「曲言法」ではない。さらに著者は、本当の曲言法を、竹西寛子の評論「茶の間の辞典」(『国語の時間』)からの引用で説明している。
曲言法を使う理由のひとつは、「ひかえめの美学」ということがある(緩叙法や婉曲法と同じ)。そして、もうひとつの理由は、「否定表現」にある。
一般に、否定を用いる意義は、ある状況が予想される場面でそれを否定するところにあります。(抜粋)
つまり、否定的な事が予想される場面で、それを否定することで強い表現となる。
なるほど、これはちょっと注意が必要かも。まずそうな食べ物(予想)を、口に入れて・・・・・「まずくない」って表現する場合を考えると
「まぁ食べられる」って意味だと(予想どおりにまずいから)「曲言法」でなく、(見た目が悪かったが)「うま~~~い」って意味だと「曲言法」ってわけですね!(つくジー)
関連図書:
芥川龍之介(原作) 、熊倉一雄(朗読)『地獄変/六の宮の姫君』、新潮社(新潮CD)、2006年
竹西寛子(著)『国語の時間』、河出書房新社(河出文庫)、2000年
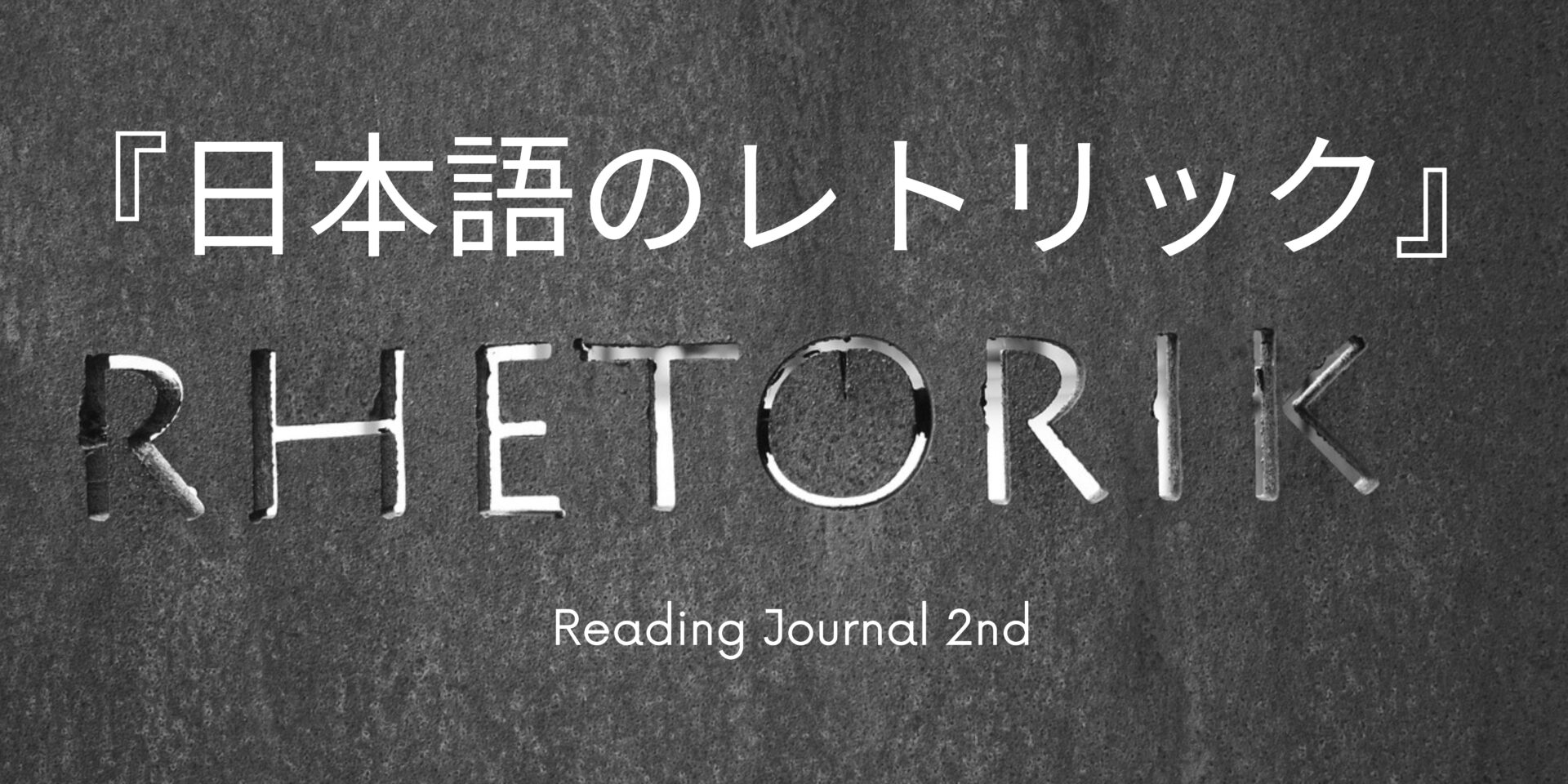


コメント