『日本語のレトリック』 瀨戸賢一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
提喩 カテゴリーをあやつる(意味のレトリック1 意味を転換する)
いよいよ、意味のレトリック1 ”意味を転換する”の最後。今日のところは「提喩」である。この「提喩(シネクドキ)」を解説するために著者は、志賀直哉の『清兵衛と瓢箪』の一節を引用する。
ここで、著者は、清兵衛が「瓢箪を見に町へ出かけた」という表現を取り上げ、町に住んでいる清兵衛が町に出かけると言うのは変な表現であると、指摘している。しかし、ここでいう町は、町中という意味であり、町中は町の一部であるので、この表現は、前章の「換喩」であると説明している。
次に、清兵衛は瓢箪の「手入れが済むと酒を入れて、手拭で巻いて、・・・」の部分の「酒」について解説している。この「酒」は、酒一般ではなく「日本酒」を指す。しかし、「酒」と「日本酒」の関係は「町」と「町中」の関係と異なり、これは、「提喩」であるとしている。なぜならば、「日本酒」は「酒」〈の一種〉だが、「町中」は「町」〈の一種〉ではなく、町の一部だからである。
提喩(シネクドキ)とは、〈の一種〉の関係、つまり類と種の関係にもとづいて意味範囲が伸び縮みする現象です。(抜粋)
提喩は、意味が含み・含まれるという関係に支えられて、ゴムまりのような弾性を示す。
瓢箪づくりに熱中する清兵衛は、
「到底将来見込みのある人間ではない」(抜粋)
と先生から言われてしまう。
ここでの「見込」はもともと「いい見込み」も「悪い見込み」もあるが、ここでは「いい見込み」である。つまり、より一般的な表現(類)がより限定された表現(種)を伝えるとい提喩になっている。このような類で種を表す提喩は言葉の本質に根ざしている。
また、提喩には「種」で「類」を表すものもある。たとえば「ごはん」は、文字どおりの「ごはん」と意味だけでなく「食事一般」も意味している。西洋の「パンを稼ぐ」という表現も種で類を表す提喩が使われている。代表的な商品名がそれに類する商品一般をさしたり、小野小町が美人を意味したりするのもこの提喩である。
関連図書:志賀直哉(著)『清兵衛と瓢箪・網走まで』、新潮社(新潮文庫)、1968年
誇張法 度を超して伝える(意味のレトリック2 意味を調整する)
ここから、意味のレトリック2 “意味を調整する”に入る。まずは「誇張法」である。
「誇張法」は、「極端に大げさな言い方にする表現法」である。「すごい」、「ものすごい」などの言葉の上塗りに始まり、「白髪三千丈」「一日千秋」「千尋の谷」などの定型句まである。
誇張法は、驚きの分をことばで上乗せするという、自然な動機によっている。
時代劇や時代小説では、誇張法を上手に配置することにより上手に人物や場面を設定できるとし、ここでは、宮部みゆきの『初ものがたり』を引用して誇張法の説明そしている。
まず、「猫の額」や「雀の涙」のような表現を取り上げ、
時代小説ではこのような定型句に近い表現が案外効果的なのです。(抜粋)
としている。
さらに、派手な誇張法として、
半次郎の黒い瞳が、目の玉のなかで、煮え立つ湯に放り込まれた豆の粒みたいに激しく動いた。(抜粋)
や、
お吉はまた笑いだした。「そりゃもう、頭で壁に穴を開けられそうなほど、ひとりで尖ってましたよ。」(抜粋)
をあげている。そして、この二つの表現はどちらも「直喩」による誇張法であることを指摘し、直喩でない誇張法として、「ノミの心臓」「心臓に毛をはやした」「鉄の心臓」さらには、「宿題の山」「仕事の山」「洗濯物の山」など「隠喩」の誇張法の例をあげている。
関連図書:宮部みゆき(著)『初ものがたり』、新潮社(新潮文庫)、1999年
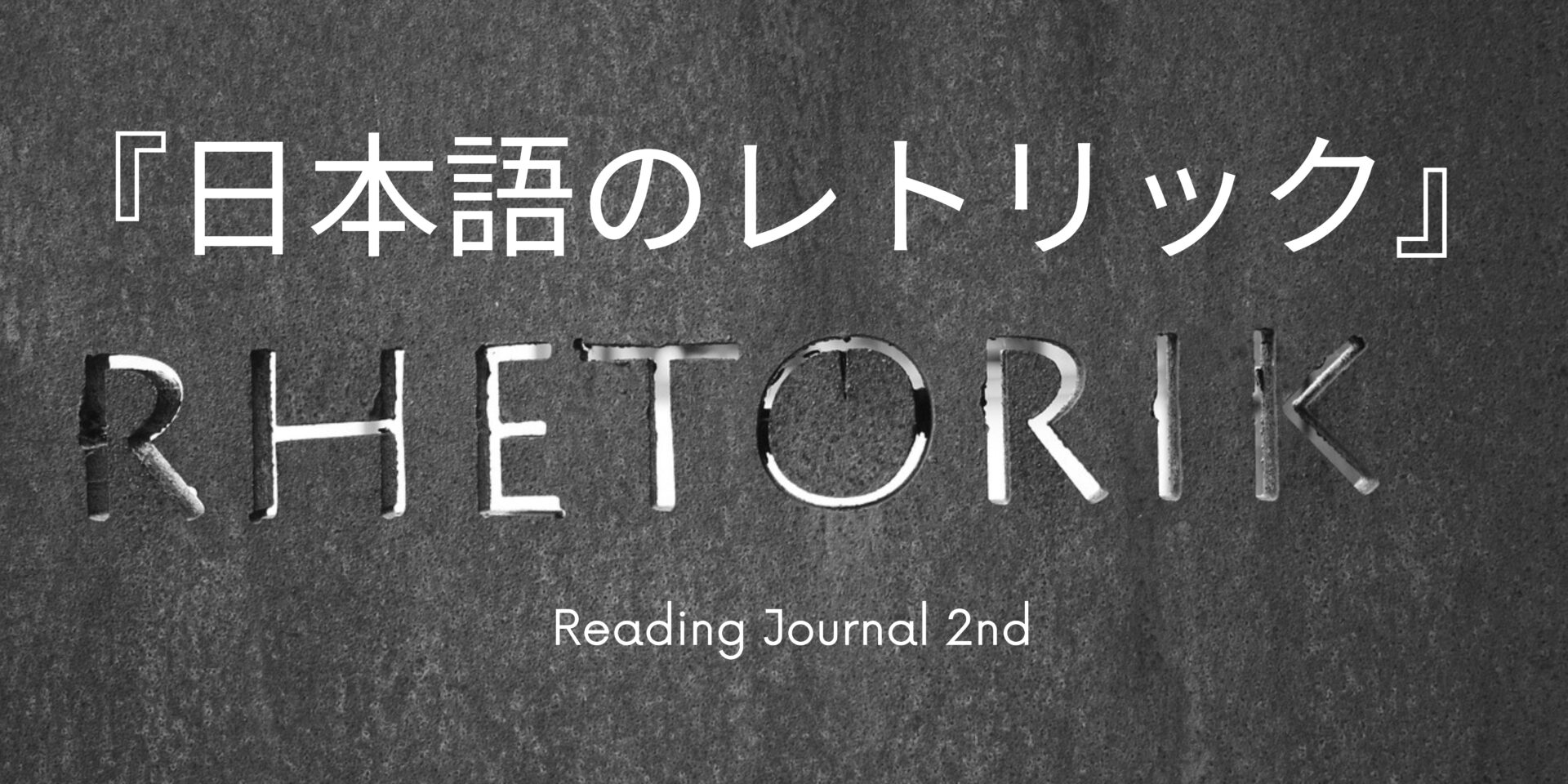


コメント