『新装版 ペルーからきた私の娘』藤本和子 著、晶文社、2024年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
『新装版 ペルーからきた私の娘』
毎日新聞(スマホ版)の書評に本書・『新装版 ペルーからきた私の娘』が紹介されていた。帯には、
日本人の妻、ユダヤ人の夫、
ペルーからきた赤ん坊。
アメリカの町から町へ
冒険に出た家族の物語。
とある。なるほどなるほど、よくわからにけども面白そうだなと思って買ってみました。「1984年刊行の名エッセイ集、待望の新装復刊。」ってとこもイイよね。
本書は、表題の「ペルーからきた私の娘」、「ウィラード盲目病棟」、「鯨が生んだ鱒」の3つのエッセイが収録されている。
「ペルーからきた私の娘」は、著者とユダヤ人の旦那さんが、赤ちゃん(ヤエル)を養子にむかえるためにペルーに滞在した時の記録である。ヤエルの生命力、親となることの戸惑い、遅々として進まない手続きへの苛立ち、滞在中に取材した女性運動家の話などが、淡々と語られている。
次の「ウィラード盲目病棟」は、60年も精神病院に入院している日本人のオキヤマ・フキタさんのためにボランティアとして病院へ行った話が中心であるが、後半の幾つかの文章は病院とは関係ない小文になっている。
最後の「鯨が生んだ鱒」の前半は、著者が翻訳したブローティガンの『アメリカの鱒釣り』に関係した話である。この部分はなかなか難しく、ボクのようなものには読み込めなかった。少なくとも、メルヴィルの『白鯨』、ヘミングウェイなどのアメリカ文学に親しんでないと難しいのではないか?と思った。それもそのはずで、これは『アメリカの鱒釣り』の翻訳本の「訳者 あとがき」なのだそうだ。『アメリカの鱒釣り』の後半の二つは、アメリカの女性への聞き書きである。
この3つのエッセイの面白さは、大体順番どおりだが、『アメリカの鱒釣り』に収録されている最後の二つ話、つまり「ペンキを塗る人」「たましいの遺産」は、不遇な環境をたくましく生きるアメリカの女性の聞きで、著者の本領発揮というところだと思う。
全体に文体は落ち着いている。そして、確かにめったにないような話が語られるが、だからと言って大きな事件が起こるわけでもない。これをなんと表現したらよいだろうかと思ったら、榎本空の解説にちゃんと書いてあった。
そうなのだとしたら奇妙で、複雑な地図だ。大事件は起こらない。出来事未満の、藤本和子によって照射されなければけっしてわたしたちがその出来事として認識することがなかったであろうくらしのかけらが、彼女にだけ可能な筆致から立ち現れる。からっとしていて、権力を持つものに批判的で、どこかとぼけているようで、踏みつけられたものの、特に女性たちの苦しみと、しかし抑圧だけには規定されぬ喜びや強さ、つまり生そのものの複雑さに敏感で、文字には残らぬ記憶の方へと引き寄せられて、そしてうつくしいものへの感嘆を隠さずに・・・・・(後略)・・・・・・(抜粋)
関連図書:
リチャード・ブローティガン(著)『アメリカの鱒釣り』、新潮社(新潮文庫)、2005年
ハーマン・メルヴィル(著)『白鯨』(上・下)、新潮社(新潮文庫)、1952年
目次
ペルーからきた私の娘
ウィラード盲目病棟
白樺病棟の「高砂」
かげりもない、ペネイの夜ふけに
ボランティアたちの晩餐会
スパゲティかぼちゃ
夢
オムライス
ヘンリーの運勢判断せんべい
鯨が生んだ鱒
『アメリカの鱒釣り』の表紙の町
『アメリカの鱒釣り』の表紙の男
はじまりとおわり
連続と不連続
一すじの黒髪と紙屑籠
ペンキ塗るひと
たましいの遺産
あとがき
解説 聞くことと聞けぬこと、その奇蹟について 榎本空
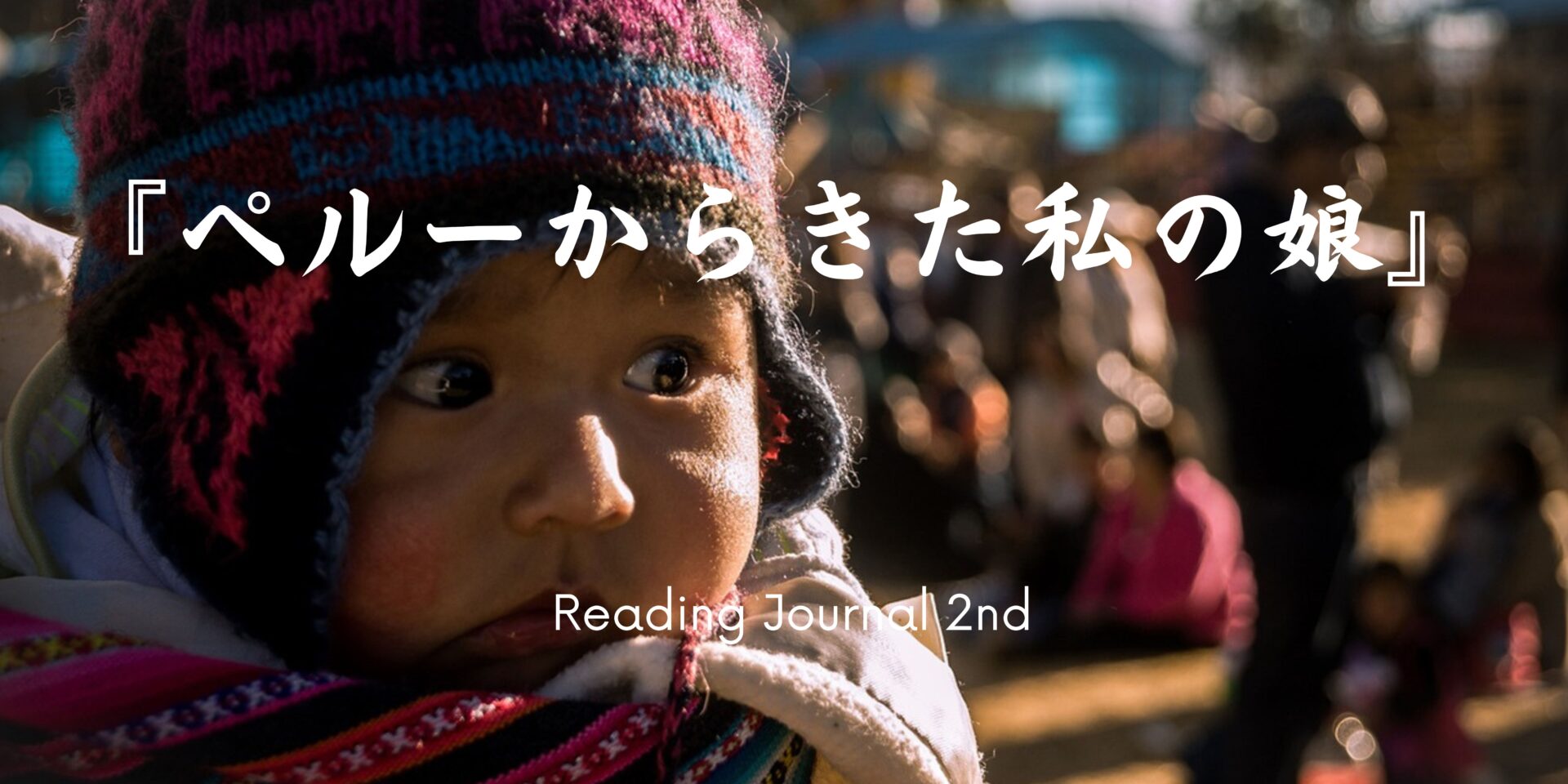


コメント