『猫の日本文学誌』 田中 貴子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第九章 描かれた猫たち(前半)
今日から本編の最終章の第九章『描かれた猫たち』である。著者は、ここでのテーマを“涅槃図”と“招き猫”、そして十二支が戦い合う御伽草子“『十二類合戦絵巻』”の3つである、としている。この九章は2回に分けてまとめるとして、前半は、“涅槃図”と『十二類合戦絵巻』、“後半”は、“招き猫”。そして最後に「エピローグ」である。
涅槃図に描かれた猫
従来、釈迦涅槃図には猫が描かれることは少ないと言われてきた(ココやココ参照)。その理由は、昭和期の『俳諧歳時記』によると、
釈迦が入滅することを天上に住む摩耶夫人に知らせると、夫人は悲しまれて薬袋を天上から投げ下ろした。ところが、沙羅樹の枝先に袋がひっかかった。誰も取りに行けない。折から、一匹のねずみが飛び出して薬袋の紐を食い切ろうとしたが、下にいた猫がねずみに飛びつき食ってしまった。それで薬が得られず釈尊は入滅された。だから涅槃図には猫は描かない。(抜粋)
と説明されている。しかし、有名な東福寺の涅槃図をはじめとしてよく目を凝らせば案外古い作例にも猫が描かれている。したがって、必ずしも猫が仏敵だから描かれなかったというわけでもないことがわかる。
著者が「猫のいる涅槃図」として親しんでいるのは東福寺の涅槃図には、下の方に猫が描かれている。しかし、実際の開帳では、縦横数メートルあるため全部は広げられずに猫のいる下の方は巻いてある。したがって猫の姿は事務所で売られている絵葉書で忍ぶだけである。
著者は、この本の単行本版を通じて、涅槃図の研究をしている河本俊子さんと知り合った。河本さんによると涅槃図に猫あるいは猫にしか見えない動物が描かれているのは珍しいことではないそうである。
猫が仏敵だから涅槃図に猫はいない、というのは、ある時点で一般化した伝説にすぎないのである。(抜粋)
南方熊楠は、「猫一疋の力に憑いて大富となりし人の話」で次のように書いている。
本邦の俗伝に、仏涅槃の時、諸畜生これを悲しみに、猫のみ笑いしとて、涅槃相の絵にこれを描かず、猫はこれを嘆き、兆殿司に請いしゆえ書き入れたるが東福寺とかにありという。(抜粋)
(『南方熊楠選集 2』平凡社、一九八四年)
この“本邦の俗伝“は、分権的に江戸時代までさかのぼれる(竹林史博『よくわかる絵解き涅槃図』、青山社、二〇〇八年)
そして猫が涅槃図にいない理由を語るパターンは二つに分かれる(河本俊子「猫好きの京都案内-歴史の中の猫-」『あふひ』二〇一二年)。
- お釈迦さまの臨終に間に合わなかったから。遅刻の理由は「寝坊した」「化粧をしていた」「ネズミに嘘の情報を教えられたから」というものまである。「十二支に猫がいない理由」との混同がある
- 天上から摩耶夫人が投げた薬袋を取りに行ったねずみを食べ、仏敵になったから
猫のいる涅槃図は、珍しくなかった。しかし江戸時代以降に「猫は仏敵だから涅槃図に描かない」という俗伝のため、東福寺や清凉寺など「猫がいる」ことを巧みに用いて参列者に寺を印象づけようとした観光事業があったようである。
『十二類合戦絵巻』の猫
猫の登場する著名な絵として、江戸初期に作られた『十二類合戦絵巻』がある。十二支の動物たちが歌合をするが、飛び入りしようとした狸が排除される。恨みを抱いた狸が十二支に入らなかった動物を集めて戦いを仕掛けるとい話である。
アイルランドにあるチェスタービューティーライブラリー(CBL)が所蔵する絵巻が大変美しい。猫は狸が集めた動物たちが宴を催している場面に現れる。猫は魚と流水、そして蝶という派手な衣装で、酒をそそぐ入れ物を手にして半身を見せている。
この猫について、単行本版では、遊女としていた。この説は、もともとは小峰和明の説である(「お伽草子の絵巻世界――物いう動物たち―」『日本文学文化』第四号、二〇〇四年)。しかし、その後、斎藤真麻理の論考によってそれが誤りとわかったので訂正するとしている(斎藤真麻理(著)『異類の歌合せ-室町の機知と学芸-』、吉川弘文館、二〇一四年)。
斎藤の論考はCBL本を詳細、周到に考察している。まず動物たちの酒宴の場面が『前九年合戦絵巻』の一場面を模しているとしていとし、次のように遊女の説を否定している。
色鮮やかな衣装や紅をさしたような口元から、遊女または若衆と見る説もある。しかし、詞書によれば猫は侍大将を拝命している上、(中略)『前九年合戦絵巻』の童子と等しく袴姿であるから遊女ではない。堂本本の猫が口元を引き締めているのに対し、CBL本の猫は赤い舌を出しているため紅と見紛うのも無理はないが、俳諧では「舌」の付合[つけあい]は「猫」(『類船集』)である。(抜粋)
関連図書:
竹林史博(著)『よくわかる絵解き涅槃図』、青山社、2008年
河本俊子(著)「猫好きの京都案内-歴史の中の猫-」『あふひ』 京都産業大学日本文化研究所報、2012年
小峰和明(著)「お伽草子の絵巻世界――物いう動物たち―」『日本文学文化』第四号、2004年
斎藤真麻理(著)『異類の歌合せ-室町の機知と学芸-』、吉川弘文館、2014年
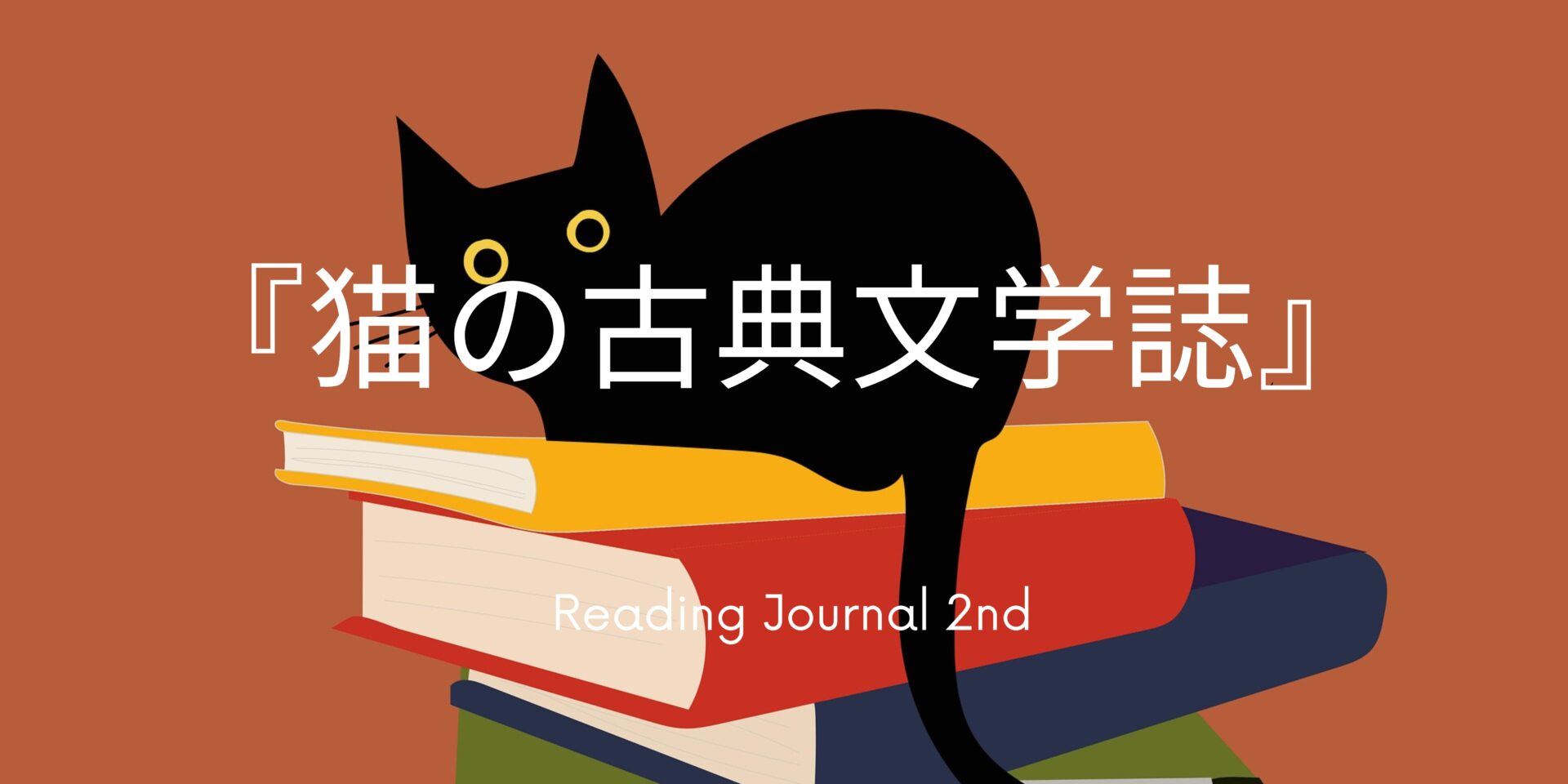


コメント