『猫の日本文学誌』 田中 貴子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第四章 金沢文庫の猫
今日から第四章である。第三章は、平安時代には、高級舶来品だった「唐猫」がしだい変容し、ついには、ねこまた妖怪になっていった。これが江戸時代には「化け猫」となるのだが、著者の関心が中世中心であるため、ねこまたまでで終わった。
そして、第四章は「金沢文庫の猫」である。金沢文庫の周辺では、「かな」という猫がいたそうである。さて読み始めよう。
金沢文庫と「かな」という猫
かつて、猫のことを「かな」と呼称していた地方があった。神奈川県の金沢文庫の周辺である。この名称は、金沢文庫の「かな」からとったと伝えられてきた。(抜粋)
金沢文庫は、鎌倉時代の中頃に北条実時が建てた図書館の名前である。その後、その蔵書は一族だけでなく好学の士に貸し出されるようになり、学問を志す人々が集まって、金沢学校とも呼ばれるようになった。そして、鎌倉幕府が滅亡すると次第に衰退し、蔵書は東隣りの称名寺の管理に移る。
この「かな」という猫について最も古い資料は、浅井了意の『北条九代記』(一六七五)である。
「かな」というのは金沢猫の種で、人ごとにほめ、家に飼っているからいう名前であろう。猫を「かな」と称している。(抜粋)
これにより、「かな」は特殊な猫で、人にほめられるほど立派であることがわかる。
さらに、『日本釈名』(一七〇〇年)には、さらに多くの情報がある。
昔、相模国(武蔵国の誤り、筆者注)金沢称名寺に文庫があって、蔵書が多く収められていた。中国から書が多く舶載されてきたとき、ねずみを防ぐためによい猫を乗せてきた。その猫の種を金沢猫といっているのを、略して「かな」とつけたのだ。(抜粋)
つまり、書物を乗せた船には、ねずみを良くとる猫を選別して一緒に乗せていて、その猫を金沢猫・「かな」と呼んでいたのである。
同様の記事は、『大和本草』(一七〇九)、『梅花無尽蔵』(中世の禅宗の書物)、『金沢山霊宝記』(一七三〇)にもある。
この唐猫たちは、江戸時代にはすっかり日本に溶け込み「今に名物なり」と言われるようになった。このように金沢猫たちは、ついには中国には帰らなかった。彼らは行きには必要だったが帰りはさほど必要でなかったからである。
『金沢名所杖』には、六浦千光寺の金沢猫の塚が名所として載っている。
堂の前に、唐猫の碑石がある。昔、唐船が三艘の浦に着いたとき、連れてきた猫が死んだのを埋めて、そのしるしに建てた石だという。今に至って唐猫の子孫がいるというのも、この故だろうか。(抜粋)
この千光寺は、現在も残っているが場所が移転している(『金沢ところどころ』(金沢区制五十周年記念事業実行委員会、一九九八)。しかしこの猫塚は有名で現在もちゃんと元の場所に建っている。
やや長い三角の形をした石である。近くには「猫畑」という地名があり、そのも金沢猫と関係する土地のよしである。(抜粋)
金沢猫とお経の関係
猫とお経は切っても切り離せない。宮川道達の『訓蒙要言故事』にも、
僧はねずいが経典を噛むのを憎んで猫を飼う。唐の三蔵法師は西方に赴いて経を取り、猫を携えてきた。(抜粋)
という一文がある。三蔵法師が猫を連れてきたかどうかは分からないが、このように猫の「起源」は神話化されている。
禅僧・万里集九の『梅花無尽蔵』に最も古い金沢猫の記述(文明八年(一四七六))がある。見えることでわかる。
二十七日、金沢の称名寺に入った。西湖の梅を問うたが、まだ開いていなかったのが残念だ。ここには楊貴妃が送った玉の簾と金沢猫、そして天竺や中国の書の目録がある。(抜粋)
このように金沢猫すでに名物となっている。
そして、金沢猫には他の猫には無い特徴があったとされている。『鎌倉欖勝考』には、
里人にたずねると、日本の猫は背を撫でるときは自然に頭から低くして背を高くするものだが、唐猫の種類は、撫でるにしたがって背を低くする。これは他にたがうことがない。またみな前足より後ろ足が長く、その飛ぶこと早い。毛色は虎文、または黒白斑文のあるものが多く、尾は短いものである。(抜粋)
と書かれている。また、そこ毛色については、菅江真澄が全集(第十巻、未来社)に書き残している。
それによると、金沢猫の尻尾は短く、体は大きくなく、三毛斑文などがいた、とある。(抜粋)
仏教では、猫をあまり重要視していないため(ココ参照)あまり涅槃図には書かれないが、金沢文庫にある涅槃図には、唐猫が描かれている。これは、金沢猫は、経典を守った徳の高い猫であるため特別に描かれたという伝承がある。
このような金沢猫の伝承は昭和三十年代まで続いていた。
関連図書:佐野大和(著)『金沢ところどころ』、金沢区制五十周年記念事業実行委員会、1998年(ココ参照)
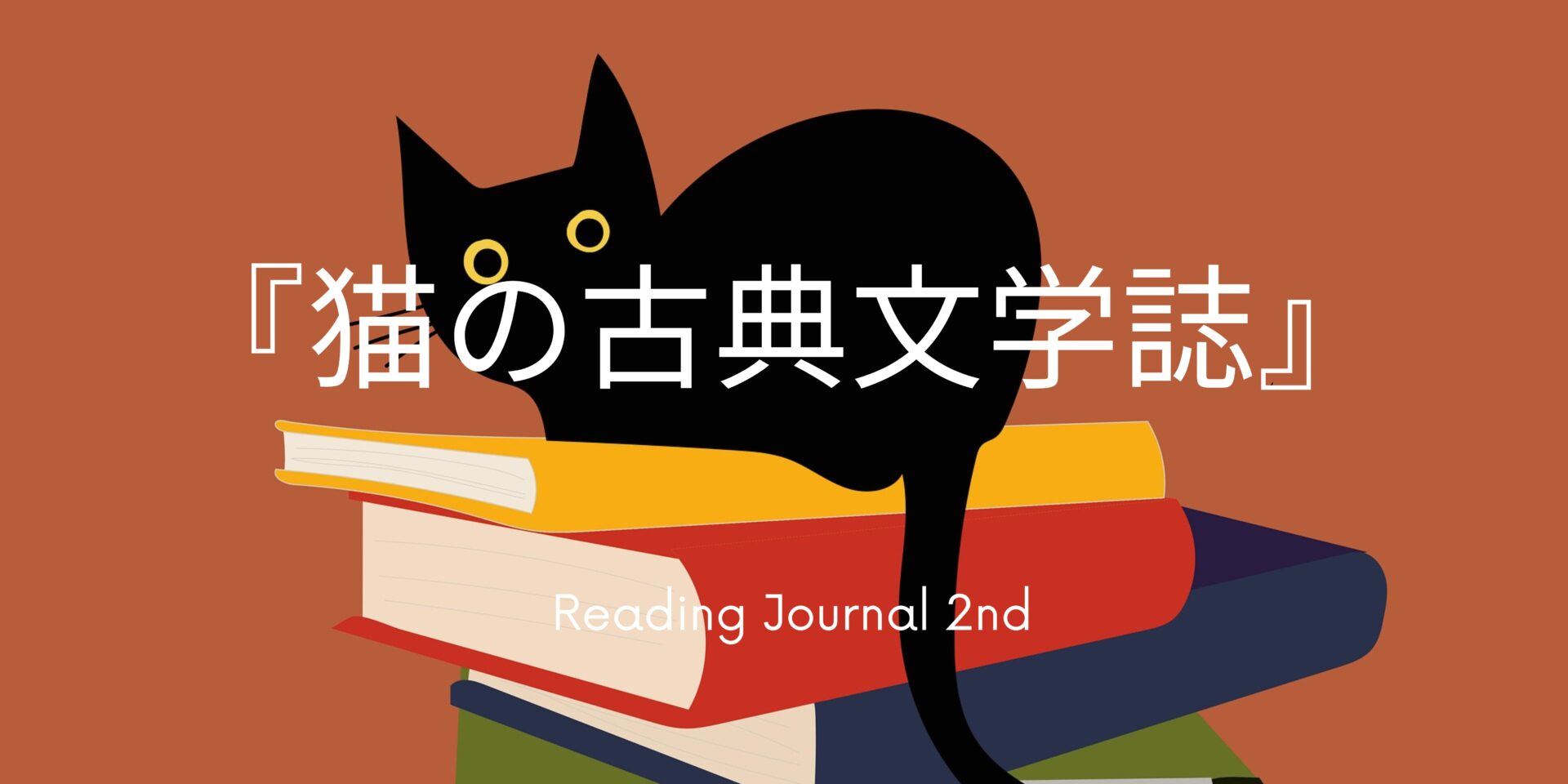


コメント