『猫の日本文学誌』 田中 貴子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第三章 ねこまた出現(その3)
今日のところは、「第三章 ねこたま出現」のその3、前回・その2でねこたまが中国の金華猫という化け猫の影響を受けていることが語られた。今日のところその3では、ねこたまに影響を与えた要因をさらに二つ、「狐」と「猫鬼」が取り上げられる。
ねこまたと狐の妖怪
ねこまたという妖怪の発生には、中国の金華猫の影響に加えて、狐の妖怪の影響がある。『重訂本草綱目啓蒙』には、
俗に、老猫で尻尾が二股に分かれ、人をたぶらかすのをねこまたという。(抜粋)
という所見が述べられている。また、伊勢貞丈の『安斎随筆』には、
数年の老猫は形がおおきくなり、尻尾が二股になって災いをなす。これをねこまたともいう。尻尾が分かれているから(ねこまたと)いうのだろう。(抜粋)
つまり、ねこまたの尻尾は二つに分かれていると書かれている。この尻尾が二つに分かれる理由として、狐の化け物との関係がある。
狐は猫よりも早くから妖怪化していて、中国にも狐の妖怪の話はたくさんある。日本で有名なのは室町時代の物語『玉藻の前』である。この物語は、多くの伝本が絵巻物として伝わっていて、その狐の尻尾は、初期は二股に時代を経ると九尾に分かれている。
そして、『燕石十種』には、猫が狐と交わって子を産んだ、という話がある。このような話が生れた背景には、猫と狐がどちらもよく化けるという認識があったと著者は指摘する。
このように、猫は、いわば化け物の先輩というべき狐との関係においてねこまた化していったと思うのである。先に、ねこまたがなぜ生まれたかという理由を箇条書きにして二点示したが、ここでもう一点、「三、妖怪と化す狐との関係」という条件をくわえたいと思う。(抜粋)
(他の二点は前回の最後を参照)
ねこまたと『猫鬼』
ここで、著者はねこまた誕生の背景として、もう一つ加える。すなわち「四、猫鬼との関係」である。猫鬼とは、巫術の呪いに用いられる妖怪のことである。
中国ではいろいろな動物を使って魔術的な行いをするが、描鬼もその一つで、猫を殺して霊を使役して呪詛したり物を盗んだりする(澤田端穂『中国の呪法』)。この猫鬼は子どもに取りつくことが多く、幼児の夜泣きはもっぱら猫鬼がついているからだと噂された。著者は子どもの夜泣き声と猫の泣き声が似ていることからこのような伝承が生れたとしている。
この猫鬼は、古い時代に中国から輸入されていたようで、すでに鎌倉時代に文献にあらわれる。『仏説護諸童子陀羅尼経』には、幼児を害する十五の悪しき鬼の一つとしてあらわれる。
この十五の鬼神は、常に世間を遊行し、幼児を病気にさせ、恐怖に陥れるのである。(中略)「曼多難提」という鬼神は猫の形をしている。(抜粋)
この十五の鬼神は「十五童子経曼荼羅」という曼荼羅図に描かれ、必ず猫鬼も含まれる。
中世に流行した「伝屍病」についての口伝を記した『伝屍病口伝』には、
猫鬼はネコの形をした鬼である。(抜粋)
と明記されている。この伝屍病については十四世紀の『渓嵐拾葉集』に詳しく述べられている。
このような猫鬼への畏怖は、金華猫より古くからあり、後のねこまたの出現への布石となっている。
中世に突如現れた猫の妖怪・ねこまた。ねこまたはこの後、近世になると化け猫とも呼ばれ、芝居や小説のよき題材になり、近世の人の心を脅かすことになるが、近世の化け猫物についての研究は多く、私の関心も中世が主なので、これ以上の追及は控えよう。(抜粋)
ここで著者が指摘した、ねこまたが生れた背景を整理すると
- 年老いた猫は化ける、という認識
- 中国の金華猫からの影響
- 妖怪と化す狐との関係
- 猫鬼との関係
となるだろうか(つくジー)
関連図書:澤田端穂(著)『中国の呪法』、平河出版社、1984年
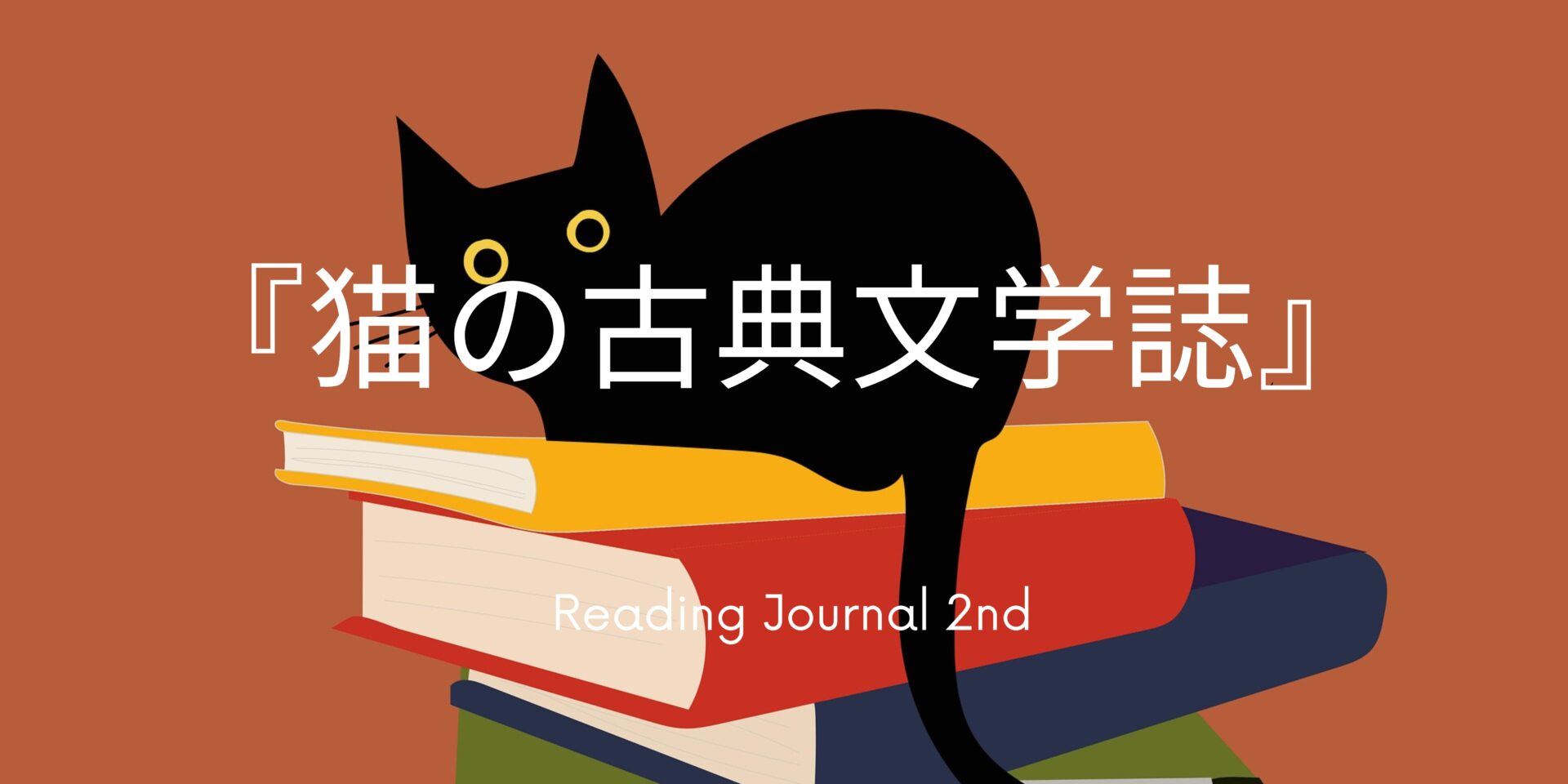


コメント