『猫の日本文学誌』 田中 貴子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第三章 ねこまた出現(その2)
その1では、ねこまたがどのように文献に出てきたかを追い、ねこまたがどんなものとして描かれたか、について書かれていた。それを受けてその2ではねこまたと中国の金花(華)猫との関係からどのように妖怪猫まで成長したかを解きあかす。
『徒然草文段抄』『徒然草諸抄大成』のねこたま
その1の最後は『徒然草』の「ねこまた出現事件」であった。ここで著者は『徒然草』の注釈書『徒然草文段抄』、『徒然草諸抄大成』を参照する。
『徒然草文段抄』には、
猫また これは和名猫(音は「ネコマ」)。『徒然草野槌』では、金花猫は黄金色の猫で、化けて婦女を犯して煩いをなす、という。(抜粋)
『徒然草諸抄大成』には、
猫また、猫の長く生きたもの(原文は「猫まのたけたる」)という意味でねこまたというらしい。和名は猫で音はネコマ、よくねずみを捕る。(中略)金花猫は黄色の猫である。化けて婦女を犯して煩いをなす。雄猫に犯された場合は雄を殺してこれを治し、雌猫に犯された場合は雌をとらえてこれを治す、というようなことが『続耳談月令広義』などという書に見えている。(抜粋)
と書かれていて、これらでは「金花猫」と「ねこまた」は同じものとして認識されている。
『五雑俎』の金華猫
この「金花猫」は、中国の金花(華)地域に住んでいる独特の化け猫のことである。中国の書・『五雑俎』には
南方に住む猴は魅となることが多い。たとえば、金華の家猫は、三年以上飼っていると、必ず人を迷わすことができる。(抜粋)
と書いてある。
この地方の猫は、飼ってから三年たつと、夜中に屋根に上り月のエッセンスを吸う。そしてそれを繰返していると妖怪になり人に取り憑く。その退治法は、猫を捕獲してその肉を焼き、病人に食べさせることである。
つまり『徒然草』の注釈者たちは、中国の文献の影響を受けている。そして猫がねこまた化する条件は、やはり「年をとっていること」とわかる。
この辺りになるとほぼオカルトですね。退治法で焼いた肉を病人に食べさせるってあるけど、病人は大丈夫なのか心配です。そもそも猫の肉を食べるって!!「にゃんとも怖い!(ねこだけにね♪)」(つくジー)
『本朝食鑑』、『和漢三才図絵』、『耳袋』の(年取った)猫
十七世紀から十九世紀にかけて、日本でも老猫が化けるという説は普遍的であった。
『本朝食鑑』には、
おおよそ雄の老猫は妖怪となる。その変化しかたは狐狸と変わらず、よく人を取って食う。俗にこれを「ねこまた」という。(抜粋)
『和漢三才図絵』には、
おおよそ十年以上生きた雄猫には、化けて人に害をなすものがある。言い伝えによれば、赤茶の毛色の猫は妖をなすことが多い。(抜粋)
と書かれている。さらに『耳袋』 巻四に狙っていた鳩を捕り損ねた猫が「残念なり」とつぶやく話が載っている。
これら近世の書物を見ると、『徒然草』に描かれたねこまたをベースにして中国からの影響を受けて猫の化け物が生れたことがわかるだろう。それを整理してみると、次のようになる。
- 年老いた猫は化ける、という認識
- 中国の金華猫からの影響
化かされたり取り憑かれたりするのは、チト困るが十年も生きると猫が「しゃべる」ってのは、見逃せない!昔はともかく今の猫は、十年ぐらい頑張れるから、これは老後に備えて猫を飼ってみるかな?大事に大事に育ててお互い年取ってから、縁側で熱いお茶でも飲みながら「今日もイイ日だったねぇ」というと「そうだにゃぁ~」とか言ってくれる。ほのぼのとした日常ですね!あ、ダメだ。あいつは猫舌だった(猫だけにね)。(つくジー)
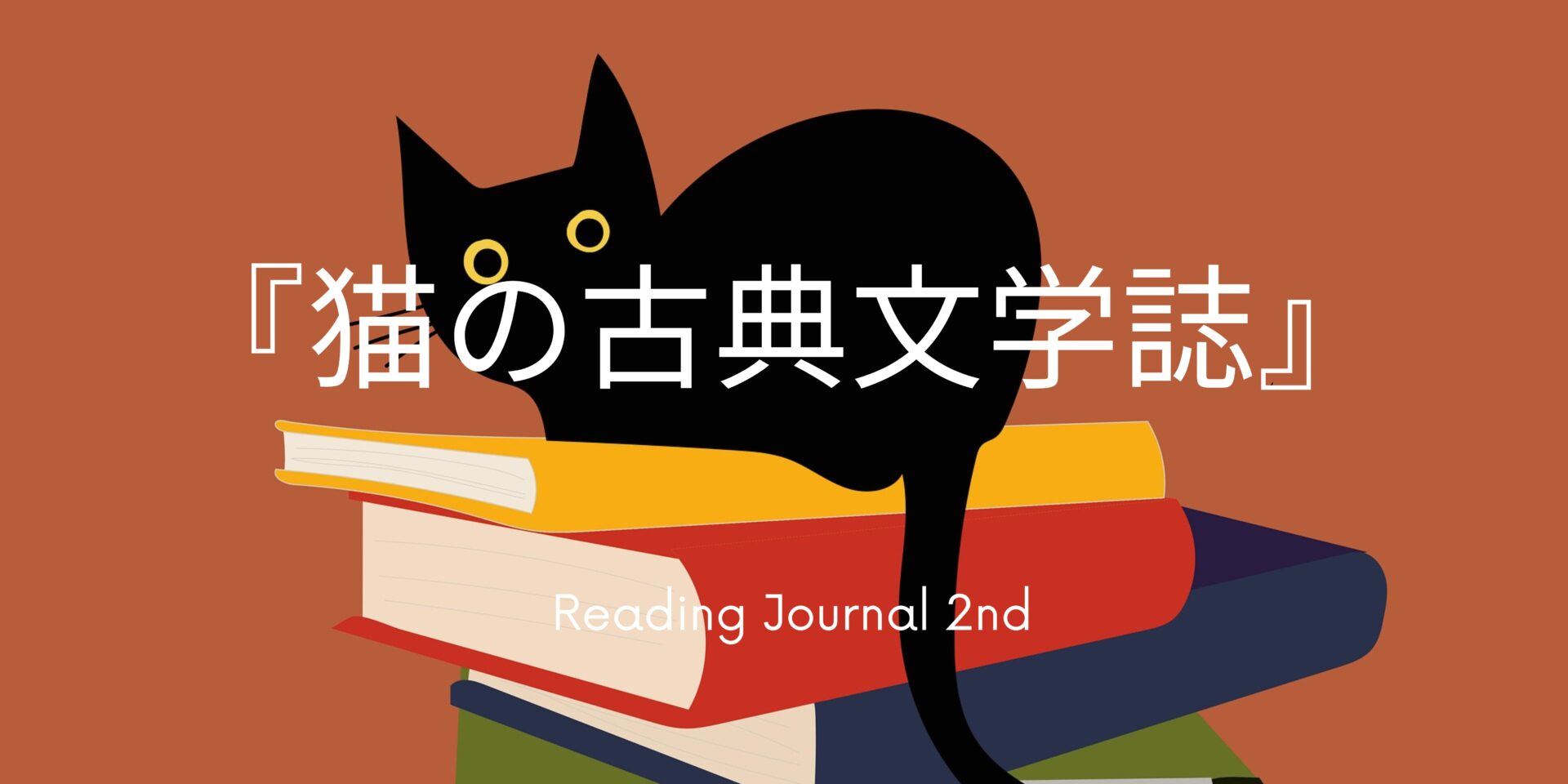


コメント