『猫の日本文学誌』 田中 貴子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第一章 「猫」という文字はいつごろから使われたか
さて今日のところは「「猫」という文字はいつごろから使われたか」である。日本の文献にあらわれた猫は、最初「狸」の字をネコと訓せている。この「狸」からはじまる「猫」のルーツ探しは、中国に渡り、さまざまなネコの話が語られた後に鼠との関係から「猫」なる文字が出来たことが分かる。そして、さらに猫と蝶の関係、虎より猫が偉かった件などの話が披露されている。それでは、読み始めよう。
狸を猫と訓む
日本の文献に「猫」が初めて記述されたのは、九世紀の仏教説話集『日本霊異記』である。しかし、ここでは、「狸」と書いて「ネコ」と訓ませている。
現代人のイメージでは、どうも「狸」と「猫」が同類であるとは思えないのである。もちろん狸はイヌ科ではあるが、その成体は猫ほどの大きさになるし、顔が尖っているところを除けば、後ろから見た限りでは猫に似てなくもない。『日本霊異記』があえてこの「狸」字を用いているのには、何か訳があるのだろう、と思わざるを得ない。(抜粋)
そして著者は、平安時代から室町時代につくられた辞書に当たる。
『新撰字鏡(八九八~九〇一)』:「狸、力疑反猫也。似虎小。亡交祢古」(ちゃんと「狸」は「猫」也と書いてある。「祢古」はネコの万葉仮名で読み方も書いてある。「狸」=「猫」は一般的ということを意味する。「猫」の項目はない。)
『本草和名』(九二三):「家狸、一名猫、和名祢古末。」(「猫」の項目が現れる。「家狸」とあるからすでに猫を飼う習慣が広まっている。)
その後、『康頼本草』(九八四~九九五)、『類聚名義抄』(一〇八一以降)、『伊呂波字類抄』(一一八〇)と辞書を探っていく。
これらの辞書の記述をまとめてみると、平安初期には「狸」を「ネコ」と訓むのが一般的で、それ以降も漢字のうえで混同があり、十二世紀頃には「狸」は野性の猫、「猫」は家で飼われている猫、といった区別がつけられるようになったと考えられる。(抜粋)
そしてその後、鎌倉・室町時代になると「猫」は猫を表わし「狸」の用語は出て来なくなる。さらに
『下学集』:「猫は毛色が虎ににていて、そのため世俗ではこれを「於兎」と呼んでいる。猫は「於兎」と呼んでやると喜ぶ。」(「於兎」は虎の別名『塵添壒囊鈔』。狸よりも虎との共通点が出てくる)
『壒囊鈔』「狸を「タタケ」、「子コマ]」と訓み、これは猫と同じである。猫は「ネコ」と訓むべきである。(中略)猫と狸は明らかに同類である。(猫と狸と同類なので混ざったという論理)
中国での猫と狸
ここで「猫」と「狸」の混同が平安初期に起こっていることから、これらは中国からの輸入文字と考え中国での状況を調べると、中国では「猫」を「狸」と書くことが当たり前であった。
日本の平安時代にあたる中国の宋時代の詞には、猫をうたったものが多くあり、猫は穀物をあらすねずみ対策に用いられていることがわかる。また、猫がすでに「我が家の一員」とされている様子もわかる(今村与志雄『猫談義』東方書房、1986年)。
『日本霊異記』が「狸」に「ネコ」と訓を宛てているのは、日本に中国の言葉が入っていたからなのだ。日本ではその後「猫」という文字をつかうようになるが、中国では(今でも)猫を「狸」と表記していることが多いのである。(抜粋)
「猫」の文字の由来
中国の陸佃(一〇四二~一一〇一)が書いた『埤雅』という辞書に次のような一文がある。
猫 鼠はよく苗を害するが、猫は鼠をとらえて苗の害を除去する。だから、猫という字のつくりは苗なのである。(抜粋)
これが、「猫」の文字の由来である。そして、中国でも「猫」の字は使うが、辞書にわざわざ字の成り立ちを説明していることより、中国ではあまり一般には「猫」の字は通用していなかったと想像される。
猫とねずみ
古来より高度な文明を持つ地域では、猫は人間にとって重要な役割を果たしていた。特に猫の長所として「ねずみ捕り」が常にあげられる。
猫がねずみから守るものは、穀物や書籍のほかに蚕があった。中国ではすでに紀元前から養蚕家には猫は欠かせないものであった。そして養蚕を行う日本でも猫はねずみ退治に重宝される(平岩米吉『猫の歴史と奇話』、築地書館、一九九二年)。
また歌川国芳の「鼠よけの猫」に代表されるように、猫の絵を描いて張っておく風習が各地にあった。(落合延孝『猫絵の殿様』、吉川弘文館、一九九六年)
また、イギリスではかつてウイスキーキャットという「働く猫」が、ウイスキー会社にいいて、猫も労働者として組合に入れるようになっていたところがあった(C.W.ニコル『ザ・ウイスキーキャット』講談社文庫、一九八七年)。
中国の猫の影響
猫と蝶
ここで、もう少し中国の猫が日本に与えた影響について述べられている。一つは「蝶を追う猫」である。しばしば漢詩文や絵画に「蝶を追う猫」が登場するが、四十年以上に渡る著者の猫とのつき合いで、実際の猫が蝶と格闘するという経験が無かった。
この猫と蝶の組み合わせによる画題は、中国で生まれた長寿を願う縁起の良いが代である(板倉聖哲「伝毛益筆蜀葵遊猫図・萱草遊狗図をめぐる諸問題」『大和文華』100号、一九九八年)。中国では、猫は七十歳を意味する「耄」、蝶は八十歳を意味する「耋」に発音が通じ、合わせて「耄耋図」という画題になった。
同様に猫が牡丹の下で眠る画題は、「猫・蝶・牡丹」で「富貴と長寿」を表わした。
しかし、日本では長寿を意味する組合せという意識は薄れていった(藤原重雄『史料としての猫絵』、山川出版社、二〇一四年)。
猫と虎
猫は「於兎[おと]」(ココ参照)とつまり「乙」=「小さいもの」と呼び「虎の小さいもの」という考え方がある(『塵添壒囊鈔』)。これは中国の説による。そして、中国では、猫は虎の舅(中国では「義父」でなく「叔父」のこと)であるとされ、虎よりも偉い。
さらに黄漢の『猫苑』によると、猫は虎の師匠であるという。
世俗では、猫は虎の師であるという。(中略)虎は、猫が機敏ですばしっこいのを羨み、猫に師事したちと頼んだ。まもなく、虎は猫そっくりに振るまえるようになったが、樹に上ることと、頸を回して物を見ることだけはできなかった。そこで、虎はこのことで猫に文句を言った。すると猫はこう答えた。「君は同類に嚙みつくのがうまい。だから怖くてしょうがないのだ。この二つを伝授しなかったのは、私自身の安全の用意だ。もし残らず伝えれば、いずれは私も君の口から逃れられないだろうから」(抜粋)
「猫」はいつから使われた
最後に、本章の題名の「「猫」という文字はいつごろから使われたか」に戻る。まず少なくとも平安初期までは、「猫」は「狸」と同じものという説が流布していた。これは、中国における表記が輸入されたためである。そして『日本霊異記』より後では、「狸」という表記はほとんど出て来なくなる。日本では、「ねずみ捕り」としての猫の受容が大きかったため、つくりが「苗」の「猫」の字が定着した可能性がある。
日本で平安初期では、中国の影響で、狸という字に「ねこ」と訓ませているっというのは、「そうなのかぁ」という感想だが、それよりも「中国では今でも「ねこ」を狸と表記していることが多い」って方がビックリって感じですね。それから、「猫」って漢字の由来も面白かった。これって世の猫好きの人たちに、自慢できますよね♪出典が示さるなんて最高ですよね♬
あと、猫が虎の先生ってものいいよねぇ~!そういえば『いなかっぺ大将』もニャンコ先生に教わってましたっけね。(つくジー)
関連図書:
今村与志雄(著)『猫談義』、東方書房、1986年
平岩米吉(著)『猫の歴史と奇話』、築地書館、1992年
落合延孝(著)『猫絵の殿様』、吉川弘文館、1996年
C.W.ニコル(著)『ザ・ウイスキーキャット』、講談社(講談社文庫)、1987年
板倉聖哲(著)「伝毛益筆蜀葵遊猫図・萱草遊狗図をめぐる諸問題」『大和文華』100号、1995年
藤原重雄(著)『史料としての猫絵』、山川出版社、2014年
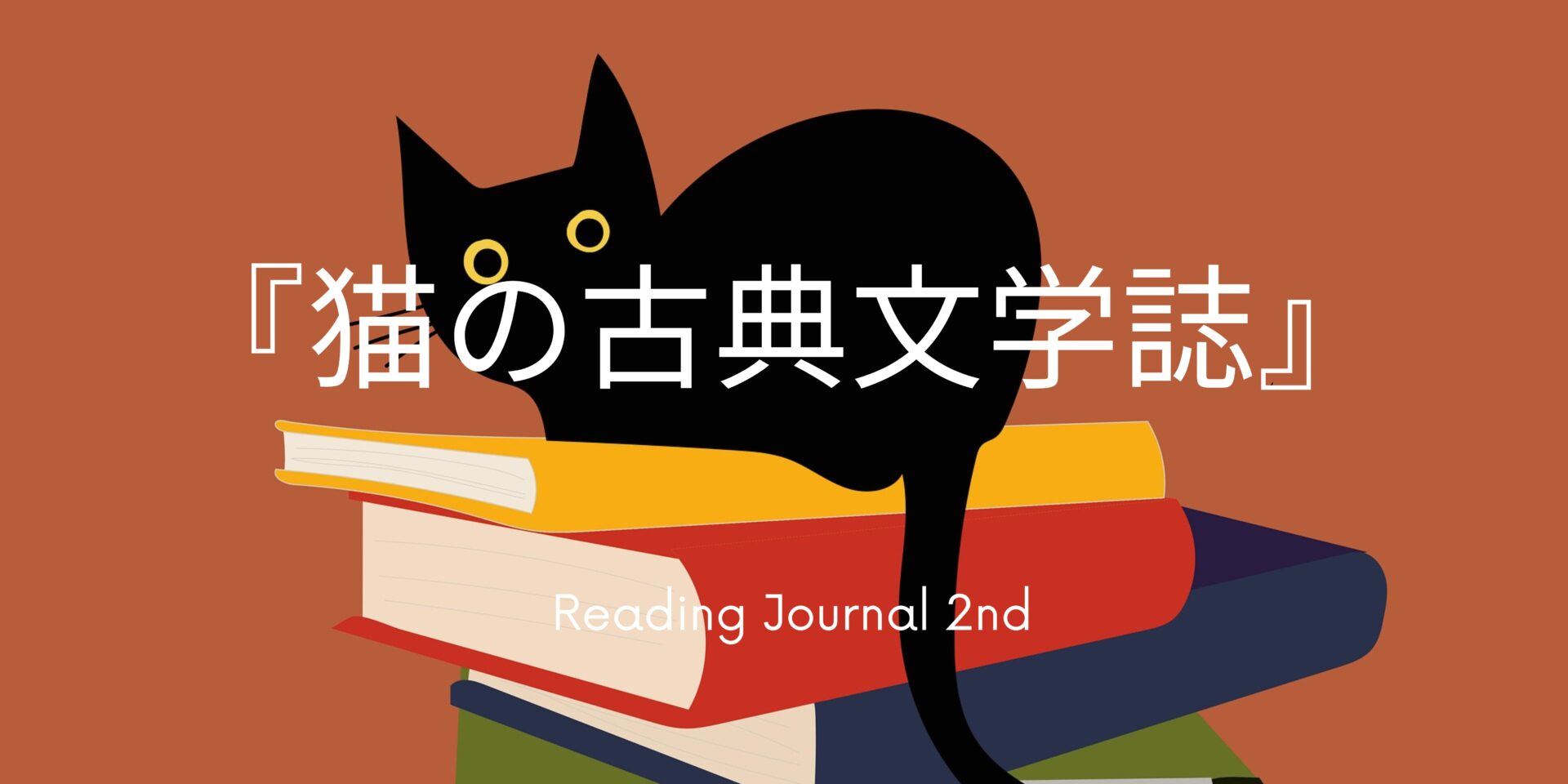


コメント