『宮沢賢治 久遠の宇宙に生きる』 北川前肇 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第6回 「デクノボー」として生きる(後半)
今日のところは、第6回“「デクノボー」として生きる”の後半。前半では、賢治の発病と、「雨ニモマケズ」の詩を法華経という観点から分析した。それを受けて後半では、賢治の臨終の様子と賢治の遺言で行われた『国訳妙法蓮華経』の出版についてである。
賢治の辞世の句
昭和八年は、数年前からの不作凶作とは打って変わって、岩手県史上最高の大豊作の年であった。そして、稗貫の氏神である鳥谷ヶ先神社の例祭も大盛況となる。賢治はこの祭りを見るために裏二階の病床から店先に出て、しじゅう楽しんでいた。
そして祭りも終わった九月二十日に賢治の様態が急変する。
ここで父・正次郎は、最悪の事を考え、死に臨むうえでそれを受け入れる不動心を確認するために、賢治と語り合う。そして賢治は辞世の句として短歌を二首墨書する。
方十里稗貫のみかも 稲熟れてみ祭三日 そらはれわたる 病のゆゑにもくちん いのちなり みのりに棄てば うれしからまし(抜粋)
一首目は、稗貫の大地に、稲が豊かに稔り、感謝の祭礼も真っ青な快晴のなかでとり行われた、いう意味であり、二首目は、病魔によって終わりを迎える私の命。この命を大地に生きる人の「稔り」のために捧げることができるならば、私にとって無上の喜びです、という意味である。
この二首は、賢治の観念の世界ではありません。私たちが生きる世俗の世界の中にあって、自覚的に法華経の世界を選び、意識して土性学を学び、献身的に生き抜き、そして疾風のごとく過ぎ去ってゆく、賢治全生涯の歩みを的確に表現していると受けとめられるのです。(抜粋)
賢治の死と『国訳妙法蓮華経』
九月二十一日、主治医は賢治の容態がこれまでと異なると診断する。
そして午前十一時半、突然、「南無妙法蓮華経」と高々と唱える声がした。皆が驚いて二階へあがると、賢治は喀血し顔面は青白くなっていた。父・正次郎は、末期が近いと直感し、賢治の遺言を聞き取ることにする。
賢治は、『国訳妙法蓮華経』一千冊の発行と配布を父に依頼しました。(抜粋)
当時、経典を印刷して配布することは、「布施行」として広く行われていた。正次郎はそれを快諾し、そのほかに言いたいことはあるかと問いかけると、賢治は「あとで起きて書く」と答えた。そして、午後一時三十分に賢治は亡くなる。
賢治の葬儀は、二十三日に宮沢家の菩提寺・案浄寺で行われた。ここで著者は、この時の弔辞が特に美しく感動的であると全文を引用して解説している。そして次のように言っている。
つまり、弔辞を捧げた友人たちは、次のように追慕しているのです。賢治は、み仏の世界、真理の世界、そして真に幸福の世界から、自分たちのいる日常の世界へと降り立ったのだ。彼は三十七年間、私たちとともに世俗の世界にあったが、その役割を終えて、またみ仏の世界へと還ってゆかれたのだ、と。 そして、賢治が真理の世界の人であるとするならば、彼の全作品は五十年後、百年後に正しく受けとめられると予言するのです。(抜粋)
そして翌年『国訳妙法蓮華経』が一千部刊行された。その和訳の底本としては、賢治が初めて触れた法華経である。島地大等著『漢和対照妙法蓮華経』が選ばれた(ココ参照)。この『国訳妙法蓮華経』の最後に賢治の言葉と弟・清六の言葉が記されている。
合唱 私の全生涯の仕事は此経をあなたの御手許に届けそして其中にある仏意に触れてあなたが無上道に入れん事を御願ひするの外ありません 昭和八年九月二十一日 宮沢賢治
以上は兄の全生涯中最大の希望であり又私共に依託せられた最重要の任務でありますので、今刊行に当りて謹んで兄の意志によりて尊下に呈上致たします 宮沢清六(抜粋)
著者は、この「皆様がみ仏の心に触れて、その真理の世界に参入してほしい」という願いは、十八歳の時に「如来寿量品第十六」を読んで感動した時(ココ参照)と同じであろうと言っている。
そして著者は最後に、この巻末の言葉に込めた賢治の心を次のようにまとめている。
久遠のみ仏は、間断なく大慈大悲の心をもって、私たちのことを思い続けておられます。どのような方法をもってしてもみ仏(私)が到達している最上の真理の世界へと私たちを導き入れ、ただちに仏心を完成せしめたい、と。 つまり、賢治の言う「仏意」とは、久遠のみ仏の誓願なのです。そのみ仏の誓願に触れて、人々が最上のさとりに入ることのみを願い続けているというのです。弟・清六は「そのことにみが、兄の生涯三十七年を貫く大切な願いである」と明言しています。(抜粋)
やっと読み終わった。この本は、はじめにのところで書いたように、松尾剛次の『日蓮』の導入が「雨ニモマケズ」の詩から始まっていて、それで興味が出て読んだのでした。とくに宮沢賢治のファンでも無いしなぁどうかな?と思ったが、面白かった。『日蓮』の中で折に触れて解説された「法華経」の知識も理解に役立った。
賢治の童話、童話作家としての賢治だけでなく、賢治生涯の全体が、ある意味「法華経」の影響を受け、賢治は菩薩行としての生き方をしていた。そういう人生だったのだと思った。(つくジー)
[完了] 全14回
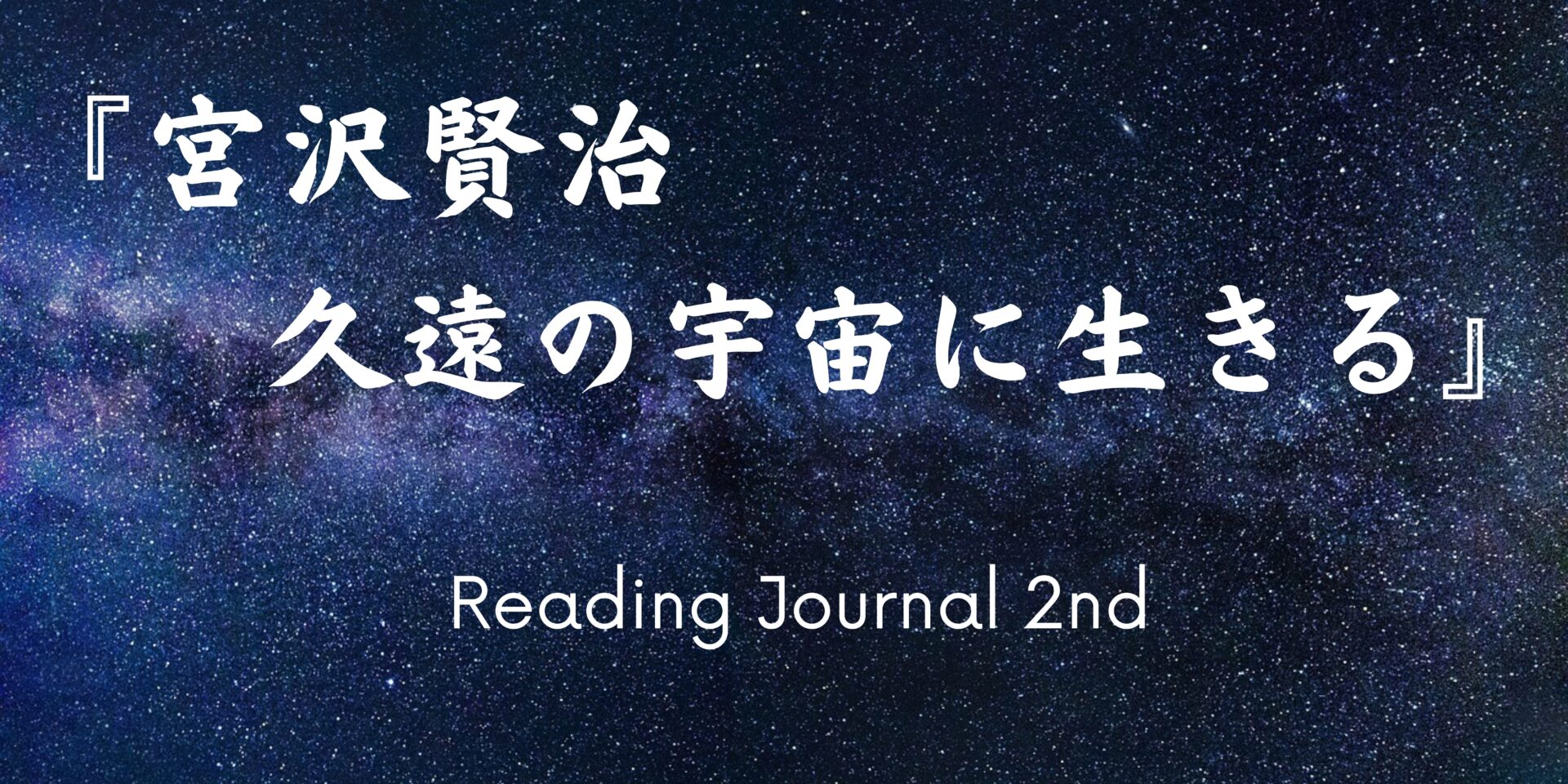


コメント