『宮沢賢治 久遠の宇宙に生きる』 北川前肇 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第6回 「デクノボー」として生きる(前半)
ここから、第6回“「デクノボー」として生きる”に入る。第5回(前半、後半)では、自ら農民となり花巻後に理想郷を築こうと奮闘する宮沢賢治の姿を追った。しかし賢治は無理がたたったのか両側肺浸潤で入院してしまう。第6回は、有名な「雨ニモマケズ」の詩に込められた賢治の願いを読み解きながら、病床にあった賢治の最晩年を取り上げている。第6回は前半で「雨ニモマケズ」手帳とその詩について、後半で、賢治の臨終とその遺言についてまとめることにする。
発病と二通の遺書
宮沢賢治は、昭和三年の夏に両側肺浸潤で入院する。その後退院はするが体調は優れず昭和四年になっても闘病生活が続いた。闘病中の賢治のもとに、東北砕石工場主の鈴木東蔵が、石灰の肥料としての効力について指導を受けようと訪ねてくる。その後書簡でのアドバイスが続いて行く。そして、体調が快方に向かっていた賢治は東北砕石工場の技師として任用された。
賢治の技師としての足跡をたどってみると、寝食を忘れるほどの忙しさで、行動範囲は秋田、岩手、宮城、茨城、東京までおよびました。まさに東奔西走、粉骨砕身の日々を過ごした賢治の驚異的な行動力は、若き日の稗貫郡の土地調査にあたったときと、同一のように感じられてなりません。(抜粋)
昭和六年九月十九日朝に賢治は東京に出張し、翌日の夜、旅館・「八幡館」で激しく発熱した。この時死を覚悟した賢治は二通の遺書を書いている。
この二通の遺書は、九月二十一日付で、賢治の死後、「雨ニモマケズ」が書かれていた手帳と共に発見された。
一通は、両親に当てたもので今までの行いを自分の我慢(=自己に執着しておごり高ぶること、慢心)のためであるとし、両親への御恩は、来世もその次も人間に生まれ変わりつづけることで報いたいと言っている。
そして最後に、どうか信仰に基づかなくとも「南無妙法蓮華経」と唱えて、私賢治を呼び出してください、その題目の中に、私のお詫びの言葉を託します、と結んでいるのです。(抜粋)
賢治は、題目を生者と死者をつなぐ大切なきずなと受け止めていた(ココ参照)。
もう一通は、弟と妹たちに宛てたもので、兄としての責任を果たすことなく迷惑ばかりかけたことを詫び、許して欲しいという内容である。
「雨ニモマケズ」と「雨ニモマケズ」手帳
賢治の死後に一冊の手帳が発見された。有名な「雨ニモマケズ」の詩が書かれているため「雨ニモマケズ」手帳と呼ばれている。この手帳は、病床にあった昭和六年十月上旬から昭和七年一月頃まで使用されていたと考えられる。そして「雨ニモマケズ」の詩は、その日付から二通の遺書を書いた五〇日後である。
野原の松の林の陰の小さな小屋に住み、病気や人や疲れた人、死にそうな人や争っている人がいれば、東西南北、どこにでも行って助ける。その姿は、貧しい農村で必死に奉仕活動をしていた賢治そのもののように思えます。(抜粋)
著者は、賢治はこの詩に書かれているような生き方を実践していた。そしてその生き方は、素晴らしい生き方と共感できる、としている。
しかし、「デクノボー」という箇所は、どうだろうか?それが素晴らしい生き方と共感できるでしょうかと疑問を呈している。そして、その内容を「賢治の法華経信仰」という側面から解釈してみたいとしている。
そのためにまずは、「雨ニモマケズ」手帳の他の部分に目を向ける。
この手帳の最初のページは、「道場観」が記されている。道場観は「如来神力品第二十一」に示されているものである。この経文は私たちが生きている娑婆世界が、み仏の浄土であると肯定し、娑婆世界をみ仏とともに修行する場所と受け止めている。それゆえに、祈りの儀式の最初に、唱える。
そして次のページには、大曼荼羅の中心部を略式で書かれている。それは中央に「南無妙法蓮華経」と書かれその両脇には地涌の菩薩を代表する「四大菩薩」の名が書かれている。
このように手帳の冒頭に着目すると「雨ニモマケズ」手帳は、病床にある賢治が「み仏とともにある」という自身の宗教的境地を記したものと見なすことが出来る。さらに、「雨ニモマケズ」の詩の次のページには、大曼荼羅の中心部分が七行に渡って書写されている。
これは略式の本尊であり、み仏によって法華経の教えが説かれて、すべての人が救済されている情景を示しています。つまり、これを書くことで、賢治は永遠のみ仏の前に、今まさに頭を垂れている、祈りを捧げているように受け取れるのです。そのように解釈すれば、「雨ニモマケズ」の詩は、賢治の祈りであり、そして仏に対する報恩感謝と新たなる誓であると言えるのです。(抜粋)
そして、「雨ニモマケズ」の詩は、賢治の理想とする生き方、このような人に成りたいという願いで終わっている。
ミンナニデクノボートヨバレ
ホメラレモセズ
クニモサレズ
サウイフモノニ
ワタシハナリタイ(前掲『全集』6巻)(抜粋)
著者はここで、この「デクノボー」という生き方は、法華経に描かれる常不軽菩薩に重なると言っている。常不軽菩薩は、人々が「必ず成仏する尊い存在」であると云い、他者を敬い礼拝した。そして、ののしられ、杖や石やかわらで打ち叩かれても、ひるむことなく修行を続け、ついには成仏した。「雨ニモマケズ」手帳には、この常不軽菩薩の姿を思わせる記述が、添削されている箇所もある。
みずからをかえりみることなく、ただ他者の真の幸福を願い、さとりの境地に到達することを祈る。また、いかなる誤解や批判やののしりを受けたとしても、妙法を敬い、お釈迦様の敬う心をもった常不軽菩薩。賢治もこの菩薩のような生き方を実践し続けたのです。それゆえに、賢治は「デクノボー」と呼ばれることを恥じないのです。むしろそうありたい、と積極的に願うのです。(抜粋)
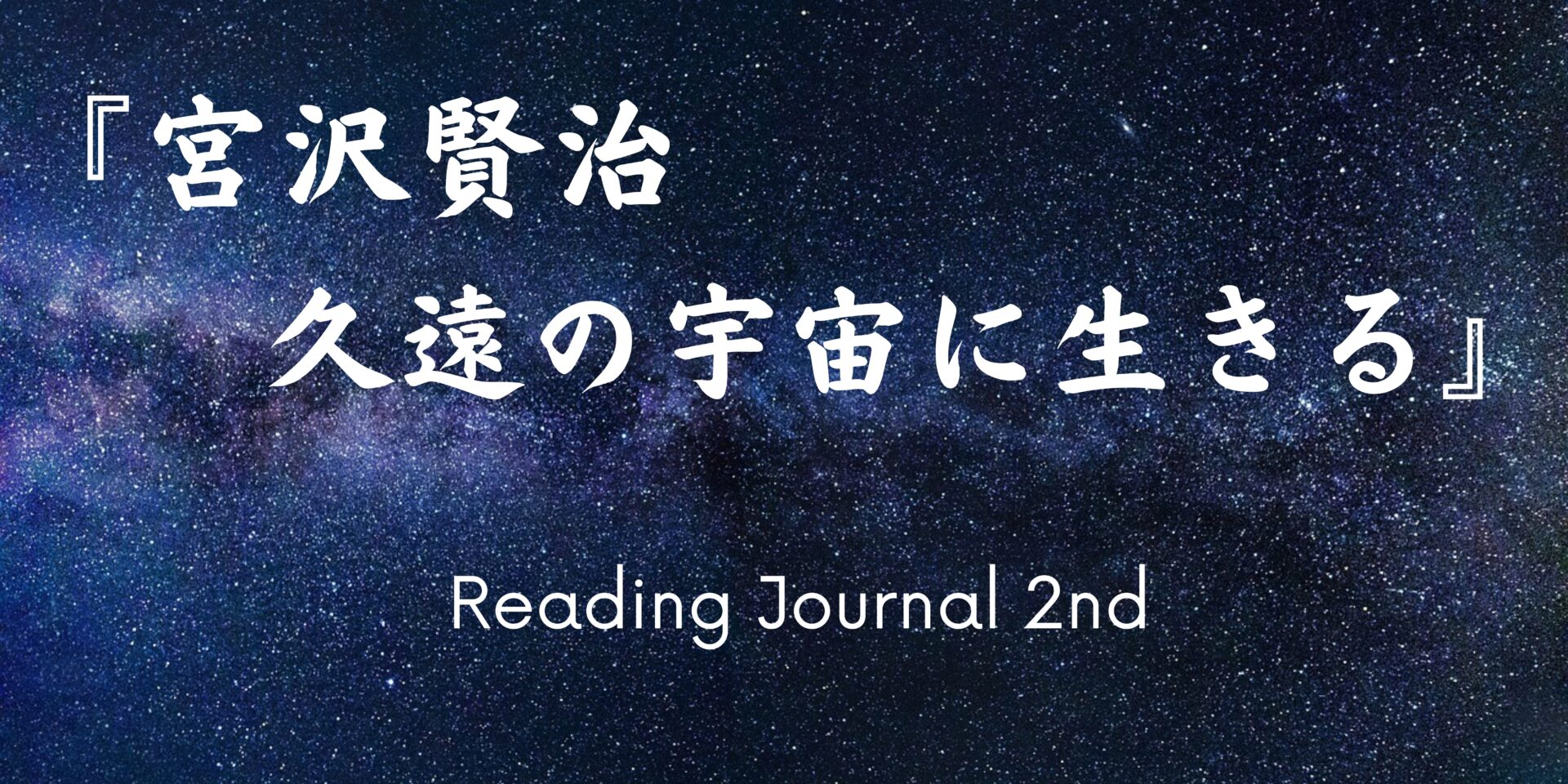


コメント