『宮沢賢治 久遠の宇宙に生きる』 北川前肇 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第5回 理想郷「イーハトーブ」の創造(後半)
今日のところは、第5回 “理想郷「イーハトーブ」の創造”の後半である。花巻農学校の教師を辞めた賢治(前半の最後を参照)は、いよいよ本当の農民となり、そこで「羅須地人協会」という理想郷「イーハトーブ」の拠点を作り、農業のみならず「農民芸術」をも実践していく。そこには、菩薩として生きるという賢治の思いがあった。
賢治の「イーハトーブ」と「羅須地人協会」
賢治は、大正十五年三月三十一日付で花巻農学校退職し、そして実家からトシの療養に使われた別宅に移り、自炊生活を始めた。家屋の傷んだ部分を自分で改築し、家から徒歩、ニ、三分の北上川付近の土地を開墾する。
賢治は故郷花巻に、農業の専門性を活用しながら、音楽や文学、演劇などを取り入れた新しい農村をつくろうとしていました。生活の中で芸術を実践する、いわば現実の「イーハトーブ」を実現しようとしたのです。(抜粋)
その活動は「羅須地人協会」と命名され、賢治はそこで教え子や知人そして地域の若い農家を招き、レコードコンサート、楽器の演奏、農学の講義や芸術論の講義などを行った。また、農家の人の求めに応じて、それぞれの田畑にあった「肥料設計」などを無償で行った。
そのような賢治をみて「金持ちの坊ちゃんの道楽だ」と揶揄する者もいた。たしかに賢治は父の資金援助をもとに高価な楽器やレコードを買っていた。しかし、彼は私利私欲のためでなく、地位の人々を救いたいという思いで奔走した。そしてそのためには「本統の百姓」にならなければならないというのが賢治の考えかたであった。
賢治には、自身が百姓になる以外に「教師として人材育成にあたる」という道もあり、賢治自身にも葛藤があった。しかし、卒業生の多くはエリートであり実際には農業を営むよりも高給をもらえる企業や役所に就職をしてしまう。そして賢治は裕福な商家で育っている自分が、彼らに「農村に戻れ」「土にまみれて生きなさい」という資格はないと思った。そういう思いから教員を辞めて「本統の百姓」になるしかないと決意した。著者は、賢治の気持ちをこのように推察している。
賢治の生き方と菩薩
著者はこのような賢治の生き方は、仏教における「菩薩」を思い起こさせると言っている。
「菩薩」とは、「菩提薩埵」の略称で、仏になる前の最終段階の修行者のことである。もとは、お釈迦様が前世で到達した姿をいったが、大乗仏教が興隆すると、成仏するための修業する者すべてを菩薩と呼ぶようになる。そして、さらに偉大な仏の誓願と大慈悲に支えられて、みずから人々の中にあって、仏の誓願を継承し、救いの行動をとる人のことを指すようになる。
法華経の「従地涌出品」に、大地の下の虚空には、金色に輝く無数の菩薩が居住していて、そして仏の声にうながされて同時に湧き出てくる光景が描かれている。これらの菩薩は「地涌の菩薩」とよばれる。
三千大千世界の無限の大地から涌き出して、過去・現在・未来と衆生に教えを伝えていく。そんあ地涌の菩薩の生き方は、故郷の大地を活動の場所として、未来のために、みずから土を耕しながら芸術や学問、農業の技術を伝える賢治の生き方と重なると思うのです。(抜粋)
『農民芸術概論要綱』と菩薩行
賢治は「イーハトーブ」は、単に農業の知識だけでなく「芸術」も必要とすると考えていた。生活が貧しく、労働が厳しいからこそ、音楽や文学が生きる支えになる。そして、労働だけでなく、農民芸術を根付かせてこそ、花巻がイーハトーブ‐‐‐夢のような理想郷‐‐‐になると考えていた。その決意は、『農民芸術概論要綱』にはっきりと示されている。
著者はこの文章を引用して解説する。そして特に注目するべきは、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」であるとしている。この文章は、「世界中の誰もが不幸にならないような社会を目指そう」と言った道徳的な意味と捉えられがちであるが、著者はそうではないと言っている。
ここで重要なのは、賢治はそもそも「世界」と「個人」が別物だと考えていないということです。彼は、法華経の世界の無限の広がり、すなわち、「諸法実相」の真実の世界を、世界全体の幸福と捉えているのです。その調和のある真実に皆が目覚めない限りは、個々人の幸福がもたらされることはないと言うのです。(抜粋)
ここでは、諸法実相という一念三千の世界と、自己の存在を不二のものと捉えていて、世界全体の幸福と個々人の幸福は分かつことが出来ないことを強調している。そして、世界全体の幸福と私の幸福とが完全に一致すると考えている。
自己と社会、世界、あるいは宇宙の関連性を不二と捉えることは、「古い聖者の踏みまた教ヘた道」だと賢治は言います。(抜粋)
そして、その求道の中にこそ、真実の生き方があり、真理があるとしている。それはつまり「菩薩行」であったと言える。
『農民芸術概論要綱』の「結論」には、「永久の未完成はこれ完成である」(同前)という文章があります。この表現は、法華経における菩薩の生き方と重なります。みずから仏となることを目的とせず、永遠に他者を導き続ける。この「仏とならない」という菩薩の誓願が、「未完成」という表現と重なり合うのです。地涌の菩薩は、すでに久遠の仏によって導かれた菩薩であり、仏の子です。この仏の子であるという大前提によって、一見未完成であっても、仏とともに存在する、つまり「完成」と言えるのです。(抜粋)
賢治の病気と「羅須地人協会」の終わり
このように自分の幸せよりも周りの幸せを願い活動していた賢治であったが、現実の生活は、想像以上に苦しいものであった。そして、「羅須地人協会」の記事が、「岩手日報」に載ると、「社会主義教育を行っている」と批判される。賢治は誤解を避けるために楽団を解散し、集会も不定期にしている。
そして、そのような無理がたたったのか、昭和三年(一九に八)の夏に、両側肺浸潤で入院している。そして実家に帰り療養していたが、年末に肺炎を発症した。そして、羅須地人協会は復活することなく、賢治のイーハトーブという理想郷を作るという挑戦は未完成のまま終わってしまう。
宮沢賢治は、妙法蓮華経という真実の教えに出会い、謙虚に頭を垂れることで、「個人のみの幸福」の追求から離れることが出来た。そして、社会とどう関わるかという答えを、他者を導き続ける「菩薩行」の中に見つけた。
凡夫が凡夫のままで終わるのではなく、凡夫を仏の子として、菩薩として認識する。そして、菩薩としての使命を生きることの喜びを、彼は『農民芸術概論綱要』に思いのまま表現しました。だから私たちも、『農民芸術概論綱要』を読むとき、自分の全存在が仏法の真理に叶っていると思い、絶対的に肯定していると感じられるのです。(抜粋)
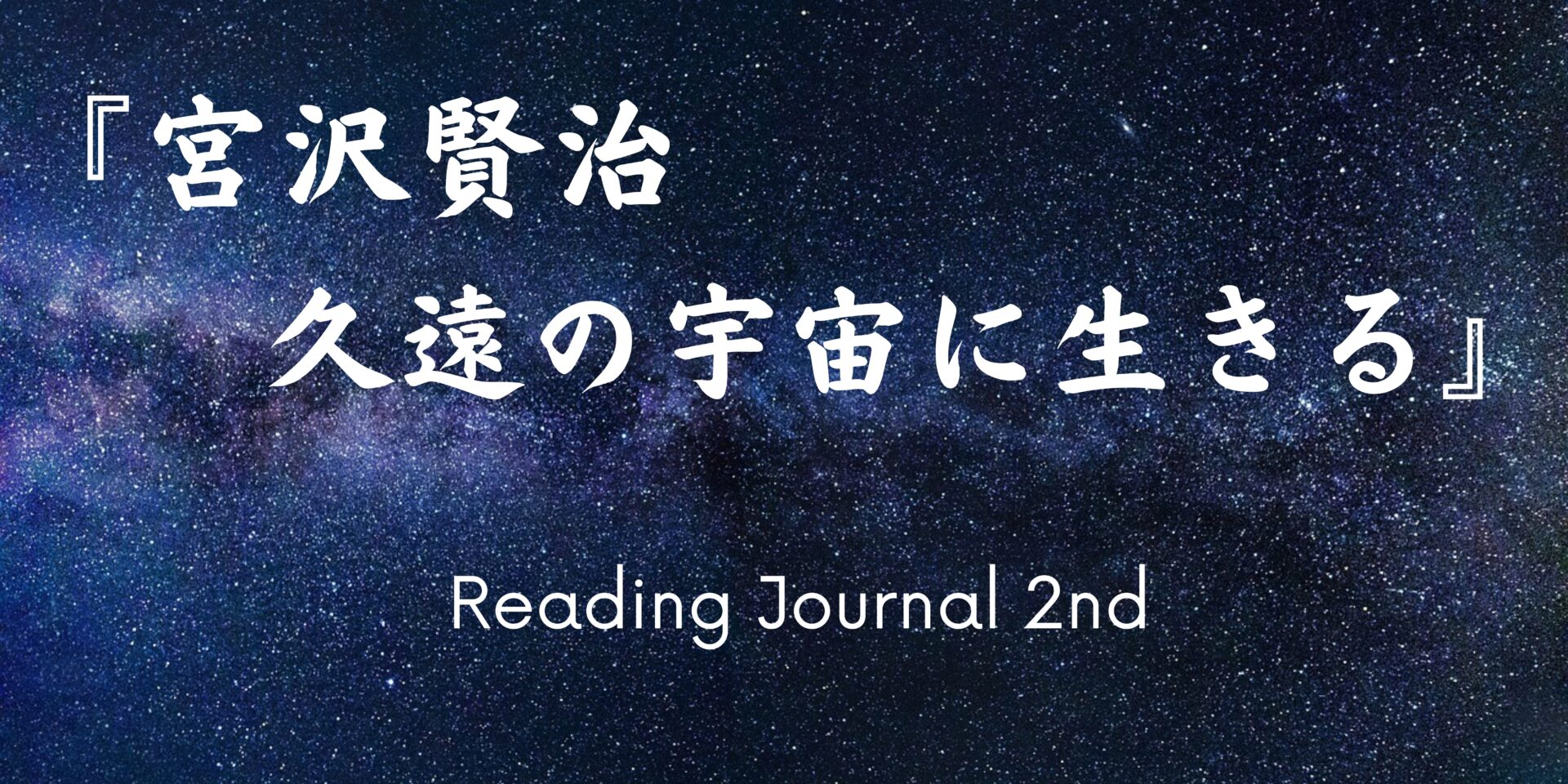


コメント