『宮沢賢治 久遠の宇宙に生きる』 北川前肇 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第4回 あまねく「いのち」を見つめて(前半)
今日のところから“第4回 あまねく「いのち」を見つめて”である。ここでは、最愛の妹・トシの死とそれを通して賢治の死生観を探っていく。第4回は、前半と後半に分けてまとめることにする。まず今日のところ前半では、妹・トシの死を、賢治の詩を通して語っている。また次回後半では、「死」の意味を法華経を通して捉えなおし、賢治の死生観に迫る。
宮沢賢治の二歳年下の妹、トシは、花巻高等女学校を優秀な成績で卒業し、大正四(一九一五)年四月に東京女子大学家政学部予科に入学する。そして、本科の卒業年次の大正七(一九一八)年十一月にスペイン風邪(インフルエンザ)にかかりさらに十二月に肺炎を発症して入院した。盛岡高等農林学校の研修生だった賢治は、母親と上京しトシの看病をする。そして三月上旬にやっとトシは退院し、実家に戻った。
しばらく静養したトシは、大正九年に、母校の花巻高等常学院の教師となる。
しかし、よく大正十年に、再び病状が悪化し、六月から病床に伏し、九月に喀血し、肺結核であることが分かった。その頃、東京で生活していた賢治は、トシの結核発病を電報で知り、帰京する。
その後、賢治は昼は稗貫農学校で教鞭をとり、夜はトシの看病をする。
そして大正十一年の十一月二十七日のみぞれの降る寒い日に、トシは二十四歳で亡くなった。
賢治の詩とトシの臨終
このトシの臨終の様子は、『春と修羅』に収録されている「永訣の朝」に描かれている。賢治はトシの最期を見守る中、「雨雪を取ってきて」と頼まれる。
けふのうちに
とほくへいってしまふわたくしのいもうとよ
みぞれがふつておもてはへんにあかるいのだ
(あめゆじゆとてちてけんじゃ)
青い蒪菜のもやうのついた
これらふたつのかけた陶椀に
おまへがたべるあめゆきをとらうとして
わたくしはまがつたてっぽうだまのやうに
このくらいみぞれのなかに飛び出した(前掲『全集』2巻)(抜粋)
ここでは、「あめゆじゆとてちてけんじゃ」(雨雪を取ってきてください)という方言が、妹を失う悲しさを引き立たせている。そして、その雨雪をトシにすくって食べさせ、詩の最後はこのように終わっている。
おまへがたべるこのふたわんのゆきに わたくしはいまこころからいのる どうかこれが天上のアイスクリームになつて おまへとみんなとに聖い資糧をもたらすやうに わたくしのすべてのさいはひをかけてねがふ(同前)(抜粋)
宮沢賢治は、『春と修羅』を出版後も修正を重ねた(宮沢家本)が、ここの「天上のアイスクリーム」の部分は「兜率の天の食」に修正されている。
この「兜率の天」とは、仏教における天上界の一つをさす。そして、ここには、将来仏になる菩薩が居住する宮殿があるとされた。そのため、日本では、この「兜率の天」を死者のおもむく安らかな世界として信仰した。
賢治は、はじめに「天上のアイスクリーム」と書いた部分を、あとから「兜率の天の食」と書き換えました。すなわちトシが死後におもむくであろう漠然とした「天上」を、より具体的に「兜率の天」と表記したのです。そしてアイスクリームというモダンな食べものでなはく、兜率天におもむいた無限の死者に対する供物として書き直したのもだと推察されます。(抜粋)
ここで著者は、トシと父・政次郎との会話に触れている。
父・政次郎は、二四歳で亡くなる娘が哀れで、「こんど生れてくるときは、また人なんかに生まれてくるなよ」となぐさめる。するとトシは
「こんど生れてくるたて、こんどはこたにわりやのごとばかりで、くるしまなあよに生まれてくる」(同前)(抜粋)
と答えた。これは、今度、生まれてくるときは自分のことばかりで苦しまないで、世の人のために役立ちたい、という意味である。著者は、このようにトシは「出来るだけ丈の大きい強い正しい者になりたい」と願う、向上心と利他心の強い女性であったと評している。
いよいよ妹の呼吸が止まりそうになったとき、賢治は急いで枕元に駆け寄り、耳元で「南無妙法蓮華経」と声高に唱えました。トシは二回ほどうなずくようにして、午後八時三十分、息を引き取りました。賢治は、押し入れに頭を突っ込んで大声で泣いたそうです。(抜粋)
このトシが死去した翌年に、賢治は花巻農学校の仕事を兼ねて、樺太に旅行した。そして、連作「オホーツク挽歌」を執筆する。著者はこの中の「青森挽歌」という詩に、気になる一説があるとしている。
あいつがいなくなってからあとのよるひる
わたくしはただの一どたりと
わいつだけがいいとこに行けばいいと
そういのりはしなかつたとおもひます。(同前)(抜粋)
著者は、ここでなぜ「ただの一度も、トシ「だけ」が良いところ、安らかな浄土へ旅立てばいいと祈ることはなかった」と書いたのかを問うている。
浄土真宗における「死」
宮沢家が信仰していた浄土真宗では、身内や先祖だけの追善供養をしない。それは、すべてのいのちは輪廻転生を繰返すため、あらゆる人がいつかどこかで家族になった事があると考えるからである。そのためすべての生命が親兄弟と同じようなものだから、自分の身内の成仏だけを願うのは道理に反するとされている。
実際、開祖の親鸞も『歎異抄』で「親鸞は父母の孝養のためとして、一返にしても念仏を申したること、いまだ候わず」(私は亡き父母の供養のために念仏をしたことは一度もない)と言っている。
また、浄土真宗では、衆生は、阿弥陀仏によって救われているのだから、死ぬことは恐ろしいことではなく、だから嘆くことではない、としている。
著者は、賢治の詩の「わたくしはただの一どたりと/わいつだけがいいとこに行けばいいと/そういのりはしなかつたとおもひます。」の部分は、明らかに『歎異抄』の影響があると指摘している。
しかし、それでは妹一人のために祈ったり嘆いたりすることは教えに反することになる。著者は、その矛盾を克服するために、「永訣の朝」において「ふたわんのゆき」を妹だけでなくすべての人の清い資糧にるようにと願ったのであると考えている。
宮沢賢治は浄土真宗から法華宗に改宗したのにも関わらず、意外なところに小さいころに親しんだ浄土真宗の影響があったわけである。
この部分はちょっとわかりづらいけど、「永訣の朝」の「ふたわんの雪」を「天上のアイスクリーム」⇒「兜率の天の食」と変えたところ、それから「青森挽歌」の「わたくしはただの一どたりと/わいつだけがいいとこに行けばいいと/そういのりはしなかつたとおもひます。」のフレーズに『歎異抄』、浄土真宗の影響があるというのが、著者の指摘である。
では、法華経ではどのように「死」をとらえているか!・・・後半につづく (つくジー)
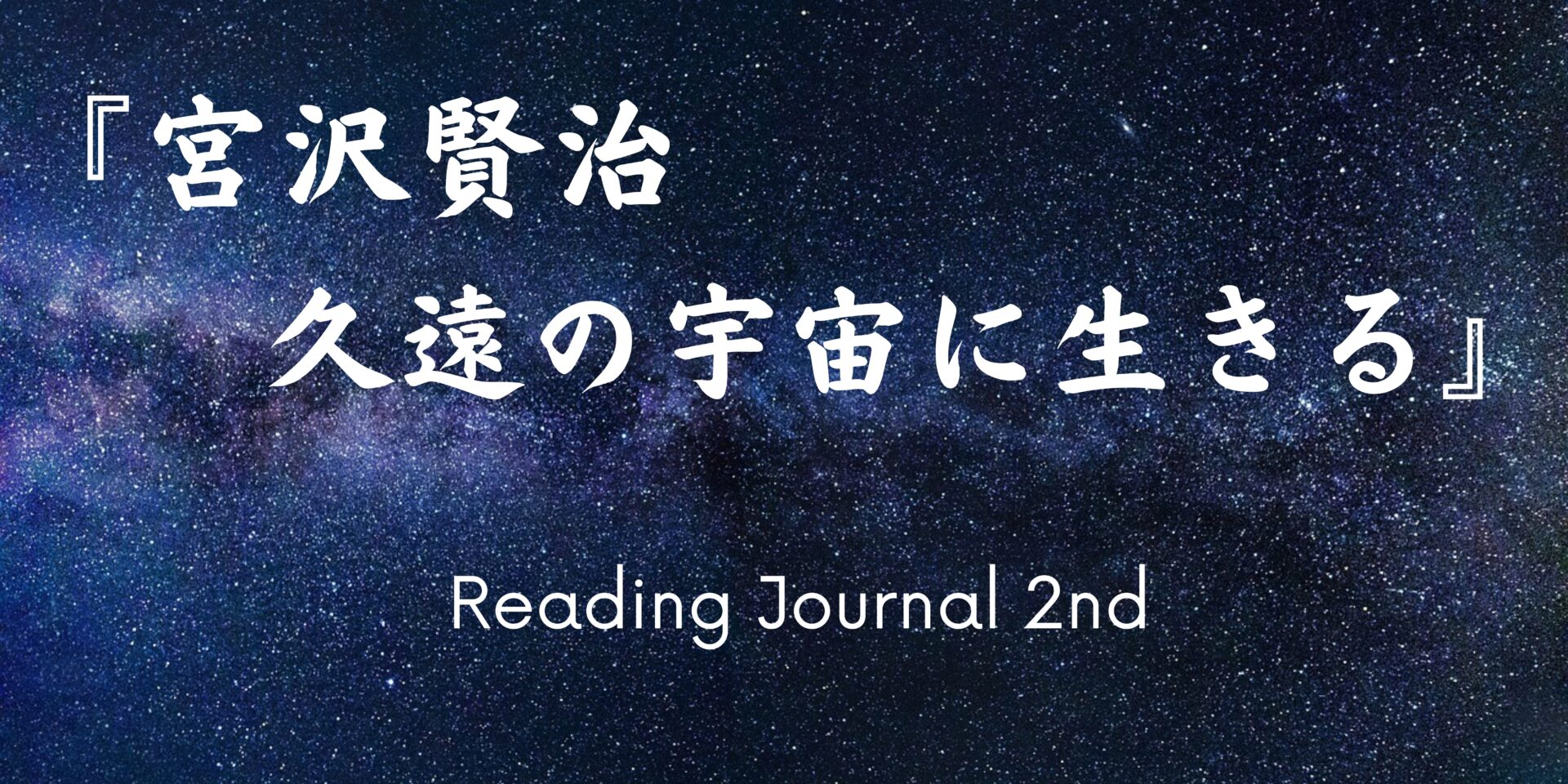


コメント