『宮沢賢治 久遠の宇宙に生きる』 北川前肇 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第1回 「法華経」との出会い(後半)
今日のところは第1回の後半である。ここでは、まず前半にある「赤い法華経」が賢治に渡るまでを、明治期の仏教改革という大きな流れの中で捉えている。その後に「法華経」に出会った後の賢治について、さらには、賢治は法華経のどこに惹かれたかについて書かれている。
仏教改革と赤い法華経
明治期には、島地大等のほかにも、仏教の改革を試みる僧侶が各宗派にいた。それは、明治政府の「神道国教化政策」への仏教間の危機感があった。明治政府は国家としてのアイデンティティを統一するために日本の宗教を神道に統一しようとした。そのため、仏教寺院の建物、仏像、仏具などを破壊する「廃仏毀釈運動」も起こった。
このとき、浄土真宗本願寺派の僧侶たちは、神道国教化に抵抗し、信教の自由や政教分離を政府に訴えました。活動の中心にいたのが、島地大等の義父・島地黙雷です。黙雷の尽力により、神道国教化は立ち消えました。(抜粋)
この黙雷と大等は、明治四十一年より盛岡仏教夏期講習会を開催していて、賢治も、盛岡中学校時代から高等農林時代にわたってこの講習会に出席している。
また花巻の大沢温泉での夏期講習会では、浄土真宗の僧侶である楠(和田)竜造、近角常観、暁烏敏、多田鼎などの高名な仏教者が招かれた。
また、江戸時代からたびたび飢饉に見舞われた東北地方には仏教界から支援があった。そして慰問の代表として暁烏が東北地方に滞在した時、高橋勘太郎との出会いがあった。
暁烏敏は、高橋勘太郎と通して宮沢正次郎とも交友し少年宮沢賢治ともつながっていた。
『漢和対照妙法蓮華経』は、そのような縁があり、島地大等から高橋勘太郎に送られ、そして、それが政次郎、賢治と渡っていく。そして、最後に賢治より盛岡高等農林学校で一年後輩の保坂嘉内へと届けられる。
このように、一冊の経本が賢治にとどけられるまでのいきさつを垣間見ると、暁烏敏、島地黙雷、島地大等、高橋勘太郎、宮本政次郎など、賢治を取り巻く当時の仏教改革の歴史が詰まっているかのようです。そう考えると、島地大等から高橋勘太郎に贈られた『漢和対照妙法蓮華経』を宮沢賢治が読んだことは、偶然でなく、歴史的必然だったのではないか、とさえ思われてなりません。(抜粋)
法華経への改宗
『漢和対照妙法蓮華経』に感動した賢治はその後、意欲的に勉強し、盛岡高等農林学校にトップの成績で入学する。そして、学内では『アザリア』という文芸同人誌を作る。
盛岡高等農林学校を大正七年に卒業した賢治は、念仏信仰と決別し、日蓮の遺文集や国柱会創始者の田中智学の著書を読み日蓮教学への理解を深め、大正九年に「国柱会」に入会する。
「国柱会」は、伝統的な日蓮宗から独立し、在家者を中心とし、人々の救済を目指す仏教改革運動を行い、法華信仰を伝道する団体である。
そして、賢治は父・政次郎などの家族に法華経への改宗を迫る。そして父とたびたび激しい口論となった。ただ、賢治の最大の理解者である妹のトシは賢治に同調し法華経に帰依する。しかしトシはまもなく病死してしまう。著者はこの妹・トシとの別れが賢治文学の核心をなす、としている(第4回を参照)。
ここで著者は、一般にはこの一連の信仰の変化を「浄土真宗から日蓮宗」への改宗と理解されているが、そんな単純な話ではないとしている。
天台大師智顗が体系化し、最澄が受け継ぎ、法然、親鸞、道元、日蓮などが学んだ天台教学。その天台教学を根幹として、日蓮が仏教の存在論、認識論を展開し、それが「南無妙法蓮華経」の題目に帰結するという捉え方は、賢治の生命観や存在論、宇宙論を考えるうえで、重要な哲学であると思うからです。(抜粋)
法華経のどこに惹かれたのか?
では、賢治はこの法華経のどこに惹かれたのか?著者は次のように推察している。
仏教は江戸時代の檀家制度のもと、形骸化していき、民衆の信心を失っていた。そして、既成教団の僧侶の一部が、旧来の仏教から脱却し、人々の苦しみと向き合う活動を始めた。
「人々の苦しみと向き合う」というのは、法華経と天台教学の根幹です。賢治は、法華経のそういう部分に心打たれたのだと思います。(抜粋)
しかし、賢治がなぜ父に改宗を求め口論までしたのかについては、宗教的な問題だけでなく「父との確執」が関わっているとしている(第2章を参照)。
ジョバンニの切符「銀河鉄道の夜」
この後、「銀河鉄道の夜」の主人公ジョバンニが持っていた切符に書かれた文字の話が挿入されている。
著者は、そのような仏教や法華経の影響が多くの作品に見て取れるとして、「銀河鉄道」から長文の引用をしている。主人公のジョバンニが切符の検札を受けるシーンであるが、その切符には「おかしな十ばかりの字」が書いてあった。そして、その文字が何かについて様々な推察がある。
その一人、ドキュメンタリー番組「宮沢賢治 銀河への旅」(NHK、ニ〇一九)の演出を手掛けた今野勉氏は、著書の中で、これこそが『漢和対照妙法蓮華経』の表紙に書いてあった「サッダルマ・プンダリーカ・スートラ」だと述べています(『宮沢賢治の真実』新潮社、二〇二〇)。(抜粋)
著者は今野の説を読んで、腑に落ちたとしている。この「サッダルマ・プンダリーカ・スートラ」・法華経は、み仏の真実智慧を有して、過去・現在・未来の時間を自由に旅行し、十法世界を貫く、み仏の自由自在のはたらきを示すお経であるからである。まさにジョバンニの「どこでも勝手にあるける通行券」なのである。
法華経のすばらしさ
では、法華経のどこがそれほど素晴らしいのか?と著者は改めて問う。そして、あえて一つだけあげるならばとして、
私たちが今生きているこの世界、すなわち「娑婆世界」を肯定しているところです。(抜粋)
としている。
平安時代末期は、戦や飢餓で荒廃し、世の中に「末法思想」が蔓延する。ここで、末法思想とは、仏法が滅尽し(白法隠没)、世の中が混乱する(闘諍堅固)という悪世である。
そのような時に「鎌倉仏教」という新しい宗教が生まれた。特に広く浸透したのが浄土思想である。
源信の『往生要集』に「厭離穢土 欣求浄土(この世(娑婆世界)を汚れた国土として厭うい離れ、西方の浄土を願い求める)」という言葉があるように、浄土宗や浄土真宗においては、阿弥陀仏の住む西方の極楽浄土に往生することが最大に救いとされた。
しかし法華経では、来世ではなく、今ここに住んでいる娑婆世界こそが「仏の世界」だとされています。そして、ただ今、この一瞬の時間の中で、永遠の時間が内包され、そのままで、み仏のすくいが成就[じょうじゅ]すると説くのです。往生するのを待つのではなく、今、ここで私たちは仏になることができるというのが、法華経、そして天台教学の根本思想なのです。(抜粋)
将来、進むべき道が見つからずに悶々としている賢治は、法華経と出会い、今生きている世界が永遠の仏の世界であると知り、自分の世界が肯定され、生きる意欲がわいたのではないかと、著者は指摘している。
この後、賢治は、花巻を理想の地と捉えて、地上の楽園をつくろうと奔走することになる(第5回を参照)。
日本の稗貫(花巻)の地から太陽系、銀河系、さらに宇宙の果てまで、自由自在に旅する宮沢賢治の精神性を裏付けるものはなんなのか。これから法華経を読み進めながら考えましょう。(抜粋)
関連図書:今野 勉(著)『宮沢賢治の真実』、新潮社(新潮文庫)、2020年
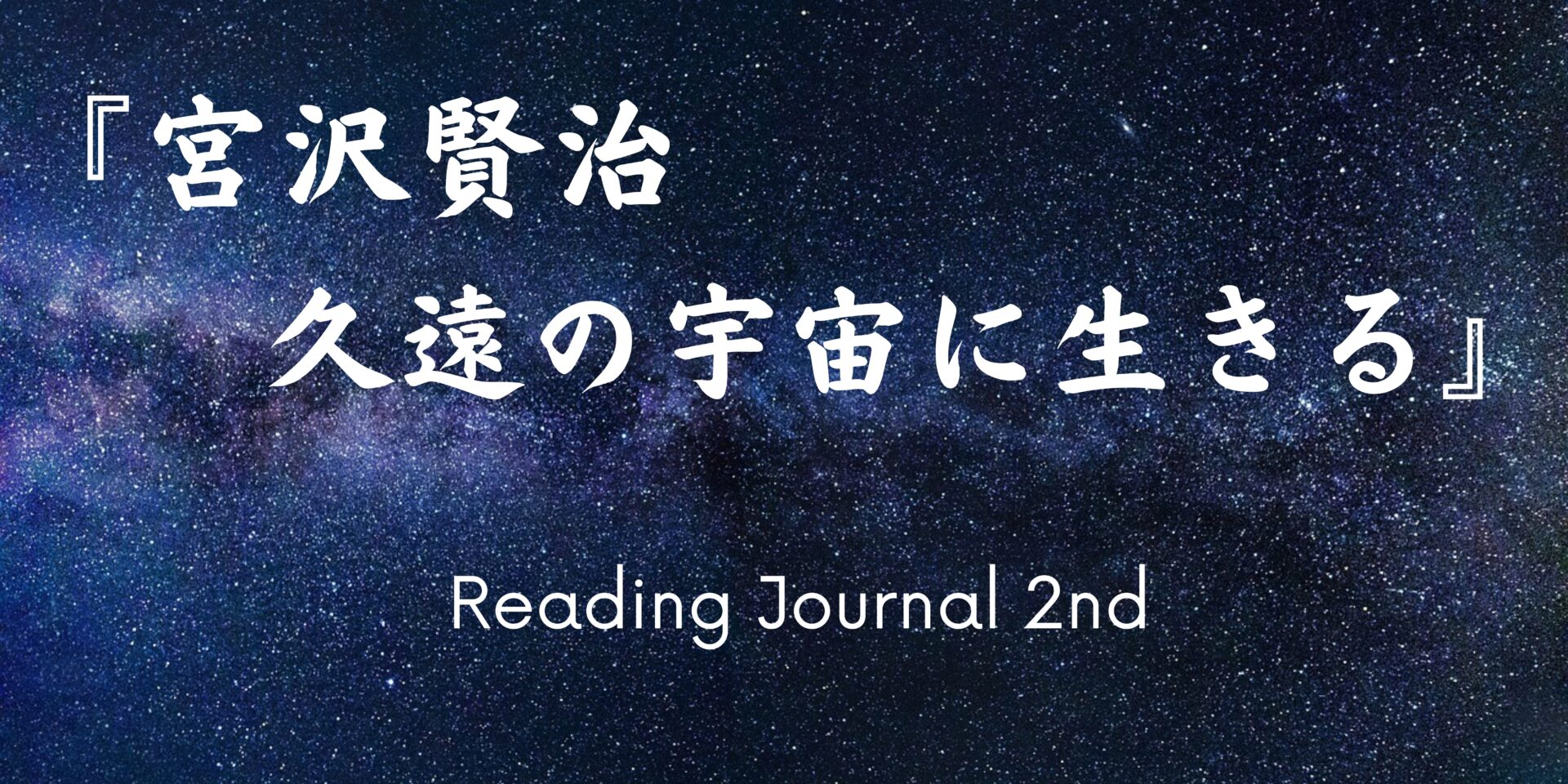


コメント