『宮沢賢治 久遠の宇宙に生きる』 北川前肇 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第1回 「法華経」との出会い(前半)
さて第1回「法華経」との出会い、から読み始めよう。読むにあたって各回を前半と後半に分けてまとめる事にする。今日のところ「法華経」との出会い、前半では、宮沢賢治の生い立ちから法華経に出会うまでを追っている。
法華経と出会うまで
宮沢賢治は明治後期から昭和初期にかけて、三十七年生涯を終えた。生前に刊行された著書はたった二冊だったが、その遺稿により、彼の作品は高く評価され、現在でも読み続けられている。
そんな健治の作品の背景には、仏教、とりわけ「妙法蓮華経」(法華経)というお経への信仰心があることが知られています。健治は幼い頃から仏教に親しみ、十八歳のときに法華経に出会いました。以後、生涯にわたり法華経を篤く信仰し、その教えに生きようとしたのです。(抜粋)
この信仰がもとで父との確執が生じるなどの心の葛藤も含めて健治作品に法華経との出会いは影響しているのは間違いない。そして、著者は本書の目的について、以下のように言っている。
健治が信奉した法華経とはどのようなお経で、作品にどう影響しているでしょうか。かれはなぜ、父との関係を悪化させてまで、法華経を侵攻したのでしょうか。
これから少しずつ、答えを探っていきたいと思います。(抜粋)
宮沢賢治は、明治二十九年、岩手県稗貫郡里川口町(現・花巻市豊沢町)で、宮沢政次郎とイネの長男として生まれた。生家は、質店と古着商を営む豊かな一家であった。
宮沢家は、浄土真宗大谷派の門徒で、賢治は、幼少より叔母のヤギから『正信念仏偈』や『白骨の御文』を聞かされて育った。
賢治は、六歳の時に赤痢にかかり、隔離病棟に入院した。以後、ずっと胃腸の弱さに悩まされていた。著者は、この悲劇が、賢治の心に生涯暗い影を落とすことになった、と言っている。
そして、八、九歳になると父が運営に関わっていた大沢温泉の仏教講習会に参加するようになる。この講習会は毎年夏に開催され、講師として各宗派の僧侶が呼ばれた。
花巻川口尋常高等小学校の五・六年では、鉱物や植物の採集に熱中する。そして仏教への関心も深まり、仏教講和を聞きに行ったり、盛岡の報恩寺で禅の修行をした。
中学校を卒業したばかりの十八歳の春に、賢治は肥厚性鼻炎の手術のため入院した。十日ばかりの予定だったが、疑似チフスにかかった疑いがあり、一か月半余りの入院となった。退院後、同級生の多くが進学したが賢治は家業を継ぐように命じられ鬱々とした日々を過ごす。
日ごとに元気がなくなる息子の姿を見て、政次郎はついに、盛岡高等農林学校の受験を許可しました。九月頃のことです。大好きな鉱物や植物の勉強ができることになり、賢治は将来への夢が広がったことでしょう。(抜粋)
そして、同じころに賢治は、父と同一の信仰を持つ高橋勘太郎から送られた赤い表紙の法華経の本を読み、強い衝撃を受けた。
浄土真宗の島地大等が編輯した本で、その「如来寿量品」を読んだ時、特に感動し、後にその感激を「太陽昇る」と書いている(宮沢清六『兄のトランク』筑摩書房、一九八七)。
進学の希望が叶い、さらに法華経というよりどころを得た賢治、彼はここから自分の生きるべき道を歩み始めたのです。(抜粋)
法華経とは
ここから、法華経の解説が書かれている。法華経については、すでに読んだ『日蓮 「闘う仏教者」の実像』のでも解説されている(ココとココを参照)。
法華経は、「妙法蓮華経」の略称で、原語のサンスクリットでは、「サッダルマ・プンダリーカ・スートラ」という。
- 「サッ(ト)」・・・正しい、妙なる、真実のという意味
- 「ダルマ」・・・法・真理の意味
- 「プンダリーカ」・・・白い蓮[はす]の華[はな]の意味
- 「スートラ」・・・お経の意味
すなわち、「泥の中から咲く真っ白な蓮の華のように、妙なる真実の教え」という意味である。
成立は、紀元前一世紀前後の「大乗仏教」が誕生して間もないころと推定されている。そしてその後、インドから中国に伝わり、四〇六年に鳩摩羅什が『妙法蓮華経』と漢訳した。その後、飛鳥時代に日本に伝わった。日本では、平安時代に「諸教の王」と称されている。
法華経は、八巻二十八品に分けられる大部のお経であり、前半十四品を「迹門」後半の十四品「本門」という。
その内容は、お釈迦様が晩年、古代インドのマガタ国首都、王舎城の霊鷲山で、おおぜいの弟子を前に行われた説法です(抜粋)
この「妙法蓮華経」は、六世紀に中国南方の天台山の智顗によって体系的に研究され、天台教学が大成する。智顗は、法華経の注釈書として『法華三大部』(『法華文句』、『法華玄義』、『摩訶止観』 )を著した。
そして、平安時代に最澄が天台教学の道場として比叡山延暦寺を建立し、日本天台宗を開いた。後に比叡山は仏法の最高学府となり、法然、親鸞、道元、日蓮といった鎌倉期の祖師たちも天台教学を学んだ。
日蓮は、法華経を根本経典とする宗派・日蓮宗(法華宗)を開いた。日蓮宗では、「曼荼羅」を拝むこと、「題目」を唱えることを修行の基本としている。
宮沢家の信仰は、浄土真宗でしたから、阿弥陀仏を本尊として安置し、「南無阿弥陀仏」という「念仏」を唱えるのが日常のいとなみでした。その家で育った賢治も、幼い頃より念仏を唱え、阿弥陀仏を信仰していたのです。 しかし、法華経と出会ったのち、賢治の信仰は、念仏から題目へ、「南無阿弥陀仏」から「南無妙法蓮華経」へと、そのかたちを変えることになります。(抜粋)
島地大等の「赤い法華経」
賢治の読んだ「赤い法華経」は、島地大等が編纂した『漢和対照妙法蓮華経』である。大正三年初版のその本は、いくつかの装丁のものが存在するが、賢治の持っていたものはその中で赤い表紙のもので、「赤い経巻」と呼ばれている。
背表紙には、「漢和対照妙法蓮華経」と印字されていますが、表紙には、不思議な文字が横書きで書かれています。サンクリットの「サッダルマ・ブンダリーカ・スートラ」(妙法蓮華経)です。(抜粋)
『漢和対照妙法蓮華経』の冒頭には道元をはじめ、日本の様々な宗派を代表する学僧たちが法華経を讃える文章が掲げられている。島地大等は、経典を「宗派にとらわれず、仏教思想を広く捉える」と言う立場であったためである。
島地大等は新潟県で生まれ、京都や東京で仏法を学んだ後、島地黙雷の法嗣(後継者)となった。大等は、父の姫宮大円から広く仏教の教理を学び、特に天台教学の研鑽は特筆するべきものがある。
大等は、浄土真宗本願寺派の僧侶でありながら、いろいろな宗派の教義に通じていました。それは彼の師匠である父・大円が、仏教を総体的に捉えた天台教学、古代インドの経典や中国の経釈論などを学ばせたからです。(抜粋)
関連図書:
宮沢清六(著)『兄のトランク』、筑摩書房、1987年
島地大等(編)『漢和対照妙法蓮華経』、明治書院、大正三年
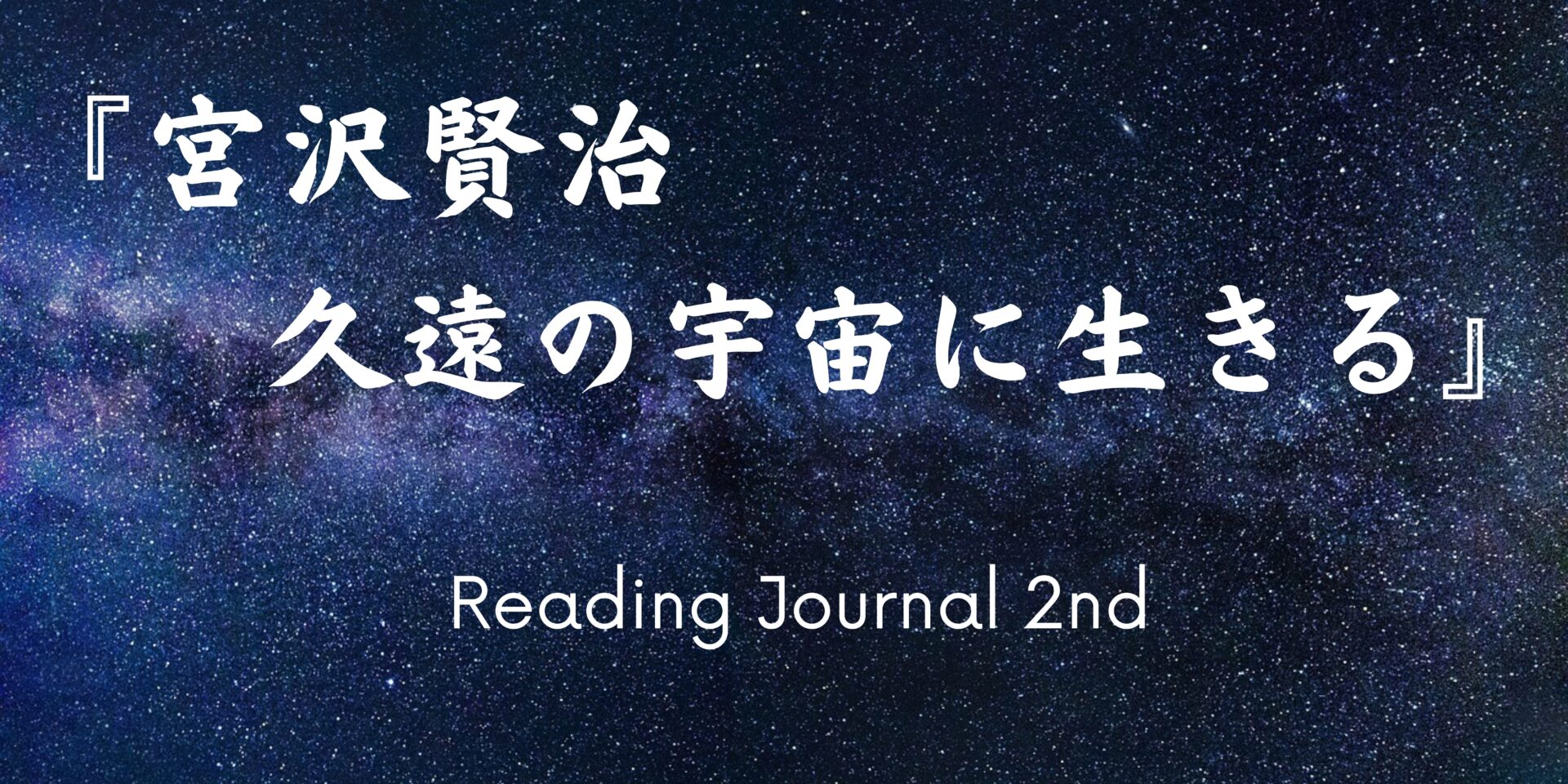


コメント