『論語入門』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第四章 孔子の素顔(その7) — 6 楽しむ孔子
今日のところは、「第四章 孔子の素顔」の“その7”(第6節後半)である。ここでは、”前回“その6”に続いて孔子が弟子たちとゆったりと語らっている条が集められている。そして、最後に「あとがき」が置かれている。それでは読み始めよう。
楽しむ孔子2
No145 由の若きは、其の死を得ざるがごとく然り
閔子 側に侍す、誾誾如たり。子路 行行如たり、冉有・子貢 侃侃如たり。子楽しむ。由の若きは、其の死を得ざるがごとく然り。(先進第十一)(抜粋)
閔子騫らがそばにすわっていた。閔子騫は誾誾如(おだやかにくつろいでいるさま)としており、子路は行行如(いかつく武ばったさま)としており、冉有と子貢は侃侃如(なごやかなさま)としていた。先生は楽しそうにしておられたが、ふと言われた。「由(子路)のような者は、天寿をまっとうできないな」。(抜粋)
この条は、孔子が閔子騫、子路、冉有、子貢とともに座っていた時の話である。他の三人が、くつろいでいる中、子路だけは、肩に力が入っていかつく構えていた。それを見た孔子が、「由(子路)のような者は、天寿をまっとうできないな」と言った。
そしてこの予感は不幸にも的中し、子路は衛の内乱に巻き込まれ、非業の死を遂げている(No89 、No94を参照)。
No146 夫子喟然として歎じて曰く、吾れは点に与せん
(NO146 は『論語』においてもっともながいため、四段階に分けるて解説されている)
子路・曾晳・冉有・公西華、侍座す。子曰く、吾れ一日爾に長ぜるを以て、吾れ以てする毋き也。居れば則ち曰く、吾れを知らざる也と。如し或いは爾を知らば、則ち何を以てせんや。(抜粋)
子路・曾晳・冉有・公西華が先生の側に座っていた。先生は言われた。「私はきみたちより少しだけ年上だが、だからといって私に遠慮しあくてもよい。(きみたちは)いつも世間が自分を認めてくれないとこぼしているが、もし認められたら、どんなことがしたいのかね」。(抜粋)
この条も、孔子と子路・曾晳・冉有・公西華の四人の高弟が一緒に座っていた時の話である。孔子がこの四人に「世間に認められた場合、何がしたいか、遠慮なく抱負をのべよ」と言ったところからこの条が始まる。
子路 率爾として対えて曰く、千乗の国、大国の間に摂まれ、之れに加うるに師旅を以てし、之れに因ぬるに飢饉を以てす。由や之れを為むるに、三年に及ぶ比おいには、勇有らしめ、且つ方を知らしむ可き也。夫子之れを哂う。求 爾は何如。対えて曰く、方六七十、如しくは五六十。求や之れを為むるに、三年に及ぶ比おいには、民を足らしむ可し。其の礼楽の如きは、以て君子を俟たん。赤 爾は何如。対えて曰く、之れを能くすと曰うに非ず。願わくは学ばん。宗廟の事、如しくは会同に、端章甫して、願わくは小相と為らん。(抜粋)
子路があわてて答えて言った。「千台の戦車を保有する小国が、大国の間にはさまって、侵略をうけ、おまけに飢饉が起こったとします。私がこの国の政治を担当したら、三年の間に、(この国の人々を)勇敢で、正しい道のわかるようにしてみせます」。先生は哄笑された、「求(冉有の本名)よ、おまえはどうだ」と言われた。冉有は答えて言った。「四方六、七十里か五、六十里の土地があるとします。私がこの土地の政治を担当したら、三年の間に、この地の人々を経済的に充足させてみせましょう。礼楽など文化的なことについては、りっぱな方におまかせします」。(先生は言われた。)「赤(公西華の本名)よ、おまえはどうだ」。答えて言った。「うまくできるとはいえませんが、学んでそうしてみたいと思うことがあります。宗廟(君主の先祖を祭る廟で行われる行事)や会同(君主たちの会合)において、玄端(礼服)や章甫(礼冠)を身につけて、小相(儀式の進行役)をつとめたいと思います」。(抜粋)
すると、
- 子路:危機に瀕した小国を救済したいと述べた。孔子は子路の意気込んだ答えを聞いて「哂」った。
- 冉有:小さな土地に的を絞って、これを経済的に充足させたいと控えめな抱負を述べた
- 公西華:国家的祭祀や行事の進行役を務めたいと、控えめな抱負を述べた
この三人は、No92でも一緒に孔子の前に集まっている。
点 爾は何如。瑟を鼓くこと希なり、鏗爾と瑟を舎きて作つ。対えて曰く。三子者の撰に異なり。子曰く、何ぞ傷まんや。亦た各おの其の志を言う也。曰く。莫春には、春服既に成り、冠者五六人、童子六七人、沂に浴し、舞雩に風し、詠じて帰らん。夫子喟然として歎じて曰く、吾れは点に与せん。(抜粋)
(先生は言われた。)「点(曾晳の本名)よ、おまえはどうだ」。瑟を爪びいていた曾晳は、かたりと瑟を置いて立ち上がり、答えた。「三人の諸君の趣旨とちがうのですが」。先生は言われた。「かまわない。それぞれの豊富を述べているのだから」。(曾晳は)言った。「晩春、春の服がすっかり仕上がったころ、冠をかぶった成年の従者五、六人と未成年の従者六、七人を連れて、沂水で水を浴びてから、舞雩(雨乞いのために築かれた土壇)に登って風に吹かれ、歌をうたいながら帰ってきたいものです」。先生はフーッとためいきをついて言われた。「私は曾晳に三世だ」。(抜粋)
そして最後に曾晳がそれまで弾いていた瑟を置いて、抱負を述べた。
この曾晳の答えに対して、著者は、ゆったりと華やいだ生の幸福感にあふれ、まことに美しい、と著者は評している。
これを聞いた孔子も、感嘆のため息をつく。このくだりは『論語』のなかでも屈指の名文とれているところである。
三子者出づ。曾晳後る。曾晳曰く、夫の三子者の言は何如。子曰く、亦た各おの其の志を言うなり。曰く、夫子何ぞ由を哂や。曰く、国を為むるには礼を以てす、其の言譲らず。是の故に之れを哂う。唯れは求は則ち邦に非ざるか。安んぞ方六七十、如しくは五六十にして、邦に非ざる者を見んや。唯れ赤は則ち邦に非ざるか。宗廟会同は、諸侯に非ずして何ぞや。赤や之れが小と為る。孰か能く之れが大と為らん。(先進第十一)(抜粋)
三人が退出し、曾晳が遅れてその場に残った。曾晳が言った。「三人の言ったことはどうでしたか」。先生は言われた。「それぞれ抱負を述べたのだから、それでいいのだよ」。曾晳はまた言った。「先生はどうして由(子路)を笑われたのですか」。先生は言われた。「国を治めるには礼によらなければならない。子路の言葉には謙遜がなく(はやりすぎで)、それで笑ったのだ。求(冉有)の言うことは国家の問題ではないか。四方六、七十里、もしくは五十、六十里の小さな土地でも国家でないものがあろうか。赤(公西華)のいうことも国家の問題ではないか。宗廟や会同は、諸侯でなければありえないものだ。赤は「小相(進行係)」になりたいと言っているが、(彼ほどの男が「小相」になったら)いったい誰が「大相」(儀式の総監督)になるのかね」。(抜粋)
子路・冉有・公西華の三人が退出した後、一人残った曾晳が孔子に、それぞれの抱負についてどうですかと尋ねた。孔子は、
- 子路:気負いすぎ、はしゃぎすぎで、謙譲の美徳に欠ける
- 冉有・公西華:ともに謙虚すぎて、おおらかな抱負を述べるに至っていない
と言った。
総じて孔子は、風に吹かれてわが道をゆく曾晳やシンプルな暮らしを楽しんだ顔回のような生きかたに、つよく魅かれていたと思われる。しかし、その一方で、孔子は、人が他者との関わりのなかで生きる社会的な存在であることを痛感していた。あらまほしき社会的関係性の構築を模索しながら、自己本来の自在な生きかたを保つこと。それは、まさしく孔子の見果てぬ夢だったといえよう。(抜粋)
あとがき
あとがきで、著者はこの本が、五百余条からなる『論語』から百四十六を抜き出し、「孔子の人となり」「考え方の原点」「弟子たちの交わり」「孔子の素顔」に分類したと記している。この分類をするために著者は『論語』の全文をひたすらパソコンに打ち込んだと言っている。
そのあと、著者と『論語』の関りについて、刊行の際にお世話になった人たちへのねぎらいの言葉が書かれている。
この本は、最初にあとがきを読んで、146条を抜き出したと知っていたので、最初からNo.を振ってまとめた。全体で500余条であるから、1/3弱である。『論語』というと何か、堅苦しいというイメージだったが、以外にもそうでなかった。
また、本書ある、孔子が悪女として名高い南子に謁見した話(No89)のところで紹介された谷崎潤一郎の『麒麟』を読んだ。『麒麟』の最後が、本書のNo.131
「吾未見好徳如好色者也[われいまだとくをこのむこといろをこのむがごとくなるものをみざるなり](抜粋)
で終わっていて、これを知っていることに、多少の優越感がありました。
著者の孔子のイメージは、基本的にゆったりとして陽気なものであるようで、そういう雰囲気もあってか、すごく身近なところに孔子が来てくれたような気がした。(つくジー)
関連図書:谷崎 潤一郎(著)『刺青 痴人の愛 麒麟 春琴抄』 、文藝春秋(文春文庫・現代日本文学館)、2021年
[完了] 全24回
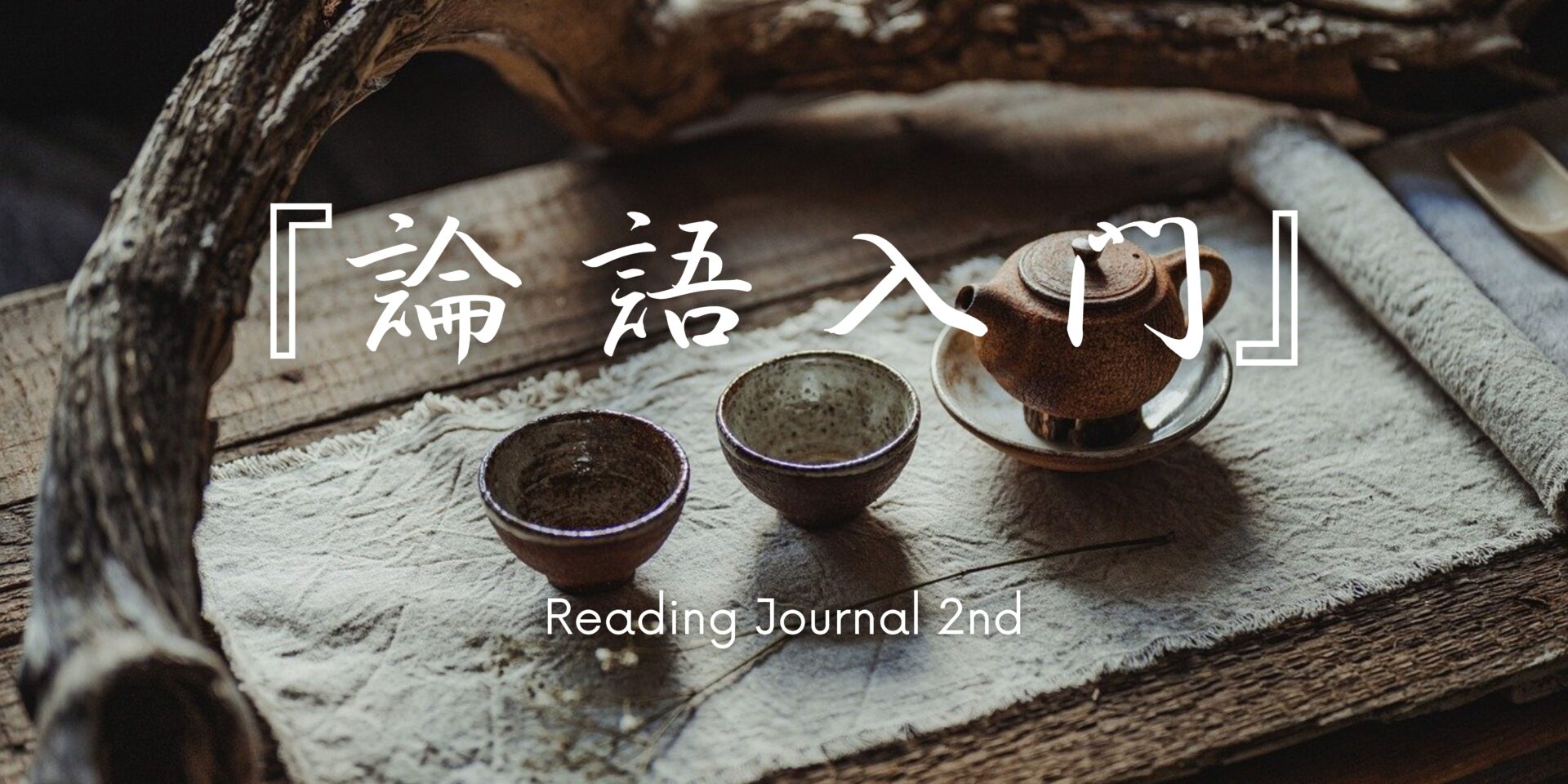


コメント